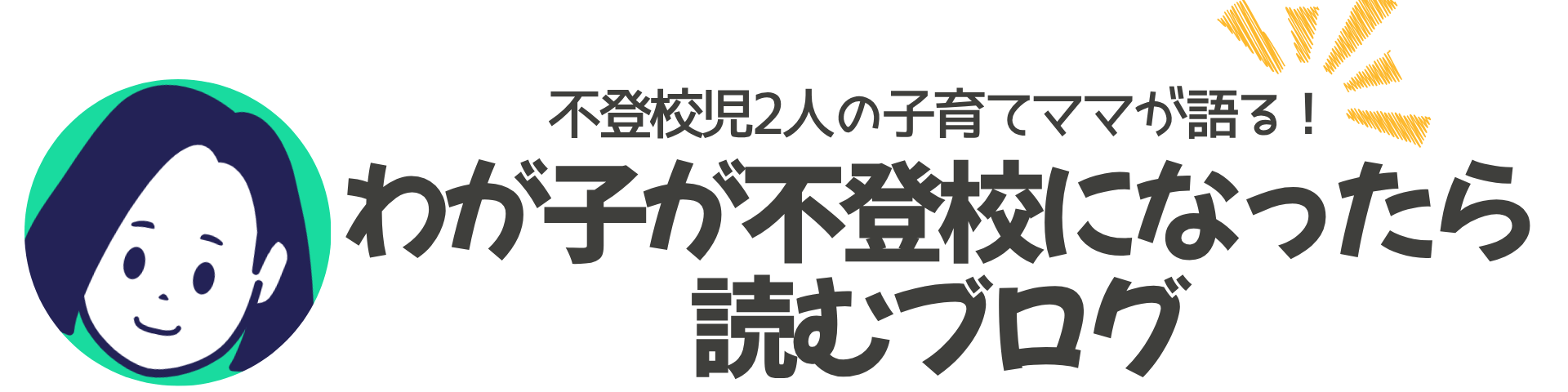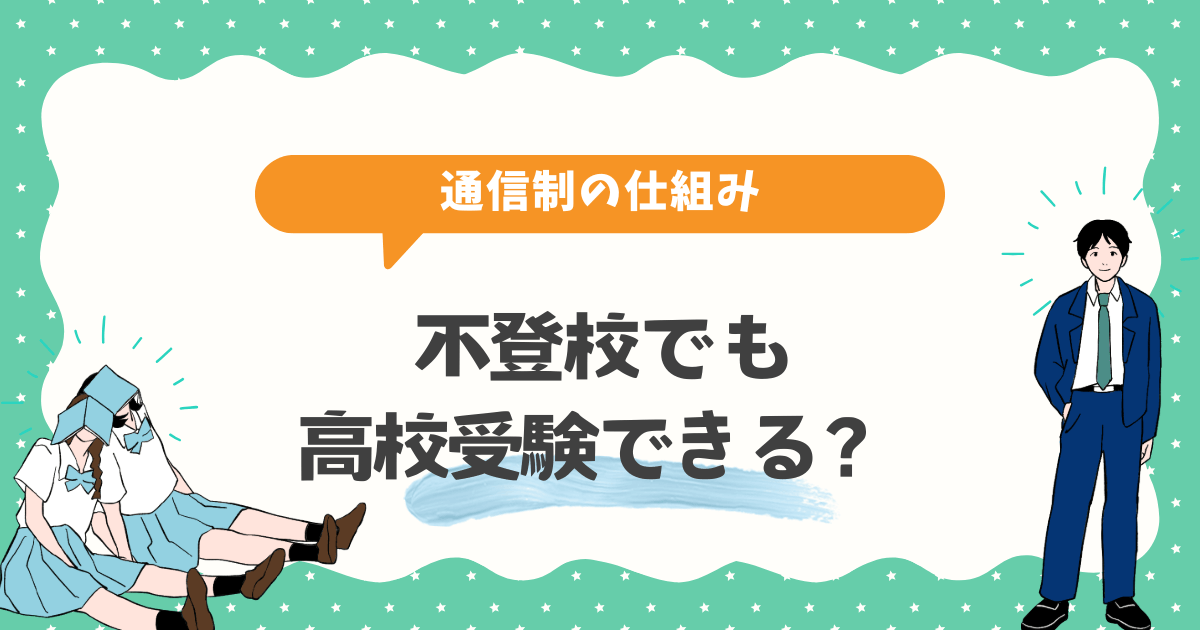「不登校でも高校受験できるの?」
そんな不安を抱える親御さんは、とても多いです。
出席日数や内申点、推薦入試の条件…調べるほど情報は増えるのに、結局どう考えればいいのか迷ってしまいますよね。
結論からお伝えすると、不登校でも高校受験は可能です。
全日制・定時制に加えて、通信制高校という柔軟な選択肢も広がっています。
この記事では、受験に必要な基本、推薦・受験科目の考え方、通信制高校の仕組みを分かりやすく整理しました。
学校選びをスムーズにする資料請求のコツや、親ができるサポートまで、私の経験も織り交ぜながら紹介します!
通信制高校のホームページでは、募集要項や学費は資料請求で掲載されている場合があります。まずは気になる学校をまとめて取り寄せておくと、安心です。
【無料】気になる学校をまとめて資料請求できます!
不登校でも高校受験は可能?基本の考え方

高校受験に必要な条件とは?
「不登校だと受験は無理?」と心配になりますが、実際は学校ごとの選考基準に合えば受験・合格のチャンスは十分にあります。
必要な条件は学校によって異なりますが、基本はつぎの3つを組み合わせて評価されます。
- 調査書:内申点・出欠・行動の記録など
- 学力検査:公立一般入試などで実施
- 面接・作文:推薦や通信制で重視されやすい
ポイントは、出席が少なくても評価の取り返しが利く方式があること。
たとえば、
- 公立高校:学力重視の学校では「当日の得点」で挽回可能
- 私立高校:面接・志望理由・適性をていねいに見る学校が多い
- 通信制高校:過去よりも「これからの学び方」を重視する傾向
大切なのは、お子さんの今の状態に合う入試方式を選ぶこと。
早めに募集要項を集め、必要な準備(基礎学力・志望理由・面接練習・提出書類)を無理のない計画に落とし込んでいきましょう。
出席日数が少なくても受験できるケース
出席が少ないと不利に見えますが、出席が少なくても合格した事例は珍しくありません。
理由は、評価の軸が学校で違うからです。
公立では学力検査の配点が高い地域・学校もあり、当日のテストでしっかり点が取れれば合否に直結します。
私立では、面接や志望理由の具体性、本人・家庭の支援体制が丁寧に見られることも多く、通信制ではスクーリング中心の学びに合うかどうかが重視されやすいのが特徴です。
確認しておきたいのは次の点です。
- 地域差:同じ「公立」でも都道府県で配点・運用は違う
- 学校差:同県内でも学校ごとに評価のクセがある
- 準備物:欠席の背景を前向きに説明(医療・カウンセラー・学校の記録が役立つことも)
- 情報源:最新の募集要項・説明会で今年の要件を必ず確認
出席の少なさを「弱み」とだけ捉えず、これからどう学んでいくかを言葉にしていけると前進しやすくなります。
不登校生の高校受験でよくある悩み

内申点はどうなる?
不登校の期間があると、どうしても内申点は下がりやすいもの。定期テストや提出物の機会が減るからです。
ただし、学校によっては、補習・追試・提出物の提出で評価の機会を設けてくれることがあります。
まずは担任や学年主任に相談し、今からできることを確認しましょう。
受験戦略としては次の考え方が現実的です。
- 学力配点が高い学校を志望(当日の点で挽回)
- 推薦・書類重視の私立や通信制を併願
- 得意科目で加点のある方式(特待・単願推薦など)を検討
- 志望理由書で「今後の学習計画」を具体化(未来志向で)
内申の低さは「過去の結果」。ここからは、これからの学び方を示していけば大丈夫。
面接や書類では、家庭での支援体制(生活リズム、学習環境、相談先)も合わせて伝えられると安心材料になります。
 ゆき
ゆき我が家の地域では、3年生になって2学期までの欠席日数が30日を超えてしまうと、全日制高校の受験自体が難しかったです。
地域差や学校の方針によって違いがあるので、中学校の先生に相談することをおすすめします。
「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
引用:不登校への対応について|文部科学省
推薦入試は受けられる?
推薦の条件は学校ごとに違います。
多くは「中学校長の推薦」「一定の内申基準」「出席や生活態度」などが条件になりますが、自己推薦(自己PR)や活動実績の提出など、内申の基準が柔らかい方式を持つ学校もあります。
私立は学校独自の推薦枠が豊富で、面接・作文の比重が高いケースも多め。
通信制はそもそも書類+面接中心の選考が一般的で、推薦の枠組みが緩やかなことが少なくありません。
準備すると良いポイントは次のとおりです。
- 募集要項で推薦要件を正確に把握
- 担任と相談し、狙える学校を複数ピックアップ
- 自己推薦書には「学び直しの意欲」「続ける工夫」「将来像」を具体的に
- 一般入試も残しておく(安全策)
推薦は「伸びしろ」と「適合性」のアピールが大切。できていることを数値化・記録化して伝えましょう。



これらの条件は、私立高校や技能連携校が主になります。
公立高校の入試では、学力検査の点数と、中学校から提出される調査書(内申書)の評価を総合して合否を判定されるからです。
お住いの地域で、不登校の生徒を対象とした独自の選抜方法がある高校があるか、中学校の先生に確認してみましょう。
学力テストの対策は必要?
受験する学校が筆記試験ありなら、対策は必要です。
ここで大事なのは、完璧主義にしないこと。短時間×高頻度で基礎の積み直しをしていけば十分に届きます。
おすすめの組み立ては次の通り。
- 英・数・国の土台(計算・語彙・文法・読解)を毎日15〜30分
- 理・社は頻出分野を優先(用語→基本問題→資料読み取り)
- 過去問は1教科ずつ:「解く→見直す→同タイプ反復」
- 映像授業・AI教材・個別指導・フリースクールの学習サポートを併用
- 面接・作文の練習も週1回ペースで
もし筆記なしの学校を中心に選ぶなら、学力対策は最小限でもOK。
ただし、入学後の学習をスムーズに進めるためにも、基礎は整えておくと安心です。



「やれた量」を見える化すると自信につながります。
不登校生におすすめの進学方法
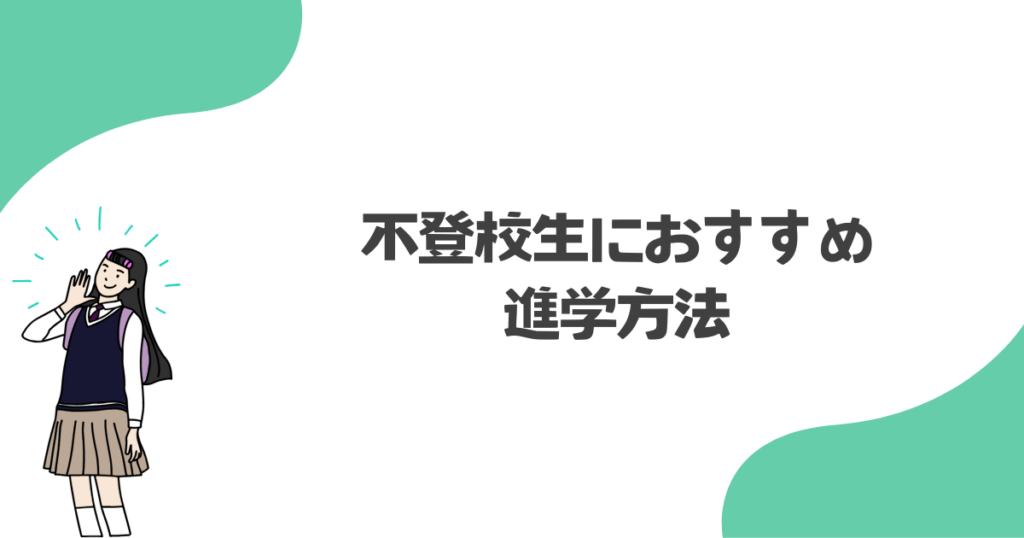
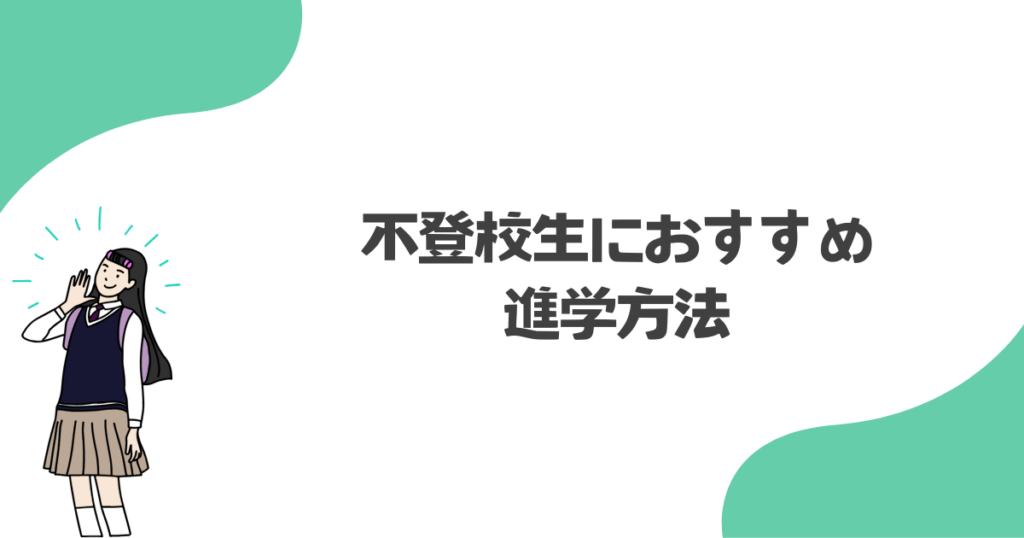
通信制高校という選択肢
通信制高校は、自分のペースで学べる柔軟さが強みです。
通学は年数日〜週1・2日など学校により幅があり、体調や気分の波があるときも無理なく続けやすい仕組みになっています。
学び方のイメージは次のとおり。
- 在宅中心:動画・オンライン授業、レポート提出
- スクーリング:必要日数、面接指導・実技を対面で
- コース:進学/資格/専門分野(IT・デザイン・美容など)
- サポート:担任面談、学習コーチ、カウンセリング など
良い点は、人間関係の負担が小さく、小さな成功体験を積みやすいこと。
一方で、自己管理の比重が高いため、家庭の見守りやサポート校の併用が力になります。
雰囲気・学費・通学負担は学校差が大きいので、必ず複数校の資料を取り寄せて比較→見学・体験まで進めましょう。



わが子の通信制高校を検討するために、色々な学校の資料を取り寄せました。
ズバット通信制高校比較は、気になる学校をまとめて請求できるので、情報入力も1回で済むので、とても便利でした。
紙の資料は並べて比較できるので便利だったし、とても活用できました。
【無料】気になる学校をまとめて資料請求できます!
通信制高校の仕組みと特徴
通信制は単位制。レポート(添削)+メディア授業(オンライン等)+スクーリング+試験で単位を積み上げ、必要単位を満たすと卒業です。
入学時期が4月・10月(学校により随時)など柔軟で、やり直しのタイミングを選べるのも安心材料です。
費用は、公立は比較的低廉、私立はコース・サポート有無で差が出ます。チェックポイントを確認しておきましょう。
- 総費用(授業料+諸費用+スクーリング+サポート校費)
- 通学頻度・場所(オンライン併用の可否)
- 進学・就職の実績(大学併修、専門連携、インターン)
- 不登校支援の経験(段階的な登校、別室対応、メンタルケア)
パンフレットだけでなく、個別相談で具体的な支援を確認しておくと、入学後のつまずきを減らせます。
全日制・定時制との違い
どれが正解ではなく、お子さんに合う環境を選ぶことが大切です。
- 全日制:毎日登校、クラス活動・行事が豊富。通学負担は大きめ
- 定時制:登校時間帯や在学年数が柔軟。働きながら通う人も多い
- 通信制:在宅+必要スクーリング。人間関係の負担を抑えやすい
選ぶときは、以下のこともチェックしておきましょう。
- 通学頻度/生活リズム
- 学費/通学時間
- サポート体制/進学実績 を横並びで比較。
通信制高校は、全日制高校とは違うことが多いので、体験授業・見学で、学校の雰囲気や先生の距離感を確認しましょう。
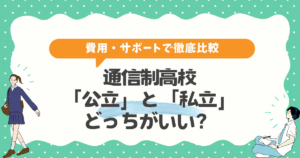
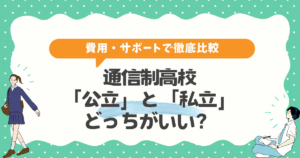
通信制高校の受験科目と入学方法
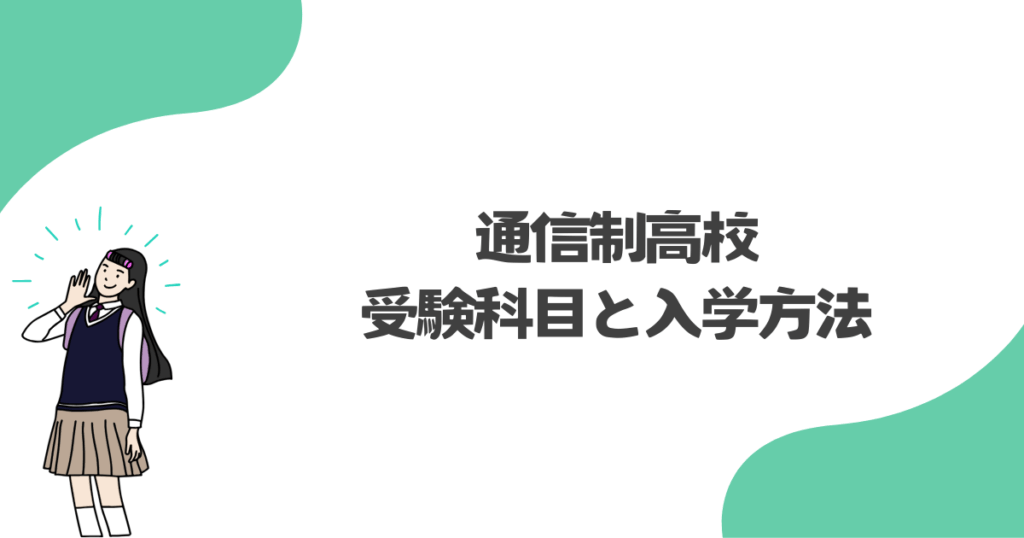
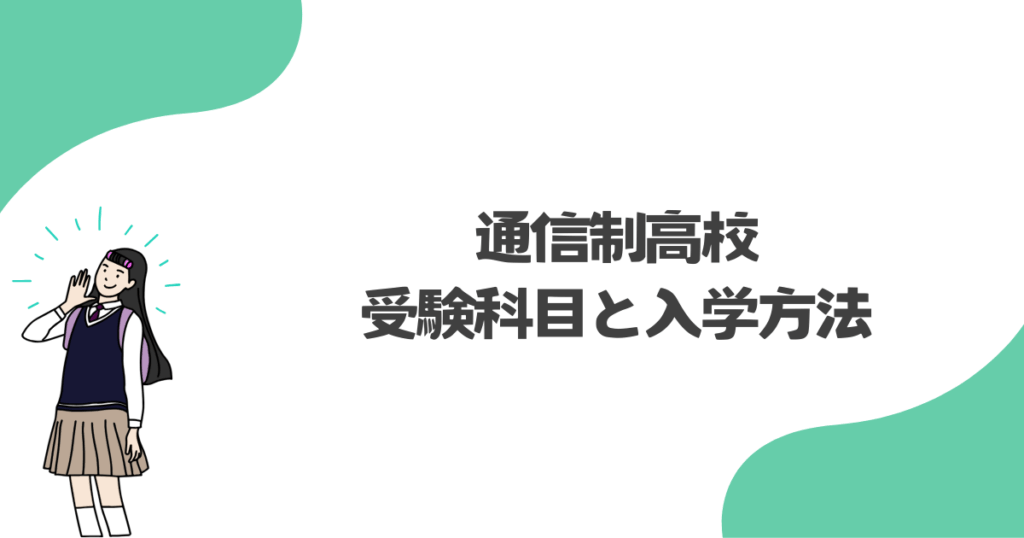
一般入試と推薦入試の違い
通信制高校の「一般入試」は、学力試験ではなく書類+面接(+作文)が中心の学校が多めです。
いわゆる筆記なしのパターンも珍しくありません。
いっぽうで「推薦」に相当する枠(学校長推薦・自己推薦など)もあり、学習意欲・将来目標・学校との相性が見られます。
出願時期は春・秋・随時など柔軟な学校も。事前にここを確認しましょう。
- 筆記の有無/作文のテーマ例
- 面接形式(個別・集団・保護者同席)
- 志望コース(進学・専門・総合)と学びたい理由
「なぜ通信制?」「なぜその学校?」が具体的に語れると、合格可能性はグッと上がります。
必要な学力・書類・面接のポイント
通信制で特に大切なのは、「基礎学力+継続意欲」。
筆記がなくても、計算・語彙・読解の土台はレポート学習の強い味方です。
準備は次の流れがスムーズ。
- 書類:調査書/志望理由書/学習・活動の記録/健康状況
- 志望理由:不登校の経緯は簡潔に、今後の学び方とサポート体制を具体化
- 面接:なぜ通信制・なぜこの学校?在宅学習とスクーリングのペース、将来の目標(進学・資格・就職)、困った時の相談先(担任・カウンセラー・保護者)
保護者同席の面接では、家庭での支援計画(生活リズム、通院やカウンセリングの継続、学習環境)が伝わると、安心して迎えられる印象につながります。
不登校生が有利になるケースとは?
通信制では、「今の状態に合う学び方を選べているか」が評価されやすく、不登校の経験が自己理解や学び直しの動機として言語化できているとプラスに働くことがあります。たとえば、
- 通学負担を抑え、基礎からやり直したい
- 得意分野(IT・デザイン等)に集中して伸ばしたい
- 体調やメンタルと両立できる計画を持っている
活動実績が多くなくても、家庭学習の記録・読書メモ・オンライン講座の修了・検定挑戦など「続けてきた証拠」が強いアピールになります。
面接では過去のつらさを詳細に語るより、そこから何を学び、今どう行動しているかに焦点を当てましょう。
フリースクール・医療・カウンセリングと連携していることなども、継続性の根拠になります。
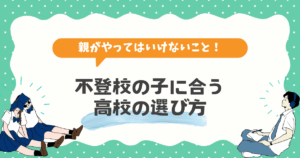
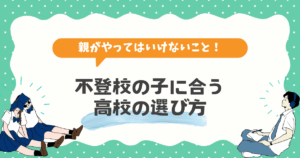
まとめ|不登校でも高校受験はできる!親ができるサポート


進学の選択肢を広げるために
不登校でも、全日制・定時制・通信制の道は開かれています。
大切なのは、今の状態に合う方式と環境を選ぶこと。そのために、次の3ステップで動くと迷いにくくなります。
- 早めの情報収集:募集要項・説明会・資料請求
- 横並び比較:学費・通学・サポート・実績を同じ物差しで
- 相性確認:見学・体験授業で「続けられる感触」を確かめる
学力試験が必要なら基礎の積み直し、面接・書類中心なら志望理由・学び方・支援体制を言語化。親御さんが選択肢を整える役割を担うだけで、お子さんは「選べる安心」を得られます。
まずは中学校の先生とよく相談して、お子さんにあった高校への進学を考えてみましょう。
知りたい情報がきっと見つかる!
お子さまにぴったりの通信制高校を見つけるには、複数の学校を比較することが大切です。
学費、サポート体制、通学日数やキャンパスの雰囲気など、あなたの不安を解消するリアルな情報をまとめてチェックしましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる