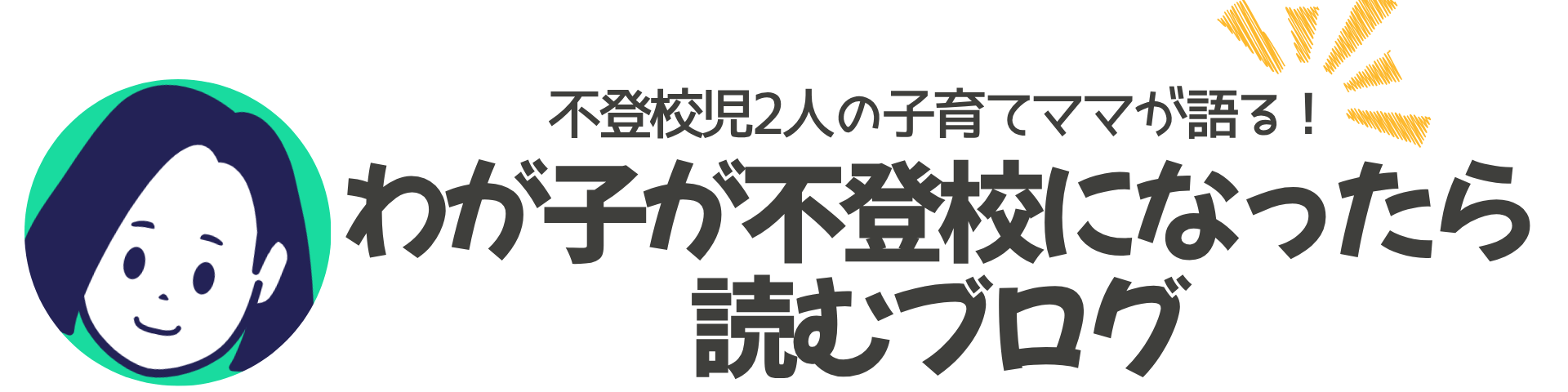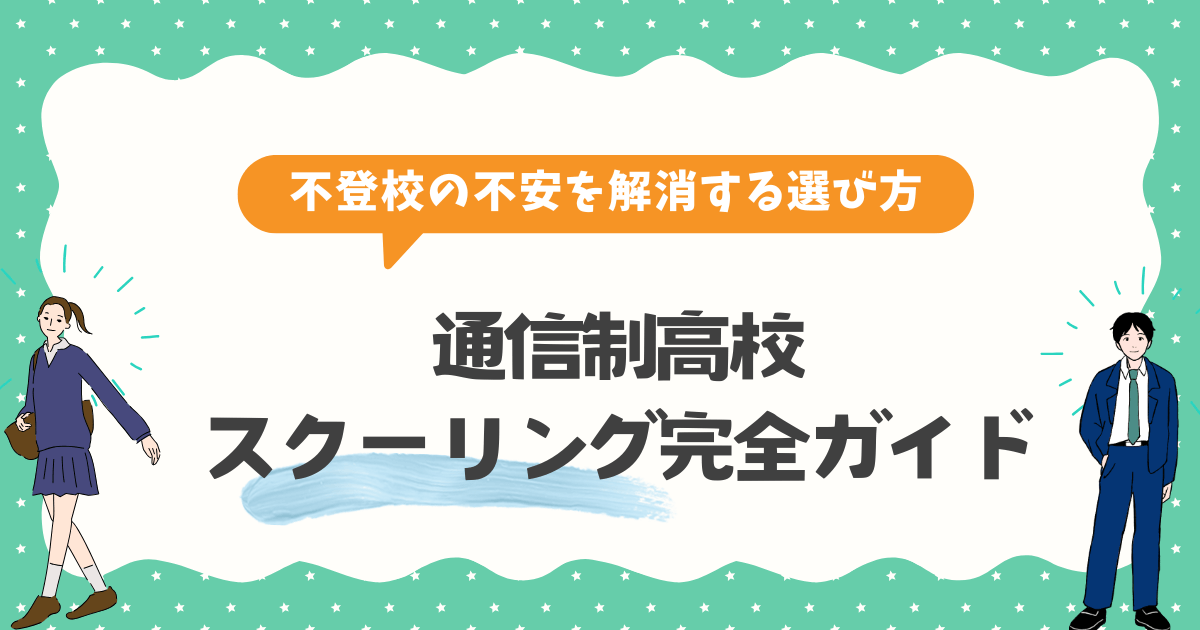「通信制高校」への進学を考えたとき、「スクーリングって結局何をやるの?」「毎日学校に行けなかった子が、急に登校できるのだろうか…」という不安が、一番大きな壁となって立ちふさがるのではないでしょうか。
スクーリング(登校)の回数が少ないことが通信制高校の最大のメリットであるにもかかわらず、その「登校しなければならない日」の心理的ハードルは、不登校を経験したお子さまにとって計り知れません。
特に、授業内容、雰囲気、そして費用など、情報が少ないがゆえに、漠然とした不安が増幅してしまうものです。
でも、安心してください!現在の通信制高校のスクーリングは、お子さまの状況に合わせて選べる、多様な形態があるんです。
決して、厳しい全日制の授業と同じではありませんし、学校側も不登校経験者への配慮を万全に行っています。
この記事では、通信制高校のスクーリングを「卒業に必須な理由」から「負担を最小限に抑える3つのタイプ」、そして「人と関わらないための具体的な戦略」まで、網羅して解説していきます。
この記事を読んで、スクーリングに対する不安が解消され、お子さまに最適な学校選びの道筋が見えてきたら嬉しいです。
スクーリングは学校毎に違うことが多いので、お子さまにあった学校を選ぶために、まずは資料請求をしておくと安心です。紙の資料は並べて比べられるので、手元に置いておくと便利です。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
スクーリングは「卒業に必須」だけど負担は最小限に抑えられる

通信制高校のスクーリングは、レポート提出やテストと並んで、高校卒業資格を得るために法律上必ず必要な要件です。
しかし、この「登校義務」は、お子さまの心身の負担を考慮し、柔軟な仕組みとなっています。
1. スクーリングの法的定義と卒業要件
通信制高校のスクーリングは、法律で定められた「面接指導(対面授業)」を受けるためのものであり、これを規定の時間数こなさなければ、どれだけレポートやテストをクリアしても卒業資格は得られません。
学校教育法に基づき、高等学校卒業資格を取得するためには、必ず対面での授業である「スクーリング」に参加する必要があります。これは、公立・私立、地域限定・全国展開を問わず、すべての通信制高校に共通するルールです。参考文献:高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編、高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン
文部科学省の定める学習指導要領において、高校教育は「教員による直接の指導」が不可欠とされています。
通信制高校では、この直接指導を「スクーリング」という形で実施することで、全日制高校と同じ卒業資格の質を担保しているからです。
- 卒業要件(3つの柱)
- 必須条件: ① 3年以上の在籍 ② 74単位以上の修得 ③ 規定時間数以上のスクーリング受講
- 単位修得に必要な時間
- 目安: 1単位あたり最低1回(50分)以上の面接指導(スクーリング)が必要です。(多くの学校ではこの基準を上回る時間を設定しています)
- スクーリングの性質
- 内容: 教員による一方的な講義だけでなく、実験・実習、グループワークなど、レポート学習では難しい対面での学びや交流が中心となります。
- 注意点: スクーリングを理由なく欠席すると、その科目の単位を落とすことになり、卒業が遅れる原因となります。
2. レポート・テストとの関係性
レポート(添削指導)とテスト(単位認定試験)は「自宅学習の成果を評価する」もの、スクーリングは「教員による直接指導を担保する」ものであり、それぞれが独立した卒業要件の柱となっています。
卒業に必要な3つの要件(レポート、テスト、スクーリング)は、どれか一つでも欠けると単位が認められません。
レポートで学習内容を理解し、テストで知識を確認し、スクーリングで直接指導を受けることで、初めてその科目の単位が修得できる仕組みだからです。
- レポート(添削指導)
- 役割: 学習内容の確認と、教員からの個別指導(添削)を受ける。提出が遅れるとスクーリングやテストが受けられなくなる。
- テスト(単位認定試験)
- 役割: 規定のスクーリング時間を満たした上で、その科目の知識が身についているかを評価する。
- スクーリング(面接指導)
- 役割: レポートやテストの成績が良くても、受講時間が不足すれば単位は認定されない。
- 親御さんへのアドバイス: お子さまの負担を減らすためには、レポートを計画的に提出し、スクーリングをスムーズに終えることが大切です。
【頻度・内容別】スクーリングの「3つのタイプ」を徹底比較

通信制高校のスクーリングは、学校やコースによって大きく3つのパターンに分かれます。
お子さまの「登校への不安のレベル」に合わせて、最適なタイプを選びましょう。
1. 集中型(年5~10日程度):登校負担を最小限にしたい人向け
登校回数を極限まで減らしたい、または遠方に住んでいるお子さまにとって、年間に数回、短期間で集中して登校する「集中型」が最も負担の少ない形態です。
このタイプは、年に一度や二度、数日間にわたって集中的に授業を受けることで、その年度のスクーリングをまとめて終えることができます。
自宅から遠い広域通信制高校の本校などで実施されることが多く、登校のための心理的な準備を年に1回~2回行えば良いというメリットがあります。
集中型スクーリングの主な特徴
- 登校頻度と期間
- 目安: 年間5日~10日程度。(多くは夏季や特定の時期に集中)
- 形態: 連続した数日間で実施されるため、宿泊が伴うことが多い。(学校やキャンパスによる)
- 向いている生徒
- 適性: 登校への強い抵抗がある、遠方に住んでいる、仕事やプロ活動など、学業以外の活動と両立させたい生徒。
- 注意点
- 心理的負担: 登校日数が少ない分、一度の登校で長時間・長期間人と接するため、緊張感が続く可能性がある。
- 費用: 交通費や宿泊費が自己負担となるため、事前に費用の総額を確認しておく必要がある。
2. 分散型(月1回~週1回程度):無理なく学習習慣をつけたい人向け
登校の習慣を少しずつ身につけたい、または自宅学習だけでは不安があるお子さまには、月に数回、決まった曜日に通う「分散型」が、無理のないリズムを作れます。
狭域通信制高校は分散型が多く、決まったリズムで登校することで、生活習慣が整いやすく、不登校からの社会復帰のトレーニングとしても機能するメリットがあります。
また、週1回程度の登校で教員に直接質問することができるので、レポート作成や学習のつまずきを早期に解消できます。
分散型スクーリングの主な特徴
- 登校頻度と期間
- 目安: 月に1~4回(週1回程度)など、比較的規則的なペース。(年間20日~30日程度)
- 形態: 狭域通信制高校や居住地の近くにあるサポートキャンパスなどで実施されることが多く、宿泊は不要な場合がほとんど。
- 向いている生徒
- 適性: 自宅学習だけでは不安がある、学習の質問をしたい、規則正しい生活リズムを少しずつ取り戻したい生徒。
- 注意点
- 自己管理: 集中型に比べ、毎月の登校日を意識し、生活リズムを乱さない自己管理が求められる。
- 通学のしやすさ: 近くにキャンパスがあるかどうかが、継続的な通学の鍵となる。
3. 通学型(週3~5日程度):全日制に近い環境を求める人向け
不登校の原因が克服されて、全日制に近い環境で手厚いサポートや指導を受けたいという強い意欲があるお子さまには、「通学型」のコースが最適です。
このコースは、実質的に私立のサポート校と通信制高校の仕組みを組み合わせており、毎日の登校を通じて、全日制と変わらない学習指導や進路指導、友人との交流機会を得ることができます。
公立の通信制高校や狭域通信制高校で多く、通信制高校の卒業資格を得ながら、より手厚い環境で高校生活を送りたい生徒に人気です。
通学型スクーリングの主な特徴
- 登校頻度と期間
- 目安: 週3日~週5日など、ほとんど毎日登校。(全日制と同じような時間割で過ごす)
- 形態: 個別指導や少人数クラスでの授業が中心で、全日制のような大人数での一斉授業ではない場合が多い。
- 向いている生徒
- 適性: 既にメンタルが安定しており、大学進学を目指したい、社会性を回復したい、手厚い進路指導を望む生徒。
- 費用
- 注意点: 通学することがスクーリングの条件になっていることも多いので、登校できない場合は単位取得が難しくなる場合もある。
4. 【補足】オンライン授業の活用で「登校回数を減らす」戦略
通信制高校の多くがオンライン授業やオンデマンド配信を導入していますが、これらは「学習サポート」として活用されることが主であり、スクーリング(面接指導)の時間をすべて代替することはできません。
文部科学省は、オンラインによる面接指導を一部認めていますが、すべての授業をオンラインで済ませることはできません。
対面での指導や交流というスクーリング本来の目的を果たすため、登校回数をゼロにすることは不可能だからです。
- 登校時間の軽減
- 効果: オンライン授業を併用することで、スクーリングで求められる時間数の一部を自宅で受講できる学校が増えている。
- 学習の遅れの解消
- 効果: 苦手科目の復習や予習にオンラインコンテンツを活用することで、登校日までにレポート提出の準備を整えやすい。
- 学校選びの基準
- 注意点: オンラインでどれだけの時間が代替可能か、学校によってルールが大きく異なるため、入学前に必ず確認すること。
知りたい情報がきっと見つかる!
お子さまにぴったりの通信制高校を見つけるには、複数の学校を比較することが大切です。
学費、サポート体制、通学日数やキャンパスの雰囲気など、あなたの不安を解消するリアルな情報をまとめてチェックしましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校の不安を解消!スクーリングで「人と関わらない」ための戦略

スクーリング最大の不安は、「大勢の中に入らなければならないこと」ではないでしょうか。
学校側もその不安を理解しており、人と関わる負担を減らすための様々な配慮を行っています。
1. 個別指導・少人数制クラスの積極的な利用
スクーリングでの対人負担を減らすために、少人数制クラスや個別指導が受けられる私立高校を選ぶことで、集団での緊張を避けることができます。
多くの私立通信制高校では、生徒一人ひとりに教員が寄り添うことを重視しており、大人数のクラスでの一斉授業ではなく、数人程度のグループやマンツーマンでの指導時間を多く設けています。
これにより、生徒は自分の発言が目立ってしまう不安を感じずに、安心して学習に取り組めます。
- コース選びの基準
- 選択基準: 個別指導や担任制を売りにしている学校を優先的に検討する。
- クラスの雰囲気
- 確認手順: 学校見学や個別相談の際に、「スクーリング時のクラスの人数や、授業中の雰囲気」を具体的に質問する。
- 授業以外の過ごし方
- 提案: 休憩時間などに無理に友人と関わろうとせず、図書室や自習スペースなど、一人で静かに過ごせる場所を事前に確認しておく。
2. オンラインコースを選択する
通信制高校には、通学の負担を最小限に抑えられるオンラインコースが多く用意されています。
オンライン学習では、ほとんどの授業を自宅で進められるため、人と関わる機会を極限まで減らしたいお子さまにとって大きな安心材料となります。
ただし、 どんなにオンライン学習を進めても、法律で定められたスクーリング(対面指導)だけは必ず必要になります。
このスクーリングの形態は、学校によって大きく異なるため注意が必要です。
- 広域通信制高校の場合
- 特徴: 本校が遠方にあるため、宿泊を伴う集中型スクーリングが多くなります。また、一度に多くの生徒が集まるため、大人数での実施となることがほとんどです。
- 注意点: 登校回数は少ないですが、宿泊や大人数での交流に抵抗がある場合は慎重な検討が必要です。
- 狭域通信制高校の場合
- 特徴: 比較的、自宅から通える校舎での実施が多くなります。宿泊を伴わず、月に数回程度、校舎に出向いて授業を受ける分散型のパターンが主流です。
- メリット: 登校のリズムを少しずつつかみやすく、心理的な負担が少ないため、不登校経験者にも適しています。
3. 事前の相談と学校側の配慮(別室登校など)
スクーリングへの不安や、対人関係への抵抗がある場合は、入学前または登校前に必ず学校側に相談することで、生徒の状態に合わせた最大限の配慮を受けることができます。
通信制高校の教員は、不登校経験者への対応に慣れています。
不安を隠さずに正直に伝えることで、教員は教室の座席配置や、休憩時間の過ごし方、緊急時の対応などについて具体的な配慮をすることができます。
学校側に相談すべき具体的な内容
- 相談すべきこと(生徒の状態)
- 内容: 「大勢の教室が苦手」「特定の時間に体調が悪くなる」「休憩時間が不安」など、具体的な不安要素を伝える。
- 学校側が提供できる配慮の例
- 配慮: 教室の出入り口に近い席への配置、別室での個別対応(別室スクーリング)、体調不良時の休憩スペースの提供など。
- 親の役割
- 手順: 親御さんが学校側に電話で連絡し、お子さまの状況を細かく伝え、無理のない登校スケジュールについて事前に話し合う。
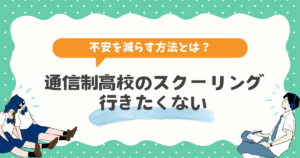
費用と注意点:スクーリングでかかる隠れたコスト

スクーリングは学費とは別に、交通費や宿泊費といった追加のコストがかかる場合があります。
金銭的な不安を解消するためにも、事前に隠れたコストを把握しておきましょう。
1. 交通費・宿泊費の目安と補助制度の有無
集中型スクーリングや遠方への登校が必要な場合は、交通費や宿泊費が年間で数万円~十数万円かかる可能性があるため、事前の確認は必須です。
スクーリングのための交通費や宿泊費は、原則として自己負担となる学校がほとんどです。
特に、本校が遠方にある広域通信制高校の場合、この費用が大きな負担となることがあります。
スクーリング費用の目安と確認事項
- 費用の目安:
- 交通費: 居住地からキャンパスまでの往復交通費を計算する。(集中型の場合は年数回分を合算)
- 宿泊費: 集中型スクーリングで宿泊が必要な場合、年間数万円が必要となることが多い。
- 学校への確認事項:
- 質問: スクーリングの会場は本校のみか、近くのキャンパスでも可能か? 宿泊が必須か、日帰りが可能か?
- 補助制度の有無:
- 注意点: 学校によっては、遠方からの生徒を対象に交通費の一部を補助する制度や、提携宿泊施設を安価で提供している場合があるため、必ず確認する。
 ゆき
ゆき我が家のスクーリングでかかった費用(年1回)です。
【息子】交通費:約4万円、宿泊費:別請求はなし、その他:行き帰りの食事代、お土産代など
【娘】交通費:約8万円、宿泊費:別請求はなし、その他:行き帰りの食事代、お土産代など
2. スクーリングでの単位不認定を避けるための注意点
スクーリングで単位を落とさないためには、遅刻や欠席に対する学校のルールを厳守し、体調不良などによる欠席が避けられない場合は速やかに学校に連絡することが鉄則です。
スクーリングは「面接指導」という法的要件を満たすため、規定の時間数を1分でも満たさないと、その科目の単位は認定されません。
レポートやテストの成績が良い場合でも、時間不足は卒業に直結する大きな問題となります。
- 遅刻・欠席の基準の確認
- 手順: スクーリングの遅刻・欠席の許容時間を事前に確認し、それを超えそうになったら担任に相談する。
- 緊急時の連絡体制
- 手順: 体調不良で欠席が確実な場合は、開始時間前に必ず学校に連絡し、振替授業や補習の可能性について相談する。
- 振替・補習制度の確認
- 注意点: スクーリングを欠席した場合、翌年度に再度受講(再履修)となるのが基本ですが、学校によっては有料の補習を受けられる場合がある。
まとめ|通信制高校のスクーリングは成長の場!


通信制高校のスクーリングは、卒業に不可欠な要件ではありますが、お子さまの心身の状態に合わせて、「集中型」「分散型」「通学型」の中から最適な形を選べます。
「不登校だった子どもに、ちょっとハードルが高いかも…」と心配になる気持ちもよく分かります。
でもスクーリングは、決して怖い場所ではなく、普段交流することがない人たちとの交流、学習の手ごたえを感じるための大切な場です。
いくつか候補になりそうな学校の資料をまずは取り寄せて、スクーリングの形態やサポート内容を確認してみることから始めてみましょう。
知りたい情報がきっと見つかる!
お子さまにぴったりの通信制高校を見つけるには、複数の学校を比較することが大切です。
学費、サポート体制、通学日数やキャンパスの雰囲気など、あなたの不安を解消するリアルな情報をまとめてチェックしましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる