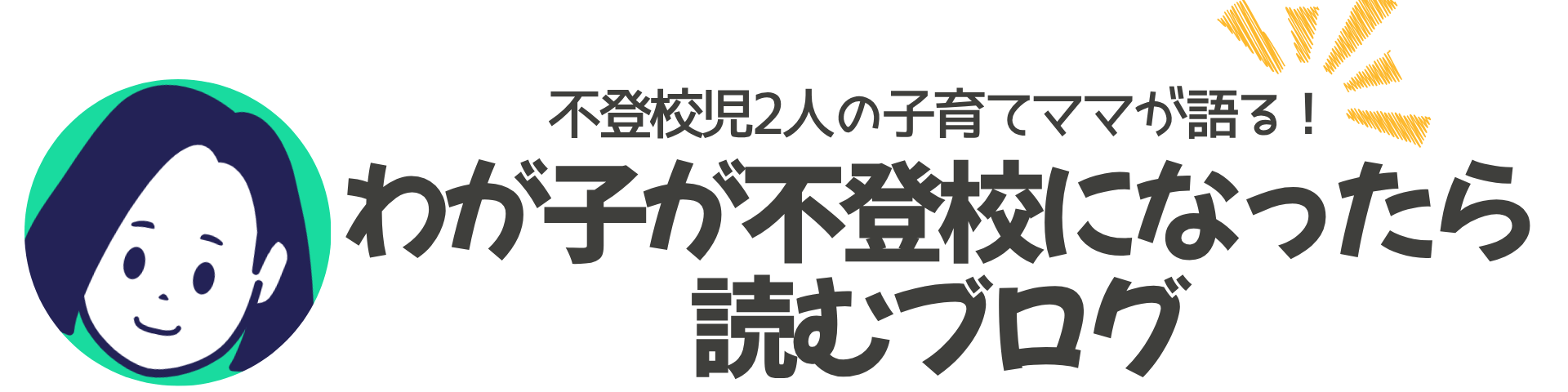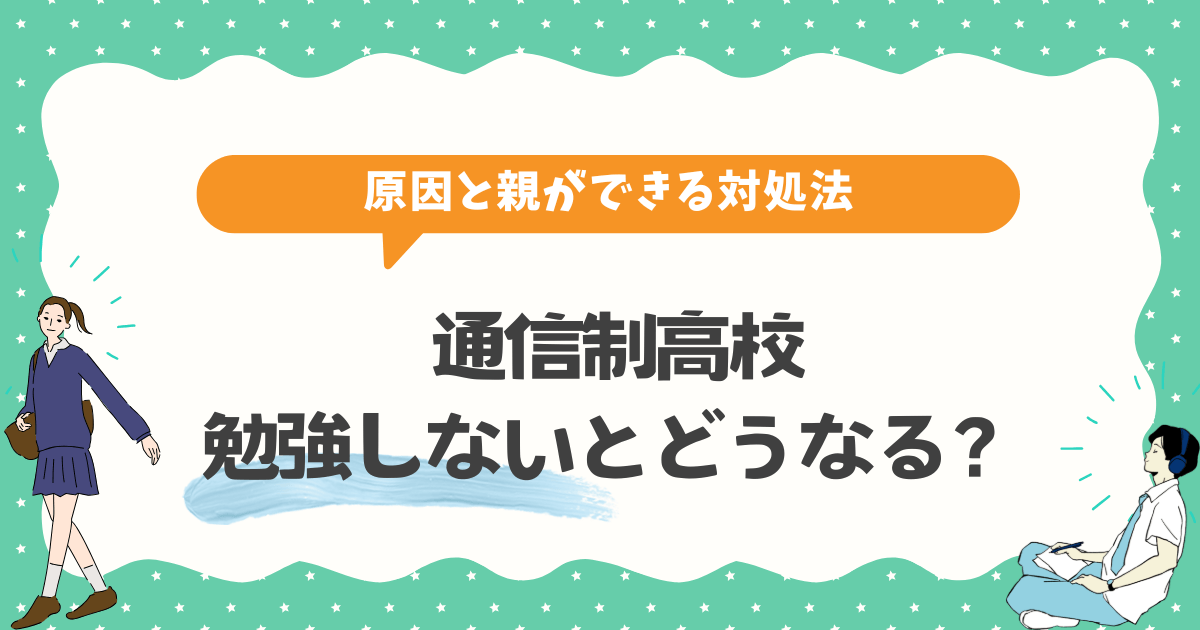「通信制高校に入ったのに、子どもが全然勉強しない…」「このままだと卒業できないかも…」
不登校を乗り越えて通信制高校に進学して、やっとひと安心できたものの、また次の問題に直面して、焦りや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
通信制高校の自由度の高さは魅力ですが、その分、子ども任せにしていると、学習がストップしてしまうこともあります。
でも、この不安を抱えているのは、あなただけではありません。
通信制高校は全日制とは仕組みが大きく違うので、「勉強しない原因」を理解して、正しいサポート方法を知ることができれば、必ず状況は改善に向かっています。
この記事では、「通信制高校でも、勉強しないと卒業は難しい」という現実を踏まえながら、その原因と、親御さんがわが子にできる具体的な対処法、そして失敗しない学校選びのポイントを解説していきます。
子どものペースに寄り添いながら、前向きな一歩を踏み出すためのヒントを、一緒に見つけていきましょう!
知りたい情報がきっと見つかる!
お子さまにぴったりの通信制高校を見つけるには、複数の学校を比較することが大切です。
学費、サポート体制、通学日数やキャンパスの雰囲気など、あなたの不安を解消するリアルな情報をまとめてチェックしましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
通信制高校で勉強しないとどうなるの?

まず、最も気になる「勉強しないと卒業できるのか?」という点について、まずは制度の面から見ていきましょう。
残念ながら、通信制高校も全日制高校と同じ「高校」であるため、勉強せずに卒業することはできません。
卒業要件と必要な学習量
通信制高校の卒業は、全日制と同様に「単位取得」が必須です。
学校教育法に基づき、高等学校の卒業には最低限の学習が義務付けられています。
- 在籍期間が3年以上であること(休学期間を除く)。
- 必履修科目を含め、74単位以上を修得すること。
- 特別活動に30単位時間以上参加すること。
通信制高校の学習は自宅での自学自習が中心ですが、決められた要件を満たさなければ単位は認定されません。
レポートの提出、スクーリングへの参加、試験のクリアが全て連動しているため、どれか一つでも欠けると、その教科の単位は取得できません。
単位取得のためには、必要な学習ステップがあります。子ども任せにせず、親もしっかり把握しておくと安心です。
- レポート提出(添削指導): 教科書に基づいた課題を提出し、合格する必要があります。
- スクーリング(面接指導): 決められた回数(年間数日~数十日)、学校に登校して先生から直接指導を受けます。出席は必須です。
- 単位認定試験: 学期の終わりに実施されるテストで、レポートとスクーリングで学んだ内容が定着しているかを確認し、合格する必要があります。
勉強しない場合のリスク
勉強をまったくしないでレポート提出や試験を怠ると、卒業が遅れ3年で卒業できないリスクが伴います。
通信制高校の学習は、生徒自身の意思と行動が単位取得に直結します。
全日制のように授業に出ていれば自動的に進むわけではないため、自発的な学習が止まると、必要な単位を積み重ねることができず、結果として卒業が遠のいてしまいます。
勉強しないことで起こるリスクとは?
- 単位の不認定: レポートの提出期限を守らない、または不合格が続くと、その科目の単位が取得できず、卒業に必要な単位数が不足します。
- 在籍期間の延長: 卒業に必要な74単位が3年間で揃わなかった場合、在籍期間が自動的に延長されます(実質的な留年です)。4年、5年と時間がかかるケースも珍しくありません。
- 進学・就職への影響: 卒業が遅れると、希望していた大学や専門学校への受験時期がずれたり、同級生と比べて新卒としての就職活動に遅れが出たりする可能性があります。
- さらなる自己肯定感の低下: 「通信制でもダメだった」という挫折感は、子どもの自己肯定感を大きく傷つけ、再チャレンジへの意欲を失ってしまう恐れがあるため、心のケアの面でもリスクがあります。
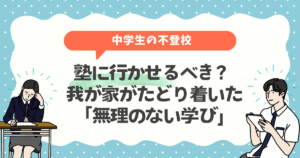
通信制高校で勉強しない原因とは

せっかく進学できたのに、どうして勉強しないんだろう…と疑問に思うかもしれません。
子供が勉強しないことには、必ず理由があるものです。親の焦りはまず一旦置いといて、勉強しない原因を理解することが、子どもへのサポートの第一歩です。
学習習慣が身についていない
不登校だった期間が長くなると、勉強していない期間も長くなり、結果的には学習習慣も身についていません。
これが通信制高校での最大の障害になっていると言えます。
 ゆき
ゆき不登校によって、「決まった時間に机に向かう」という学習リズムや生活リズムが崩れてしまっています。
通信制高校の学習は、この「習慣」に大きく依存するため、何から手をつけていいか分からず、高い心理的ハードルを感じて立ち往生してしまいます。
学習習慣がない状態のサインと対処ポイント
- サイン: 昼夜逆転気味で午前中に集中できない、レポートを開いてもすぐに閉じてしまう。
- 心理的ハードル: 「何から始めればいいかわからない」「集中力が続かない」という不安が大きい。
- 対処法: 達成感を得るために、まずは「1日10分だけ机に座る「レポートの表紙を開く」といった簡単な目標から始めましょう。
自己管理が難しい
通信制高校の自由度の高さが裏目に出て、計画を立てる力や自己管理力が弱いと、課題を後回しにしてしまいます。
通信制高校は、生徒自身が学習時間やペースを決められる反面、自己管理能力が求められます。
この能力は、全日制のシステムの中で守られていた子どもにとっては、急に身につけるのが難しいスキルです。



自分で時間配分ができないため、締切間際になってやっと焦りだすパターンが多いです。
また、スマホやゲームといった誘惑も多いので、優先順位がつけられずに時間だけが過ぎていくことも…。
初めのうちは、親が「伴走車」になって、家族のカレンダーやホワイトボードなどに、締切日や提出日を書き出して、スケジュールを見える化してみましょう。
自己管理するための「型」を一緒に作っていくことで、子ども自身に身についていきます。
モチベーションの低下
不登校だった期間に勉強していなかった場合、高校に進学したからといって急に勉強できるようにはなりません。
なぜ勉強するのか意味が見えない、そして将来の目標がない状態だと、学習が「やらされ感」になり、意欲が湧きません。
勉強は本来、「将来の目標を達成するため」の手段です。
しかし、不登校を経験した子どもは、自己肯定感が低く、将来への展望を描けていないことが多いため、「何のためにこんな難しいレポートをやるのか」という疑問にぶつかり、やる気を失ってしまいます。
周囲に一緒に勉強する仲間がいないことも、孤独感からモチベーションをさらに下げてしまう要因にもなっています。
モチベーションを高めるためのポイントは?
- 課題: 「とりあえず高校卒業」が最大の目標になりがちで、その先の具体的なビジョンが見えていない。
- 孤独感: 仲間と一緒に勉強する環境がないため、孤独感からやる気が上がりにくい。
- 対処法: 勉強の話をする前に、まずは「将来やりたいこと」や「興味があること」について、一緒にインターネットや本で調べてみる対話の時間を持ちましょう。「勉強は、あなたの興味を深めるための道具なんだよ」というメッセージを伝えてあげることが大切です。
学習内容が理解できない
不登校による基礎学力の不足が原因で、通信制高校のレポートや課題が難解に感じられ、つまずいてしまう子が多くいます。
通信制高校のレポートは、中学までの基礎学力が身についている前提で作成されていることが多いのですが、不登校でブランクがある場合、基本的な内容すら理解できず、つまずいたまま先に進めなくなってしまいます。
質問できる環境が自宅にないことも、つまずきを放置してしまう大きな要因です。



息子もレポートが分からなくて、初めの頃はイライラしていました。
でも、第一学院高等学校の教材では中学校からの振り返りもできたので、コツコツ進めてやり切ることができました。
基礎学力に不安がある場合、中学校の振り返りから勉強できるカリキュラムが用意されている学校を選ぶと安心です。
もし大学への進学を考えているなら、学習塾や家庭教師など外部の力を借りることも検討してみるといいですね。
オンラインで受けられる塾や家庭教師もたくさんあります。
メンタル面の不調
通信制高校に進学はできたものの、メンタル面が完全に整っていないと、心のエネルギー不足で勉強への意欲がわかないこともあります。
精神的なエネルギーが低下している状態では、脳が学習モードになりません。
「やらなきゃ」という親や自分のプレッシャーを感じるほど、逆に「体が動かない」「頭が働かない」という状況に陥ってしまい、悪循環になってしまいます。
この時期は、成績よりも心の回復を最優先にすべき時期です。
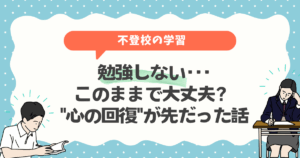
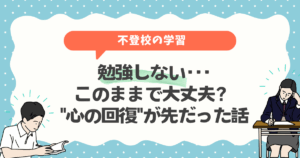
サポート不足
学校や家庭のフォローが不十分だと、子どもは「誰も見ていない」と感じ、孤立感が強まりやすいです。
通信制高校は、先生との接点が全日制よりも少ないため、生徒が自らアクションを起こさないと、学校側もなかなか異変に気づけません。
そのため、学校側から積極的に声をかけてもらえない場合や、親が忙しくて学習状況を把握できないと、子どもは「どうせ誰も見ていないからやらなくてもいいや」という心理に陥りやすいです。
効果的なサポート体制を作るには?
- 学校との連携: 通信制高校は個別の相談を受けてくれることが多いです。先生に相談して、定期的なやり取りをお願いしておくと安心です。
- 家庭内のルール: 勉強を強制するのではなく、「勉強はしなくてもいいけど、レポートの進捗だけは毎週一緒に確認しよう」など、親子でできる「見守りルール」を設けます。
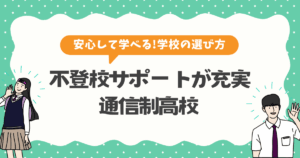
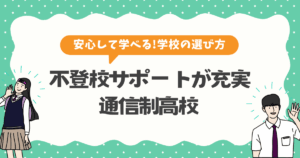
子どもが勉強しないときの対処法


子どもが勉強を再開して、通信制高校を無事に卒業するために、親御さんが今すぐできる具体的な対処法をご紹介します。
大切なのは、焦らず、小さな一歩を褒めることです!
小さな成功体験を積ませる
学習への自信を取り戻すために、ハードルを極限まで下げた「小さな成功体験」を積み重ねましょう。
長期的な不登校を経験した子どもは、「自分には勉強ができない」と思い込んでいます。
そのネガティブな思い込みを打ち破るには、「できた!」という達成感を少しずつ感じてもらうことが最も効果的です。
目標は、「誰でもできるレベル」に設定することが重要です。
小さな成功体験を積ませる具体的な手順
- 1日10分から始める: いきなり1時間ではなく、「今日は10分だけ机に座る」という簡単な目標からスタートします。
- 簡単な課題をクリア: レポートの本題に入る前に、中学の簡単な復習問題や短い読書など、確実にクリアできる課題を選びます。
- 結果ではなく行動を褒める: 成果ではなく、「10分間座れたことがすごい」「レポートの表紙を開いたのが偉い」など、行動そのものを具体的に褒めましょう。
- 記録を見える化: カレンダーなどに「できた日」にシールを貼るなど、成功を視覚化して自信につなげます。
学習計画を一緒に立てる
自力での管理が難しい場合は、親が「伴走者」として、学習計画の見える化をサポートしましょう。
自己管理が苦手な子どもにとって、レポートの期限管理は非常に困難です。
親が先生のような役割を担うのではなく、一緒にスケジュールを確認する「秘書」のような立場でサポートすることで、プレッシャーを与えずに済みます。
このプロセスを通じて、子どもは計画の立て方を学び、自分から学習ができるようになっていきます。
学習計画を一緒に立てるためのポイント
- 親が伴走する姿勢: 「やれ」と言うのではなく、「一緒にレポートの提出期限を確認してみようか」と提案する形で声をかけます。
- スケジュールを見える化: 大きなカレンダーやホワイトボードに、レポートの期限、試験日、スクーリング日を全て書き出し、目につく場所に貼ります。
- 休憩時間も組み込む: 計画には、勉強時間だけでなく、ゲーム時間、散歩時間、睡眠時間なども含め、メリハリをつけます。
- 週に一度のチェック日を設ける: 毎日声をかけるのではなく、「毎週日曜日の夜に5分だけ確認しよう」といったルールを決め、習慣化させます。
メンタルケアを優先する
勉強への意欲がないのは心のエネルギー不足のサインかもしれません。まずはメンタルケアを最優先しましょう。
精神的に不安定な状態では、どんなに素晴らしい教材を与えても効果はありません。
心と体が回復し、「勉強してみようかな」と思える状態になるまで、親は焦らず見守ることが最大のサポートになります。
親の焦りが子どもに伝わると、さらに追い詰められてしまうため注意が必要です。
メンタルケアを優先するステップ
- カウンセリングや相談窓口の活用: スクールカウンセラーや教育支援センターなど、子どもの気持ちを吐き出せる場所を確保します。
- プレッシャーの排除: 勉強に関する話題は一切避け、子どもの好きな話題や趣味について話す時間を増やし、親子の関係を安定させます。
- 生活リズムの安定: 昼夜逆転を改善するため、一緒に散歩に出かける、決まった時間に食事をとるなど、基本的な生活リズムを整えることに集中します。
勉強しやすい通信制高校の選び方


通信制高校は、どこも同じではありません。
「勉強しない」という悩みを解消するためには、手厚いサポート体制が整っている学校を選ぶことが非常に重要です。
サポート体制が充実している学校
勉強が苦手な子には、生徒に合わせたきめ細やかなサポート体制が整っている学校を選ぶべきです。
自由度が高いからこそ、個別の進捗管理や精神的なフォローがないと、子どもはすぐに孤立してしまいます。
担任制や個別指導に力を入れている学校は、生徒を見守る目が多いため、学習がストップしにくい環境だと言えます。
サポート体制の充実度を見極めるポイント
- 担任制の有無: 生徒一人ひとりに専属の担任がつき、学習だけでなく生活面もサポートしてくれるか確認します。
- 学習相談の頻度と方法: オンラインや電話で、いつでも質問できる体制(質問専用ダイヤルなど)が整っているか確認しましょう。
- 登校スタイルの柔軟性: 週1回、月1回など、無理なく通えるスクーリング形式が選べるかチェックします。
モチベーションを高める仕組み
お子様の学習意欲を引き出すためには、「勉強」だけを強制するのではなく、勉強以外の活動を通じて自信と興味を育める仕組みがある学校を選ぶことが大切です。
趣味や特技を伸ばせる活動を通じて「学校って楽しいかも」と感じてもらうことが、結果的に学習への意欲にもつながり、子どもが心から興味を持てる「居場所」を見つけられるかどうかがカギとなります。
このようなモチベーションを高める仕組みがある学校かを確認するために、例えば、IT、美容、eスポーツなど、将来の目標につながる専門的な科目が豊富に用意されているか。
大学受験対策だけでなく、就職や専門学校など、多様な進路選択に寄り添ってくれる進路指導の手厚さがあるか。
そして、登校日以外にも、学校イベントや部活動があり、仲間と交流できる機会が設けられているか、といった点を総合的にチェックすることをおすすめします
親へのサポートがある学校
結論:親御さんの不安を解消し、親子で卒業を目指せるよう、保護者へのサポートが充実している学校が理想的です。
理由: 子どもの不登校や通信制高校での学習の遅れは、親御さんにとっても大きなストレスです。学校が親の不安を受け止めてくれる体制があれば、親が精神的に安定し、家庭内の雰囲気を落ち着かせることができます。
親へのサポート体制を見極めるポイント
- 保護者会の頻度: 定期的に情報交換や相談ができる保護者会が開催されているか確認します。
- 保護者向けカウンセリング: 親自身が専門家(スクールカウンセラーなど)に個別に相談できる窓口があるかチェックします。
- 情報共有の仕組み: 子どもの学習状況を、アプリやウェブで親が簡単に確認できるシステムがあるか確認します。
勉強しない、という不安を解消するには、サポートが充実している学校を探すことです。まずは気になる学校の資料を請求して、サポート内容を見比べてみましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
まとめ:親の焦りを手放して親子二人三脚で乗り越えよう


通信制高校に入ったのに勉強しないという問題は、決して珍しいことではありません。
それは、お子さんが「サボっている」のではなく、不登校によって失われた「学習習慣」や「自己肯定感」を取り戻すのに時間がかかっているからです。
親にできることは、「勉強しなさい」と責めることではなく、「今は休む時期」「焦らなくて大丈夫」という安心感を伝え、お子さんの「伴走者」として、小さな一歩を共に踏み出すことです。
もし、今通っている学校のサポートに限界を感じているなら、この記事で解説した「勉強しやすい学校の選び方」を参考に、サポートが手厚い通信制高校への転校も視野に入れてみてください。
お子さんの心と体が安定すれば、必ず自ら動き出します。焦らず、二人三脚で乗り越えていきましょう。
知りたい情報がきっと見つかる!
お子さまにぴったりの通信制高校を見つけるには、複数の学校を比較することが大切です。
学費、サポート体制、通学日数やキャンパスの雰囲気など、あなたの不安を解消するリアルな情報をまとめてチェックしましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる