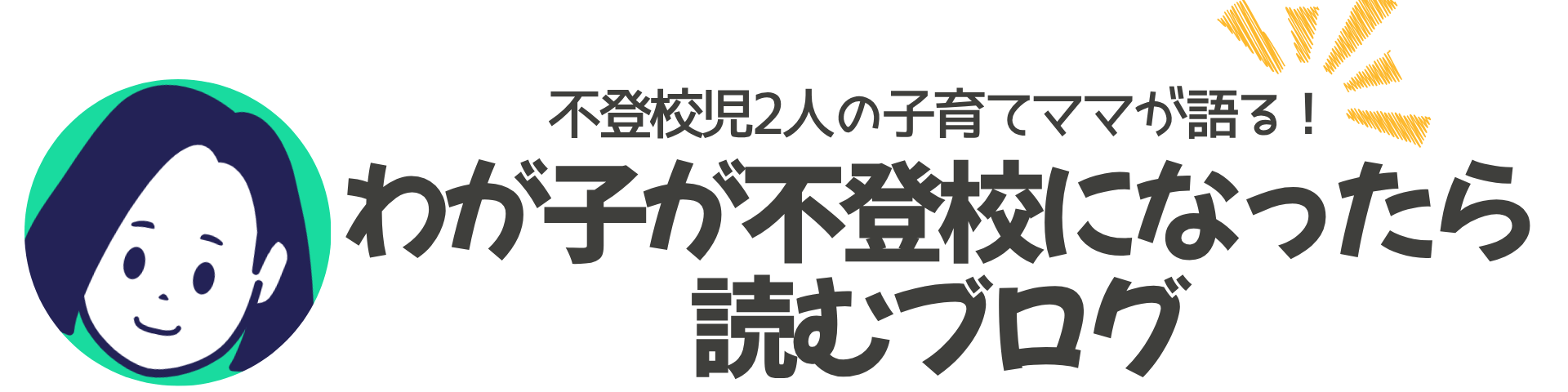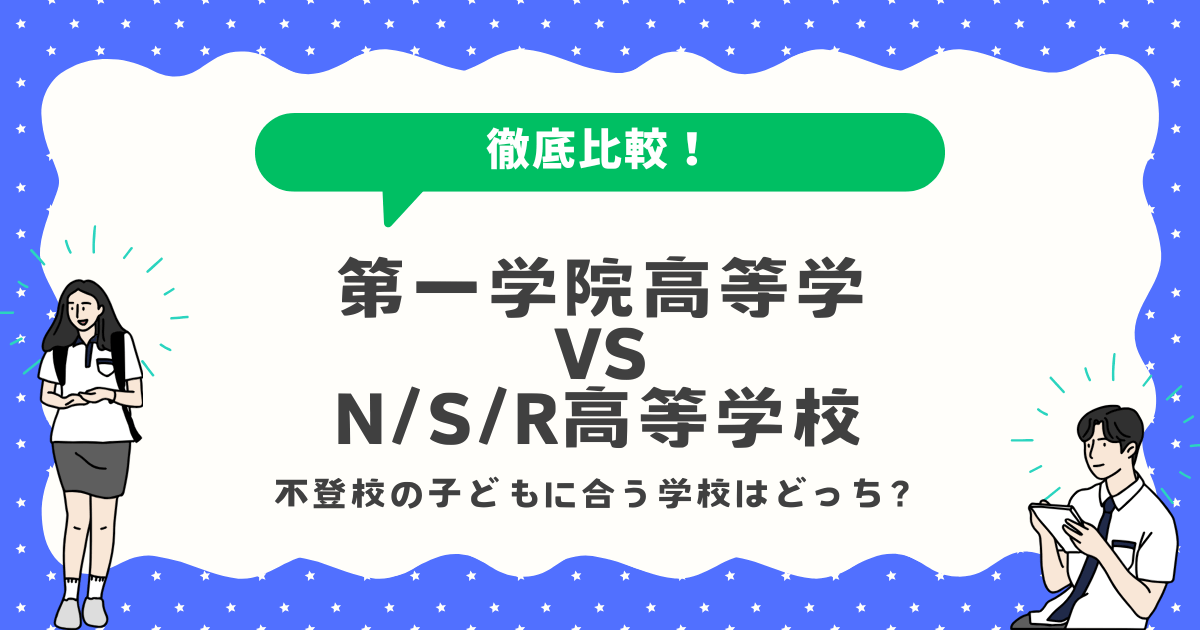「第一学院高等学校とN高等学校。どちらも有名で、名前は聞いたことがあるけれど、うちの子には一体どっちが良いんだろう?」
お子さんの高校選びをされている親御さんなら、必ずこの2つの学校名が候補に挙がるのではないでしょうか。
 ゆき
ゆき我が家の息子も、進学先を選ぶ時に「第一学院高等学校」と「N高等学校」が候補にあがりました。
どちらも通信制高校として非常に人気が高く、不登校のお子さんにとって心強いサポートを用意してくれています。だからこそ、「違いが分かりにくい」「決め手に欠ける」と悩んでしまいますよね。
でも、ご安心ください。学校選びは、お子さんの「個性」と「学びたいスタイル」に合わせることが一番大切です。
どちらも素晴らしい学校ですが、そのサポート体制や学習方法には、実は明確な違いがあります。
この記事では、不登校のお子さんを持つ親御さんの視点に立って、「通学頻度」「手厚いサポート」「デジタル学習」という3つの重要なポイントで、この2校を徹底比較します。
この記事を読めば、お子さんにピッタリの学校を見つけるための明確なヒントが得られるはずです。
一緒に、未来への一歩を踏み出しましょう!
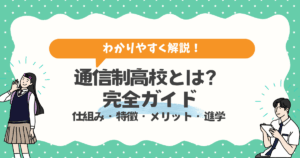
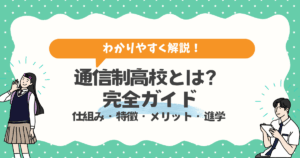
【徹底比較】第一学院とN高等学校の教育方針と基本の違い


【教育理念の比較】「1/1の教育」の寄り添いvs「ITと個性」の未来志向
第一学院高等学校は、一人ひとりの個性と向き合う「1/1の教育」を掲げ、生徒に寄り添う心の成長を最優先します。
一方、N高等学校・S高等学校・R高等学校は、「IT×グローバル社会を生き抜く“創造力”を身につけ、世界で活躍する人材を育成する」未来志向の教育理念を持っています。
第一学院の「1/1の教育」とは、お子さんの不登校の背景や個性、ペースを深く理解し、焦らず自己肯定感を育むことを目的としています。
これは、心の不安を抱えるお子さんにとって、安心できる居場所となることを目指しています。
N高等学校・S高等学校・R高等学校は、ITが進化する社会で生き抜くため、教養・思考力・実践力という「総合力」に、独自の「個性」を加えて価値を生み出せる人材の育成を重視しています。



「心の安心と自信回復」が最優先なら第一学院高等学校が向いています。担任のフェロー(仲間)による手厚い個別指導を通じて、心の傷を癒し、学ぶ意欲を回復させることに特化しています。
一方で、「ITスキルと自己成長」を重視するならN/S/R高等学校が選択肢になります。最先端のIT学習や多様な選択授業を通じて、自分の興味を追求しながら個性を伸ばしたいアクティブなお子さんに向いています。
キャンパスの雰囲気と立地の違い・通いやすさはどうか?
通学時の安心感と通いやすさを重視するなら、全国にキャンパスを持つ第一学院高等学校が有利です。
一方、場所を選ばない自由な学習を優先するなら、N高等学校・S高等学校・R高等学校が適しています。



不登校経験のあるお子さんにとって、「通いやすさ」は単なる地理的な距離だけでなく、心理的な負担に直結する非常に重要な要素になるからです。
N高等学校・S高等学校・R高等学校も全国にキャンパスがあり、今では第一学院高等学校よりも数は多く、通学コースも充実しています。
ただN高等学校・S高等学校・R高等学校はオンライン学習コースも充実しているので、自分のペースで学習したい、通学したくないというお子さんに向いていると言えます。
【サポート内容】お子さんの状態に合わせた選び方|第一学院vsN/S/R高


不登校だったお子さんへの「心のサポート体制」徹底比較
対面での手厚い寄り添いと個別指導を重視するなら第一学院高等学校、時間や場所を選ばないオンラインでのメンタルケアと相談体制を求めるならN高等学校・S高等学校・R高等学校が、それぞれ強みを持っています。
不登校経験のあるお子さんにとって、再登校のプレッシャーがない環境と、信頼できる大人(先生やカウンセラー)の存在が不可欠です。
第一学院高等学校は、キャンパス常駐の教職員による日々の声かけや相談を大切にし、対面でじっくりと安心感を育みます。
N高等学校・S高等学校・R高等学校は、オンラインの特性を活かし、専門のカウンセラーやメンターがチャットや通話で迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えています。



ここは、私たちが学校選びで一番重視したポイントでした!
うちの息子は不登校で自信を失っていたので、「オンラインだけ」では孤独を感じて続かないだろう、という不安がありました。
N高の先進的なIT教育は魅力的でしたが、それよりも「困ったときに、すぐに先生と顔を見て話せる」という第一学院の対面サポートが、息子には必要だと判断しました。
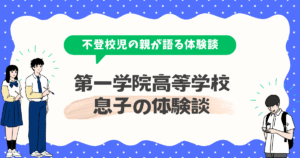
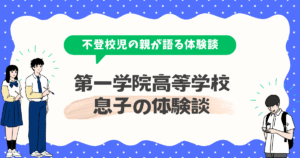
学習の進め方と柔軟性:得意を伸ばすor基礎からやり直す
学習の進め方と柔軟性についても、両校の教育形態の違いが色濃く反映されています。
不登校が原因で学習に大きな遅れがあるのか、それとも得意な分野を突き詰めたいのかによっても選ぶことができます。
| 比較項目 | 第一学院高等学校 | N/S/R高等学校 |
| 基礎学習 | 【マイプラ(個別最適化・自立型学習法)】 ・自分でプランを立てて学習が進められる ・中学校の内容から学習を始められる | 【学習システム「ZEN Study」】 ・映像学習とレポート(添削指導) ・ICTツールを利用し、ネットを介した学習やコミュニケーションを行う |
| 得意分野 | 【プレミアムコース(週5日登校)】 ・大学進学専攻、グローバル専攻などの進学や語学が学べるコース ・AIスキル、アート、デジタルなど専門知識が学べるコース | 【+ONE 授業】(2026年4月スタート) ・多彩なジャンル、100種類以上の学習をチケット制で学習できる ・IT・プログラミング、多様な課外活動 |
| 学習の自由度 | ・通学頻度や個別指導の回数で調整 ・自分だけの時間割(マイプラン)を先生と一緒に考える | ・時間や場所を問わず、自分のペースで進められる |



学習の不安が強い場合は第一学院のきめ細やかな対面サポートが、自分でどんどん学びたい意欲があり、IT分野に強い興味がある場合はN/S/R高が、それぞれ強みを発揮します。
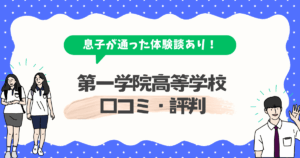
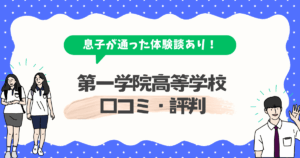
【費用・進路】不安を解消する学費と卒業後の進路|第一学院vsN/S/R高


【費用の比較と注意点】学費は?必要な費用と支援制度の確認
どちらの学校も、「コースや登校頻度」によって年間費用が大きく変動します。
特に通学コースや専門コースを選ぶ場合、全日制高校より高額になる可能性があるため、内訳を詳細に確認することが費用に関する不安を解消する鍵です。
重要ポイント(学費と確認すべき項目)
- 費用でチェックすべき内訳
- 授業料: 単位数に応じてかかる費用(就学支援金の対象)。
- サポート費: 個別指導やカウンセリング、登校サポートにかかる費用。
- 施設設備費: 校舎やオンラインシステムを利用するための費用。
- 諸経費: 教材費、スクーリング費用、各種検定費。
- 支援制度の確認
- 就学支援金: 国からの補助金。適用後の年間負担額を必ず把握する。
- 各学校独自の奨学金や学費減免制度の有無。
- 分納(月払いなど)に対応しているか。
学校の費用は、安心して高校生活を送るために最も重要な項目の一つです。
学費に関する不安や、学校の特徴、サポート内容などを知りたい場合は資料請求で詳しく確認しましょう。
無料で、複数の学校をまとめて請求、比較することが、後悔しない選択に繋がります!


卒業後の進路と大学進学実績はどちらが有利?
第一学院高等学校も、N高等学校・S高等学校・R高等学校も、大学や専門学校の進学サポートは充実していて、進学実績もあります。
個別サポートで着実に進路を決めたいなら第一学院、難関大学への進学やデジタル分野の専門進路を目指すならN/S/R高等学校を選ぶと、それぞれの強みが活かせます。
第一学院高等学校は、先生が生徒一人ひとりの個性と向き合う「1/1の教育」を活かし、面接や作文対策など、総合型選抜(旧AO入試)や推薦入試に強い個別指導に注力しています。
一方、N高等学校・S高等学校・R高等学校は、オンラインの特性を活かしたハイレベルな受験対策(大学受験予備校提携の授業など)を早期から提供しており、難関大学への合格実績を伸ばしています。


【まとめ】どちらを選ぶかは「お子さんの個性」がすべて


第一学院高等学校、N高等学校・S高等学校・R高等学校の2校は、どちらが良い・悪いということはありません。
どちらの学校も、不登校のお子さんが高校卒業資格を取得し、その後の進路へ進めるように全力でサポートしてくれます。



どちらを選ぶかは、「子どもに合うか」がすべてです!
お子さんのタイプ別:最終チェックリスト
- 【対面サポート重視派】 第一学院高等学校
-
- 先生や仲間と対面で少しずつ関わる練習をしたい
- 自宅の近くにキャンパスがあり、通学の安心感を優先したい
- 心のケアや人間性の成長を一番大切にしたい
- 【オンライン自由派】 N高等学校・S高等学校・R高等学校
-
- 自宅でマイペースに学習を進めたい、登校は最低限で済ませたい
- ITスキルやプログラミングなど、専門性の高い授業に興味がある
- デジタルでの学習や相談に抵抗がない
「うちの子にはこっちかな?」と心が決まりかけても、費用やサポート体制の詳細は、必ずパンフレットや個別相談で最新情報を確認しておきましょう。