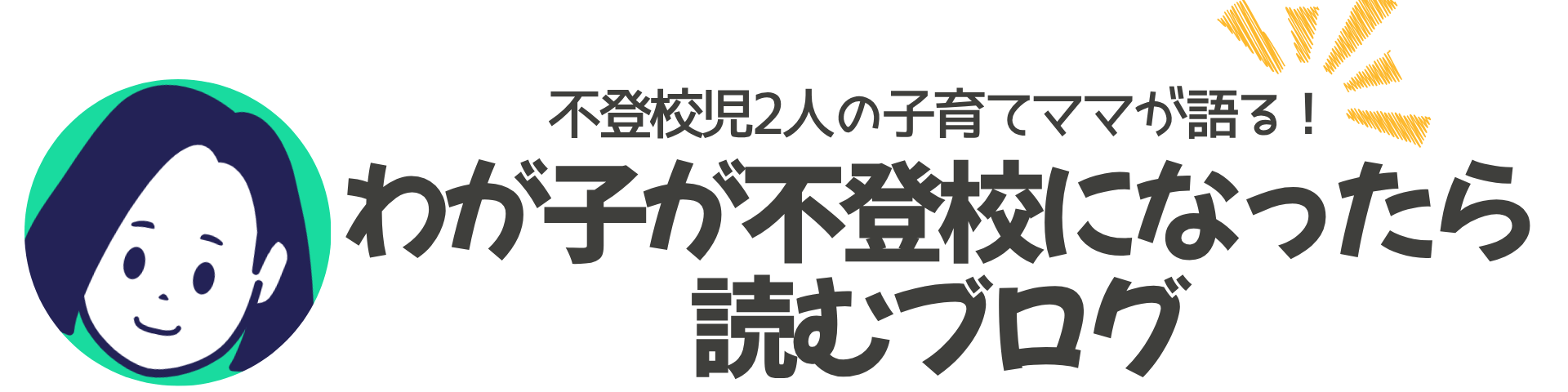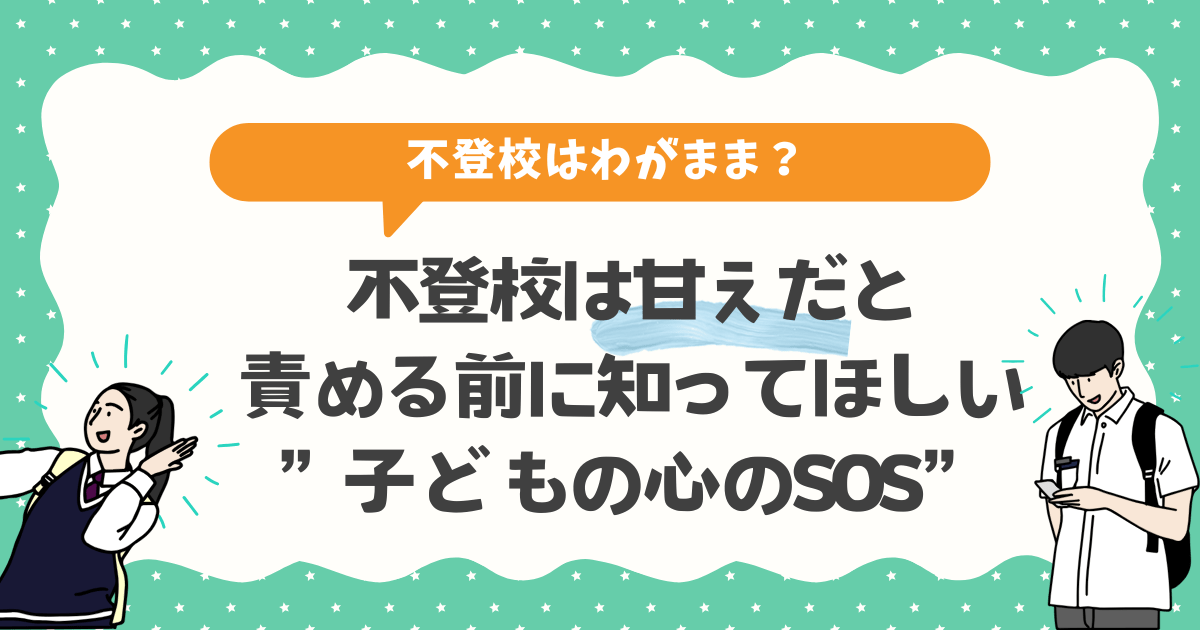「うちの子、ただの甘えなんじゃないか…?」
「学校に行かないのは、私の育て方が悪かったから…?」
今、このブログを読んでいる方は、そんなふうに自分を責めてしまっていませんか?
真面目で、お子さんのことを誰よりも大切に思っているからこそ、「不登校」という現実に加えて、「甘やかしているjんじゃないか?」「わがままじゃないか?」という言葉に、辛い思いをしているのではないでしょうか。
私もそうでした。中学生の息子と娘が相次いで不登校になった時、私もこの言葉に、何度も胸を痛めていました。
 ゆき
ゆき私は今、フルタイムで働きながら2人の不登校を経験した子どもを育てています。今では息子も娘も進学して、好きなことに夢中になっています。今は「甘え」の本当の意味を知ることができました。
このブログでは私の経験をお話ししながら、不登校のお子さんを持つお母さんが抱えがちな「甘え」「わがまま」という言葉への葛藤から、一歩踏み出すためのヒントになれば嬉しいです。
今、私が感じることは、「甘え」は子どもからの「心のSOS」だったのではないか、ということです。
「子どもが学校に行けないのは甘えなのでは…」 そう悩んでしまうのは、どの保護者の方にも起こりうることです。
でも実際は、“行けない”のには必ず理由があります。 そして、お子さんが少しずつ自分のペースで立ち直っていける環境もあります。
通信制高校やフリースクールなど、学校以外にも安心して学べる場所を知るだけでも、 気持ちがぐっと楽になりますよ。
ズバット通信制高校比較なら、全国の通信制高校の資料をまとめて取り寄せて、 登校スタイルやサポート内容を比較できます。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
「不登校は甘え」という言葉に隠された、親の深い悩みと焦り


子どもが学校に行けなくなり、昼過ぎまで寝ていたり、一日中部屋にこもりがちになったりすると、お母さんの心を襲うのは、深い混乱と焦りではないでしょうか。
特に、「みんな学校に行ってるのに、どうしてうちの子だけ…?」という疑問が、「甘えなんじゃないか?」という言葉にすり替わってしまう気持ち、痛いほどよく分かります。
良い母親であろうとして自分を追い詰めた日々
息子が中学2年生になったばかりの頃、学校に行くのを渋るようになりました。娘も、息子に続くように不登校に。
当時の私はフルタイムで働いていましたし、息子が中2になるタイミングで離婚もしたので、子どもたちの面倒を一人で見ていて、とにかく余裕がありませんでした。
そんな中で、子どもたちが不登校になったので、本当に頭が真っ白になりました。
「みんなは頑張ってるんだよ!」「ちゃんと起きなさい」「学校へ行きなさい」
そう声をかけても、息子は「わかってる…」、娘は「頭が痛い」「お腹が痛い」と、学校へ行くことを拒否しているような言葉しかでてきませんでした。



これって「甘え」なの?もっときつく言い聞かせないとダメなの?と思いながらも、本当にそれが正解なのか、「じゃあどうやって対応すればいいの?」と、途方に暮れていました。
当時の私は、良い母親であろうと必死でした。周りのママ友はみんな、子どもを全日制高校に進学させているし、仕事も頑張っている。
なのに、私は子どもたちを学校に行かせることができない。
「私がもっとしっかりしなきゃ…!」と、自分を追い詰めてばかりいました。
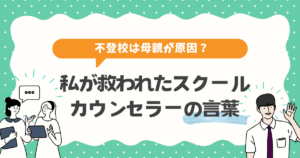
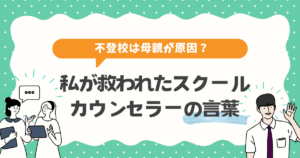
甘えじゃなかった、頑張りたいのに体がついていかない子どもたち
私の焦りは、子どもたちをさらに追い詰めてしまっていたのかもしれません。
息子が不登校になった頃は、反抗期も重なって話をする時間も少なかったのですが、大学生になった今では当時の話をすることがあります。



当時は、学校へ行かなきゃいけないって分かっていても、体が重くなって動けない感じになっていたんだよね。
当時の息子は、学校へ行きたい気持ちはあったのに、体が言うことを聞かないようでした。
そして娘も同じように、学校に行かなくてはいけないと頭では理解できているのに、体に症状が出ていました。



夜、眠れなくて、朝は頭痛や腹痛がひどかった。無理に学校へ行くと、途中で辛くて保健室へ行かないと耐えられなかった。
親の私から見ると、少しぐらいなら学校へ行けるでしょ、我慢できるでしょ、と思ってしまっていたんです。



私たちの学生時代は少しくらいの体調不良でも学校へ行くのが当たり前の時代で、その考え方が抜けていなかったんです。
当時の私はスクールカウンセリングを受けていて、そのカウンセラーのアドバイスもあり、子どもたちに「頑張れ」と言うのをやめました。
あの頃の私は、ただただ「甘え」ということにだけに目を向けて、「どうすれば甘えを治せるのか」ということばかり考えていたんです。
でもその「甘え」は、子どもたちの体に表れた「SOS」だったんだと思います。
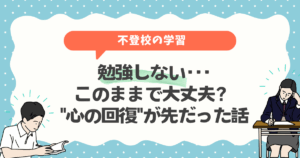
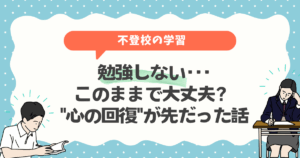
子どもから教わった「本当の甘え」とは?


「じゃあ、子どもが「甘え」という言葉で表現している時に、どうやって向き合えばいいの?」 そう思いますよね。
私が経験から学んだのは、不登校中の子どもにとって、まず優先すべきは「甘えを治すこと」ではなく「心の回復」だ、ということです。
「甘え」の原因、実は病気だった
子どもたちが不登校になり始めたころ、スクールカウンセラーから通院を進められました。
息子のときは、親だけの通院と親子での通院の2回、息子を連れていけたのは1回だけ。
問診では「学習障害の可能性があり、今のところグレーゾーン」だと言われました。
学習障害とは、全般的に知的発達に遅れはないが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習上、様々な困難に直面している状態をいいます。(参照:文部科学省)
グレーゾーンとは…
診断基準を完全に満たすわけではないけれど、発達障害の特性や傾向がみられる状態を指す、いわば「診断名のない生きづらさ」です。(参照:文部科学省)



息子の場合、「書く」ことが極端に苦手でしたが、通信制高校ではタブレット学習だったので、上手く適応できました。
そして娘のときは、「抑うつ」と診断を受けました。
気分が落ち込んだり、やる気が出なかったり、食欲不振や睡眠障害などの身体症状が現れる状態のことです。重度のうつ病とは違い、日常的な活動は可能ですが、心身ともにエネルギーが低下している状態です。



うつ病まで進行する前に気付けたことは、本当に良かったと思います。
2人とも、病院に行ったことで学校に行けない理由が分かり、正直ホッとしました。
「甘え」だと不安に思っていたけれど、甘えではなかった、不登校は甘えやわがままという理由だから起こることではないと分かりました。
そして子どもたちを「甘え」と責めてしまった過去の自分が、偏った知識と一方的な考え方で、未熟さを感じました。
息子と娘が私に「甘えてくれた」から、私は立ち直れた
私が心を落ち着かせることができて以降、子どもたちを「甘え」と責めるのをやめてから、子どもたちも少しずつ心を開いてくれるようになりました。
「お母さん、なんか怒らなくなってから、ちょっと楽になったかも」 息子がポツリとそう言いました。 娘も、「家が一番落ち着く」と言って、少しずつ私と話してくれるようになりました。
そして、ある時、息子と話していたときのことです。



俺、今は学校には行けないけど、高校には進学したい



よし、わかった。じゃあ一緒に探していこう
子どもたちが「甘えてくれる」、親を頼るようになりました。
私は、この時、初めて「甘え」は悪いことじゃない、むしろ、「甘えてくれる」ことが、親子の信頼関係を築くための、とても大切なことなんだと知りました。
当時は周りに相談できる人がいなかった私は、一人で悩みを抱え込み、不安でいっぱいでした。
そんな中で、スクールカウンセラーの先生は私の話を丁寧に聞いてくれて、「大丈夫ですよ」と、一緒にこれからの対応について考えてくれました。
気軽に相談できる内容ではありませんが、1人でも相談できる人がいることって本当に大切だな、と実感しました。
心のエネルギーが少し回復してきたら、次のステップとして、お子さんの「これからの居場所」や「学びの選択肢」について、ゆっくり考えてみませんか?
今すぐ決める必要はまったくありません。「こんな道もあるんだ」と知っておくだけで、親御さんの不安も少し和らぐはずですよ。
関連記事:不登校サポートが充実した通信制高校|安心して学べる学校の選び方
不登校は甘えじゃない!子どもの様子をしっかり観察することが大事


不登校のわが子を前に、「甘えじゃないか」という思いに悩み、苦しんでいる方も多いと思います。
でも、子どもの不登校には「甘え」だけじゃない原因が潜んでいることを忘れないでほしいです。



まずは子どもの様子をよく観察して、その時に必要なところへ相談することが大切だと感じます!
どこに相談すれば分からない場合には、まずは学校が提携しているスクールカウンセラーがおすすめです。
不登校って出口が見えないし、いつまで続くか分からなくて不安や孤独に襲われることもたくさんあります。
そんな時は無理をしないで自分を労わってあげてくださいね。完璧を目指さなくても大丈夫です!
お母さんが笑顔でいることが、何よりもお子さんにとっての安心につながります。
あなたとあなたのお子さんの未来が、希望に満ちたものになることを心から願っています。
不登校で先が見えない不安で、今は他のことが考えられないかもしれません。
でも、焦らないでください。お子さんのエネルギーが回復すれば、驚くほどのスピードで学びを取り戻せるケースも多いです。
大切なのは、「今の」お子さんの状態に合った学びの環境を選んであげること。
全日制高校だけが選択肢ではありません。最近では、不登校サポートが手厚い通信制高校や、個性に合わせたフリースクールなど、多様な学びの場が増えています。
まずは「どんな選択肢があるのか」を知ることから始めてみませんか?
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる