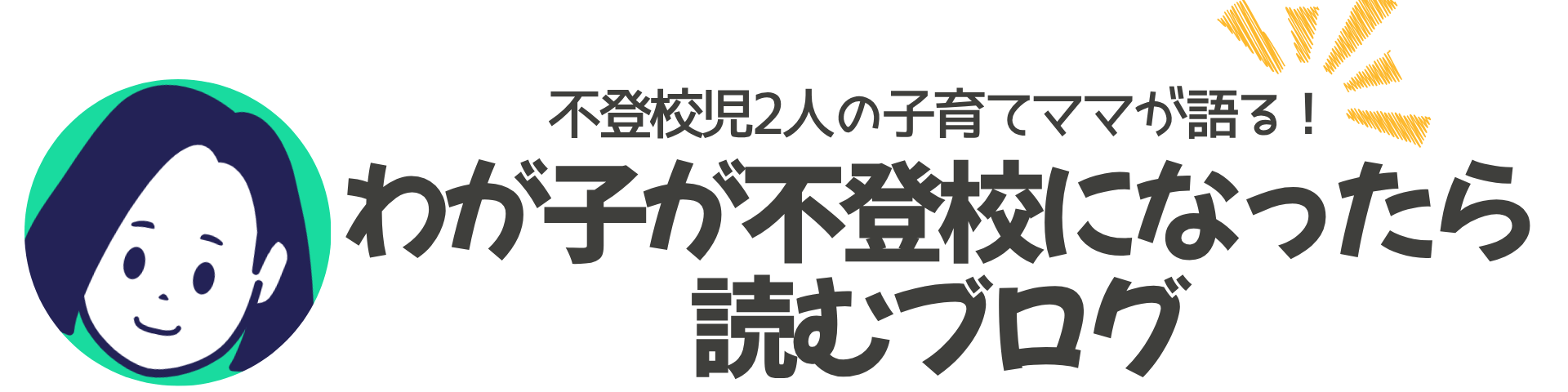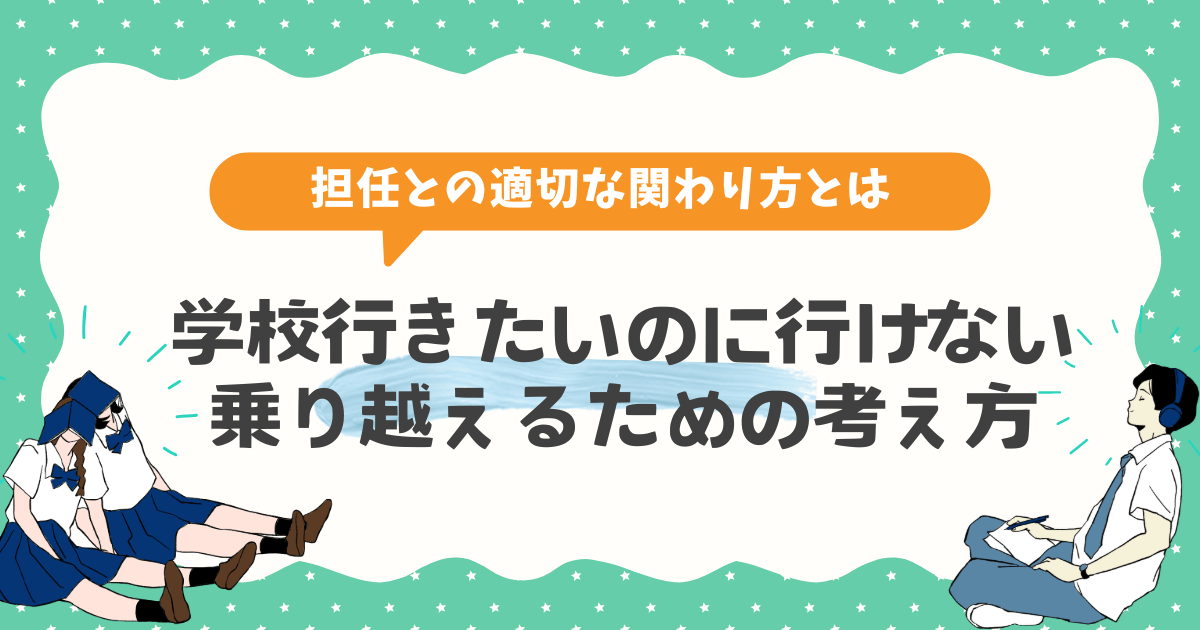「学校に行きたいって言うのに、朝になると行けない…」
「行きたいって言うのに、どうして行けないんだろう…」
今、このブログを読んでいる方は、子どもの気持ちが分からなくて悩んでいないでしょうか。
不登校で学校を休んでいても、学校に行きたいと思っている子ども。
そして、行きたいのに行けない子どもの様子を見て、親として何ができるのか分からない、そばで見守ることしかできなくて、辛い思いをしているのではないでしょうか。
私もそうでした。娘は、学校に行きたいと強く思っていたのに、なかなか学校へ行くことができなかったんです。
 ゆき
ゆき私は今、フルタイムで働きながら2人の不登校を経験した子どもを育てています。娘は抑うつで不登校でしたが、早く治したい、学校に行きたい、と強く思っていました。
学校に行きたいのに行けない状態は、親として悩ましい限りです。
この記事では、私の子どもたちの経験談を交えながら、学校に行きたいのに行けない子どもの理由や乗り越え方についてまとめています。
同じように悩んでいる方に、少しでも参考になれば嬉しいです。
「行きたい気持ちはあるのに、どうしても学校に行けない」 そんな思いに悩んでいるお子さん、そして支える親御さんへ。
焦る必要はありません。 “いまのペースで学べる環境”も、しっかりと用意されています。
通信制高校は、お子さんの心と体を大切にしながら学び直せる進路のひとつです。 ズバット通信制高校比較なら、全国の通信制高校の資料をまとめて取り寄せて、 自分のペースに合った学校を見つけることができます。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
「学校行きたいのに行けない」5つの理由とは?


「どうして行きたいのに、学校へ行けないなんだろう?」と悩んでいるあなたのために、
まずは、お子さんが抱えているかもしれない「行きたいけど行けない」理由を探ってみましょう。
①体調や心の不調
学校に行きたいのに、体調や心の不調で行けない人はとても多く、文部科学省の調査をみても心身の不調を訴える子供が多いことが分かります。


朝になるとお腹が痛くなったり、頭が重くなったり、体がだるくて起きられないこともありますよね。
これは怠けているのではなく、心や体が「今は休ませて」とサインを出している状態なんです。
特に精神的な不調、例えば不安や緊張、抑うつなどは周りからは見えにくいので、「ただサボっている」と誤解されてしまうこともあります。
それがさらにプレッシャーになり、余計に行けなくなるという悪循環に陥ることも少なくありません。



娘も、まさにこの状態でした。夜は「明日は学校に行きたいな」と言っていても、朝になると頭痛、腹痛、そして不眠と、体に症状が出ていました。
体調が原因で行けない時は、まず休養が必要です。
無理に登校するとますます体調が悪化してしまい、長期的に見てもよくありません。
心の不調も同じで、しっかりケアをすることが第一歩です。必要なら病院やカウンセリングを利用するのも、立派な選択肢です。



娘の場合、スクールカウンセラーに相談して、「児童精神科」を受診しました。結果は「抑うつ」だったので、早めに病院へ行って良かったです。
②人間関係のストレス
クラスメイトとの関係がうまくいかないと、学校に行きたい気持ちがあっても足が止まってしまいますよね。
仲間外れやいじめまでいかなくても、ちょっとした一言や雰囲気で「居場所がない」と感じることもあります。
人間関係のストレスは本当に大きな要因です。
朝から「今日もあの子と顔を合わせるのか」と考えると、お腹が痛くなったり、気分が落ち込んでしまうのは自然な反応です。決して弱いからではありません。
人との関係が辛いときは、無理に合わせる必要はありません。距離を取ることも大事です。
もし可能なら、担任やスクールカウンセラーに相談して席を変えてもらうなど、環境を調整する方法もあります。



学校によっては、学年が変わるクラス替えのタイミングで、配慮してもらえることもあるそうです。スクールカウンセラーに教えてもらいました。
③先生や授業への苦手意識
授業についていけなかったり、特定の先生が苦手だったりするのも「学校に行きたいけど行けない」理由の一つです。
「どうせ理解できない」と思うと授業自体が苦痛になりますし、先生に当てられるのが怖くて教室に入りたくなくなることもあります。



息子の場合、「学習障害のグレーゾーンの可能性がある」と、児童精神科の先生に言われました。そのため、他の子どもよりも勉強への苦手意識が強かったのかもしれません。
苦手意識を持つのは自然なことですが、それで学校全体が嫌になってしまうのは辛いですよね。
特に勉強の遅れは自分を責めがちですが、わからない部分は個別に教えてもらったり、タブレット学習など別の方法で補うこともできます。



娘も、タブレット学習や個別学習塾を試してみたことで、少しずつですが「分からない」という苦手意識を克服していきました。
④家庭の事情や環境
家庭の事情で、学校に行けないケースもあります。
例えば親の体調が悪くて家の手伝いが必要だったり、経済的な問題で通学に支障が出ることもあります。
また家庭内の不和が精神的なストレスとなり、学校に行く気力を奪うこともあります。
これは本人の努力では解決できない部分も多いので、「自分が悪いかも…」と思い込む必要はありません。
むしろ、家庭以外の周囲の理解やサポートが不可欠です。
- 学校:担任の先生、スクールカウンセラー、養護教諭
- 教育委員会:自治体の教育委員会
- 教育支援センター(適応指導教室):自治体のホームページや教育委員会で確認
- フリースクールや民間団体:各団体のホームページや問い合わせ
- その他:子ども家庭支援センター、児童相談所など
ひとりで抱え込まず、正しい相談先を見つけて頼ることも、立派な手段です。



うちの場合は、私が離婚して一人で子育てをする中で、息子と娘も心のどこかで不安を感じていたのかもしれません。
⑤自分の性格や気持ちの問題
「内向的だから」「緊張しやすいから」といった性格的な要因で、学校に行けないこともあります。
人前に出るのが怖い、知らない人に話しかけられるのが苦手、そうした気持ちは決して珍しいものではありません。
また「行かなきゃ」と思えば思うほどプレッシャーになって、玄関で足が止まることもあります。
これは根性の問題ではなく、心の仕組みとして自然に起こることなんです。
もし子どもが動けないときには、「行かなくても大丈夫だよ」と声をかけてあげることで、肯定してもらえた子どもの心は楽になっていくこともあります。
「行きたいけど行けない」を乗り越える5つの解決法


①小さな一歩から始める
学校に行くのが難しいときは、いきなりフル登校を目指す必要はありません。
「今日は制服を着るだけ」「校門まで行ってみる」など、ほんの小さな一歩を踏み出すことが大切です。
こうした小さな一歩を積み重ねると、自己肯定感が少しずつ回復していきます。
人間は「できた」という体験が自信に変わる生き物ですから、例え些細なことでも大きな意味があります。
「ねぇ、今日は一時間だけ出てみる?」と声をかけてみたり、「玄関まで行けただけでもすごいよ!」と褒めてあげてください。
②信頼できる人に相談する
学校に行けない悩みは、一人で抱え込むとどんどん苦しくなります。
親や先生、友達、スクールカウンセラーなど「安心して話せる人」に相談してみましょう。
話すだけでも気持ちが軽くなりますし、具体的な解決策が見つかることもあります。



私はスクールカウンセラーに相談しました。「一人で頑張ってきたんですね」と言われて、涙が止まらなくなりました。
③無理しないで休むことを認める
学校に行けない時は、「休むこと」も立派な選択肢です。
無理して登校して体調を崩したり、精神的に限界を超えてしまうと、回復に時間がかかってしまいます。
親からすると、子どもが休むことに焦りや不安を感じてしまい、とにかく学校へ行かせようと思いがちです。
実は私もそうでした。



我が家の場合、無理に学校へ行かせてしまい、結局症状が悪化してしまって、朝も起きれなくなってしまいました。
学校を休ませることは、とても勇気がいることですが、「今日は休んでもいい」と自分に許可を出すことで、親も少し楽になることがあります。
休むことで体調が整ったり、心に余裕が生まれることもあるんですよ。
④環境を少しずつ整える
学校に行きづらい原因の一つは、環境です。
席替え、クラス替え、担任のサポート、通学経路の変更など、ちょっとした工夫で負担が軽くなることもあります。
まずは学校に相談して、子どもが無理しないで学校へ通える方法を見つけてみてください。



娘のときは先生と相談して、保健室へ登校、午後だけ、部活だけ、と、臨機応変に対応していただけました。
⑤専門機関や支援サービスを頼る
どうしても一人や家族だけでは解決できない時は、専門機関に相談するのも選択肢です。
スクールカウンセラー、不登校支援センター、地域の教育相談機関などが力になってくれます。
- 学校:担任の先生、スクールカウンセラー、養護教諭
- 教育委員会:自治体の教育委員会
- 教育支援センター(適応指導教室):自治体のホームページや教育委員会で確認
- フリースクールや民間団体:各団体のホームページや問い合わせ
- その他:子ども家庭支援センター、児童相談所など
プロに話すことで「自分だけじゃない」と思えたり、具体的な支援策を提案してもらえたりします。
特に長期間学校に行けない場合、第三者の力を借りることはとても有効です。
お子さんにとって「安心できる環境で学ぶ」ことは、再スタートの大きな一歩になります。
もし今の学校が合わないと感じるなら、 登校日数や授業スタイルを自由に選べる通信制高校という選択肢もあります。
ズバット通信制高校比較なら、全国の学校を一度に見比べて、 お子さんのペースに合った学校を探すことができます。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校を未来の力に変える!家でできる前向きなアイデア


学校に行けない今だからこそ、できることもたくさんあります。
この時間を、将来への力に変えるためのアイデアを5つご紹介します。
①家でできる学習を進める
学校に行けなくても、勉強は家でできます。
YouTubeや学習アプリ、通信教材など便利なものがたくさんあり、自分のペースで学べるのは大きなメリットです。
子どもが興味を持てる分野から始めてみるのがおすすめです。
たとえば、アニメやゲームが好きなら、英語字幕で観てみたり、プログラミング学習アプリを試してみるのも良いですね。



娘の場合も、できる時間に取り組めるタブレット学習を使い、自分のペースで勉強をしていました。
大切なのは「学校の勉強を完璧にする」ことではなく、「学ぶこと自体を楽しむ」という気持ちです。
②趣味や好きなことに没頭する
絵を描く、音楽を聴く、ゲームをするなど、自分の好きなことに時間を使うのも大切です。
不登校になると、「自分は何もできない」「価値がない」と感じてしまいがちですが、好きなことに没頭している時間は、そうしたネガティブな気持ちから解放されます。
好きなことに集中している間は、達成感や喜びを感じることで、少しずつ自信を取り戻すことができます。
また、その活動を通して新しいスキルを身につけたり、共通の趣味を持つ人とつながったりすることで、子どもの世界は広がり、自己肯定感も高まります。
「好き」という気持ちは、子どもが自分らしさを取り戻し、未来へ向かうための大切なエネルギーになります。
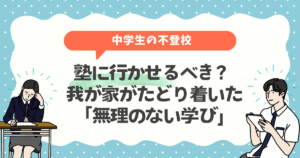
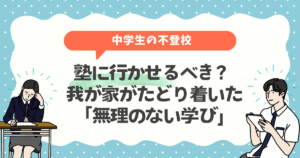
③将来やりたいことを考えてみる
学校に行けない今だからこそ、自分の未来を考える時間にしてみてもいいかもしれません。
お子さんの興味や関心に合わせて、体験ができるイベントを調べてみたり、オンラインでいろんな人に話を聞いてみるのも良い方法です。
将来への漠然とした不安も、具体的な選択肢を知ることで、安心に変わります。
ワクワクするような「未来の地図」を親子で一緒に描くことで、新しい目標が見つかり、前向きな気持ちで過ごせるようになります。
不登校の将来不安を乗り越える!5つの具体的なアイデア


①通信制高校やフリースクールを知る
学校に行けなくても、進学の道はたくさんあります。
通信制高校やフリースクールは、自分のペースで学べる環境が整っており、不登校の子どもたちにとって大きな選択肢となります。
通信制高校では、レポート提出やオンライン授業などを通して高校卒業資格の取得を目指せる一方、フリースクールは、少人数制で個性に合わせた学習や体験活動を重視しており、人間関係や社会性を育む場所としても機能します。
子どもの性格や将来の目標に合わせて、これらの情報を親子で一緒に調べてみることで、「自分に合った学びの場がある」という安心感が生まれます。
通信制高校、フリースクールは、時期を問わず、いつでも見学や説明を聞けるところが多いので、気になるところがあったら早めに問合せしてみるといいですね。
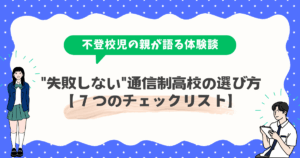
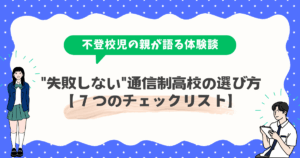


②社会に出るルートは一つじゃないと理解する
大学や高校に行かなくても、社会に出るルートは本当にたくさんあります。
資格を取得する、専門学校で特定の技術を学ぶ、あるいは就職して実社会で経験を積むなど、自分に合う道は必ず見つかります。
社会には多様な生き方や働き方があり、必ずしも「学校のレール」に乗らなくても幸せな人生は送れます。



私の息子も、通信制高校に進んだことで、将来への焦りがなくなり、自分のペースで学び、最終的に大学進学という道を見つけました。
大切なのは、周りと比較せず、お子さんが「これがやりたい」と心から思えることを見つけ出すことです。
③小さな経験を積み重ねて自信にする
不登校になると、どうしても「自分は何もできない」と自信をなくしてしまいがちです。
でも、日常生活の中で「小さな成功体験」を積み重ねていくことで、失った自信を少しずつ取り戻せます。
たとえば、家での手伝い、趣味の時間を楽しむこと、オンラインゲームで友達と協力すること、簡単なアルバイトやボランティアを経験することなども立派な「社会に出る準備」です。
社会に出るための力は、学校だけでなく、さまざまな場所で育まれます。
子どもの「できた!」を一緒に喜び、その頑張りを肯定してあげることで、自己肯定感が高まり、次のステップに進む勇気が湧いてきます。
④未来の選択肢を広げる工夫をする
不安な気持ちを抱えているとき、人はつい視野が狭くなってしまいがちです。
でも、未来の選択肢は、私たちが思っている以上にたくさんあります。
子どもが興味を持っている分野の書籍を読んだり、インターネットでさまざまな職業について調べてみたり、多様な生き方をしている大人に話を聞いてみたりすることで、未来の可能性は大きく広がります。
オンラインで参加できる習い事やコミュニティに顔を出してみるのも良い方法です。
今は不安でも、選択肢を知るだけで安心できます。子どもがワクワクするような「未来の地図」を一緒に描いてみてください。
⑤不登校経験者の言葉に触れてみる
不登校の経験は、親にとっても子どもにとっても、とても孤独な道のりに感じられるかもしれません。
でも同じように不登校を経験し、現在は社会で活躍している人はたくさんいます。
そんな人たちの体験談やインタビュー記事、ブログなどを読んでみることは、大きな希望につながります。
「自分と同じような悩みを抱えていた人がいる」「こんなに前向きに生きている人がいる」と知ることで、子どもはもちろん、親心も軽くなります。
学校の先生やスクールカウンセラーだけでなく、経験者からの生の声に触れてみることで、新たな視点や解決策が見つかることがあります。
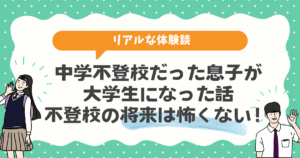
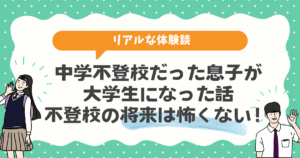
学校に行きたいのに行けない・・・子どもに合わせた対応を探してみて


不登校の不安を乗り越えるために、できるアイデアはたくさんあります。
- 通信制高校やフリースクールを知る
- 社会に出るルートは一つじゃないと理解する
- 小さな経験を積み重ねて自信にする
- 未来の選択肢を広げる工夫をする
- 不登校経験者の言葉に触れてみる
不登校は、親子にとってとても辛い経験かもしれません。
でも、「学校に行きたい」という気持ちがあることは、お子さんが前に進もうとしている証拠です。
学校というレールから少し外れたことで、もしかしたら、もっと自由に、もっと自分らしく生きる道を見つけるかもしれません。
子どもたちはそれぞれの場所で輝き、親である私たちも、新しい自分を見つけることができるはずです。
一緒に、子どもの将来を、そしてあなたの未来を、明るくしていきましょう。
お子さんのエネルギーが回復すれば、驚くほどのスピードで学びを取り戻せるケースも多いです。
大切なのは、「今の」お子さんの状態に合った学びの環境を選んであげること。
全日制高校だけが選択肢ではありません。最近では、不登校サポートが手厚い通信制高校や、個性に合わせたフリースクールなど、多様な学びの場が増えています。
まずは「どんな選択肢があるのか」を知ることから始めてみませんか?
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる