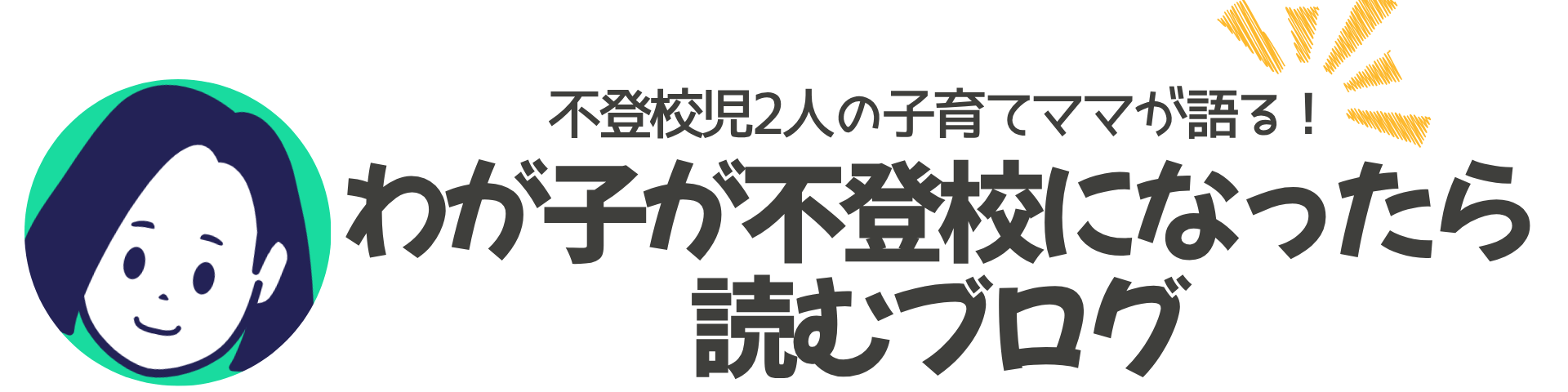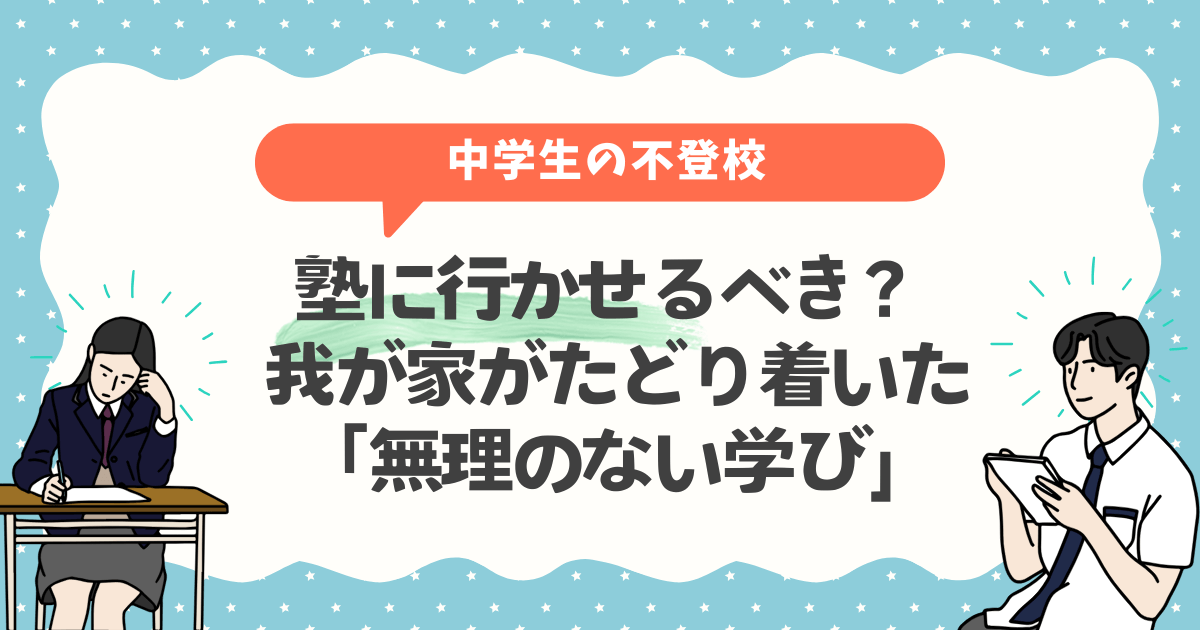「学校に行けないと、勉強が遅れちゃう…」
「勉強できない分、塾に行かせるべきか悩む…」
今、このブログを読んでいる方は、そんなふうに不安でいっぱいの毎日を送っていませんか?
真面目で、お子さんのことを誰よりも大切に思うからこそ、不登校という現実に加えて、学習の遅れ、将来の進路について不安や心配になっていると思います。私もそうでした。
中学生の息子と娘が相次いで不登校になった時、まず頭に浮かんだのは「高校受験は大丈夫か?」「どうにかして勉強をさせなきゃ…!」という焦りでした。
学校に行けていない分、せめて塾くらいは通わせたい、何とか勉強できる時間を作りたい、と思ってしまいますよね。
 ゆき
ゆき私は今、フルタイムで働きながら2人の不登校を経験した子どもを育てています。子どもたちは、塾やタブレット学習を使って勉強に取り組みました。
このブログでは、私たち親子の塾やタブレット学習などの失敗談、そして無理のない学習にたどり着いた経緯などをお話ししながら、不登校で学習の遅れに不安を感じている方へのヒントになれば嬉しいです。
私たち親子のたどり着いた結論は、「勉強の遅れを心配して無理やり学ばせるよりも、まずは心の回復が先だった」、ということでした。
不登校でも進学できる通信制高校は、勉強の遅れがある場合にも受けられるサポートがあり、安心して学べることができます。学校毎にサポート内容はちがうので、まずは気になる学校の資料をまとめて取り寄せて、比較してみましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校だからこそ塾に行かせたい親と、行きたくない子どもの葛藤


焦りが生んだ「塾に行かせなきゃ!」という使命感
息子は中学2年生から不登校になりました。
それまでは個別指導塾へ通っていましたが、不登校になり始めたころから、塾へは行かせていたものの、どこかで時間を潰して残り時間の数十分前に入る、というさぼりを始めました。



塾から「息子さん、まだ来ていません」という連絡があり、「えっ?さっき家を出たのですが」と急いで息子に電話をかけるも出ない。
塾までの道を探して回り、「息子さん、遅れてきました。途中でお腹が痛くなっていてコンビニに寄っていたそうです」と再度、塾から連絡が入りました。
初めのうちは、元々お腹が弱いこともあり、大丈夫かな?と心配していましたが、これが数回続いたんです。
そして本格的な不登校になり、塾へも通うことができなくなりました。
「ねぇ、いい加減にして!このままだと、勉強がどんどん遅れるよ!」 「…分かってるよ」 「分かってるなら、どうして塾へ行かないの?」 「…」
こんなやり取りの繰り返しで、私は次第にイライラが募り、子どもも反発して何も言わなくなる。
「このままだと、高校に行けないんじゃないか…、今の時代に中卒ってありなの…」と、悲観的なことばかり、ぐるぐると考えてしまっていました。



結局、塾は通うことが出来なくなり、先生と相談して、一旦休会の手続きをしました。
娘がチャレンジした「タブレット学習」と「個別学習塾」の結末
一方で娘の場合、学校へは行けないものの勉強の遅れに不安を感じていたので、家でも勉強できる「スマイルゼミ」に入会しました。
タブレット学習は、1回のコマ数が10分くらいでできる仕組みになっているので、ちょっとした時間にも取り掛かりやすくて、結果もすぐにわかって達成感も得られるので取り組みやすいと、娘と相談して決めました。
ちょうどスマイルゼミで、無料利用できるお試し期間があったので、使って見てダメなら解約しようと思い、手続きしました。娘はシンプルで使いやすいと気に入ったので、スマイルゼミを選ぶことにしました。
ただ、タブレット学習は、モチベーションが続きにくいのが難点で、結局自分から行動しないと勉強できない、親が声かけしてやっと勉強する、といった具合。
そして不登校が長引くと、娘自身は学習の遅れに不安を感じながらも、勉強する意欲がわかなくなり、だんだんとタブレットから遠ざかるようになってしまいました。
そして中学3年生になり、出遅れている高校受験の対策をどうするか、という話になり、塾で強制的に学習できる環境を作りたいという娘の希望もあり、通える範囲の塾を調べてみることに。
不登校で勉強が遅れていることに理解を示してくれること、出席日数はギリギリだけど全日制高校を希望していて理解してくれること、体験してみて娘の感触が良かったところを条件に、個別指導の学習塾へ入会しました。
そして結論ですが、娘なりに頑張って夏期講習まで乗り切ったのですが、メンタル面での不調で継続することが難しく、結果としては退会になり、通信制高校への進学へ切り替えました。
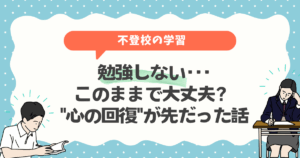
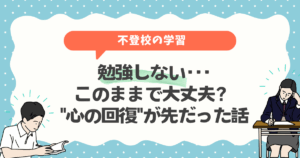
不登校の学習は専門機関がおすすめな理由
不登校の子どもの塾選び、タブレット学習について、我が家の場合はどちらも親が理想としていた形にはなりませんでした。
まず感じたことは、勉強するには子ども本人のやる気が一番大切だということ。(言われなくても知ってる、と思われることですよね汗)
次に、不登校でも受けれいてくれる、特化型の塾や家庭学習のツールを選ぶ必要がある、ということです。



後から同じように不登校で悩んでいるママに話を聞いたところ、不登校児や発達障害などに対応している専門の塾があることを知りました。
我が家の場合は、当時そこまで深く調べる余裕がなく、入塾する際にも不登校であることは伝えていたものの、普通に学校へ通っている子の指導がメインの塾では、対応が難しいと感じる場面が多かったように思います。
不登校の子どもが塾を選ぶ場合は、事前に良く調べて、塾側と子どもの状況について詳しく相談し、連携を取っていくことが本当に大切だと、後になってから後悔したものです。
私たち親子が「もっと早く知りたかった」と痛感したのが、不登校の生徒さんを専門にサポートする体制です。
子どもの繊細な気持ちとペースを理解し、「勉強の遅れ」と「自信の回復」を同時に解決できるのが、不登校専門のオンライン個別指導です。
ティントルなら、自宅で安心して、お子様の状態に合わせた無理のない学習を進められます。まずは専門の無料相談で、お子様の状況を話してみませんか?
\不登校専門のサポートで、自信と学力を取り戻す/
無料相談・詳細はこちら
塾に通う前に考えるべきこと、親が知っておきたい3つの視点


不登校になった子どもたちを前に、「塾に行かせなければ」と焦る気持ち、痛いほどよく分かります。
でも、その前に、少しだけ立ち止まって一緒に考えてみませんか。
そもそも、なぜ塾に行かせたいのか?親の「心の声」と向き合う
「塾に行かせたい」という気持ちの裏には、実は、親自身の「不安」や「焦り」が隠れていることが多いです。
- 「勉強が遅れて、将来の選択肢が狭まるのが怖い」
- 「不登校という現実から目を背けたくて、何か行動を起こさなきゃと思っている」
- 「世間体や周囲の目が気になり、何もしていないと思われたくない」
塾は、子どもの学力アップのためだけではなく、親の「安心材料」でもあると思うんです。
そして、その親の焦りは、結局空回りになって、意味がない事も多いとも感じます。



「お母さん、そんなに焦らなくても大丈夫ですよ」 と、スクールカウンセラーに言われた言葉が響きました。
不登校の期間は、決して「怠けている」わけではなく、子どもたちは、学校という環境で心身ともに疲弊し、「充電期間」に入っている途中なんだなと。
まずは、親である私たち自身が心を落ち着かせて、子どもに「安心感」を与えることが何より大切だと、私はこの時知りました。
「学習の遅れ」は本当にそんなに心配?別の視点から考えてみる
「でも、勉強の遅れが心配で仕方ないんです!」 そう思いますよね。
私もそうでした。でも、不登校という経験を通して、私は少し別の視点を持つことができました。
「勉強の遅れ」は取り戻せる。でも「心の傷」は簡単には治らない。
息子は、中学2年生から卒業まで学校に通えませんでした。明確な理由は分かりませんが、後から「行きたくなかった」と聞きました。一度だけ児童精神科に連れていく事ができましたが、その時に言われたことは学習障害の可能性がある、グレーゾーンだということ。
息子は、病院へ行くのを嫌がり、結局診断はできませんでしたが、もしかしたら、学校の授業についていけず、人一倍頑張っていたのかもしれません。
その疲労が、不登校という形で表れたのかもしれない、と今は思っています。
勉強の遅れは後からいくらでも取り戻すことができますが、一度傷ついた子どもの心は、そう簡単には回復しません。
塾は、子どもが「行きたい」という気持ちになってからでも遅くはない、と感じます。
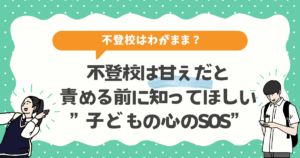
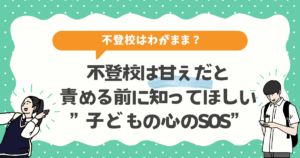
塾以外にも!不登校中の子どもに合った「学び」の見つけ方


「じゃあ、塾に行かせないなら、どうすればいいの?」 そう思いますよね。
我が家がたどり着いたのは、塾や学校という「型」にはまらない、子どもに合った「学び」を見つけることでした。
楽しさを優先!親子のコミュニケーションから見つける「興味の芽」
私は、子どもたちが不登校になってから、「勉強しなさい」と言うのをやめました。
代わりに、「楽しい」と思えることを優先するようにしました。
勉強はもちろん大切なことは分かっていますが今ではない、今は「心の回復」のために興味を広げていくことが大事だと思ったんです。
- 息子の場合
-
高校進学後、社交ダンスを始めました。息子がやりたい!と言い出したことがキッカケです。その後はアルバイトを始めたり、一人でフラッと旅行に行ったり。自分の興味があることを素直に実行するようになりました。
- 娘の場合
-
中学校では美術部で、絵を描くことが好きだった娘。不登校中もイラストを描き続けていました。デッサン用の本を購入したり、画材を買い足したりして、徹底的に絵を描き続けました。
大切なのは、勉強という形にこだわらず、子どもが「楽しい!」と思えることを見つけてあげること。
それが、結果的に「心の回復」につながるのかな?と我が家の経験から感じました。
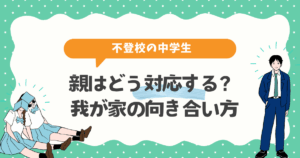
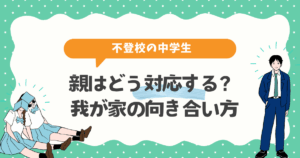
我が家が見つけた「通信制高校」という新しい学びの場
息子と娘は、中学を不登校のまま卒業し、最終的に我が家がたどり着いたのは、通信制高校という選択肢でした。
通信制高校は、毎日学校に通う必要がなく、自分のペースで学習を進められる場所です。
息子は通信制高校で自分のペースで勉強できたことで、少しずつ自信を取り戻していきました。そして、今では大学生です。
娘も、抑うつという診断を受け、全日制高校への進学を諦めましたが、通信制高校に進学してからは、「中学の時より、今の学校の方が私には合ってるみたい。無理しなくていいって、こんなに楽なんだね!」と笑顔で話してくれます。
塾での勉強がうまくいかなくても、子どもには必ず合った学びのスタイルがあります。
大切なのは、親が「こうあるべき」という焦りを手放し、その子にとって何が一番幸せなのかを、一緒に考えてあげることが大切だと思っています。
【中学生の不登校】塾選びは専門機関も視野に入れてみて


不登校のわが子を前に、「塾に行かせるべき?」と悩む毎日。そして、勉強の遅れや将来の不安に、苦しんでいることと思います。
不登校でも勉強を続けたい、学習の遅れを取り戻したい、という意思が子どもにもあれば、塾へ通うことは選択肢のひとつです。
もし、身近に良い塾が見つからない、不登校の子どもで通えるか心配、という場合には、不登校や発達障害などの子どもに特化した、専門の塾も視野に入れてみると安心です。
- 子どもとよく相談すること
- 体験ができるようなら、必ず体験してみること
- 疑問に思ったこと、分からないことは、しっかり聞いておくこと
- 不登校を理解してもらえるか確認しておくこと
- 欠席した場合の振り替え対応について確認しておくこと
「どうしたらいいんだろう…」と悩み、出口が見えなくて孤独を感じている親御さんも多いと思います。私もそうだったのでよくわかります。
塾に行かせるかどうかの選択に、正解はありません。
周りに影響されて不安になるかもしれません、でも大切なのは子どもにあった「居場所」を見つけることだと思います。
不登校という経験は、つらいこともたくさんあるけれど、それを乗り越えた先には、必ず新しい景色が広がっています。一緒に頑張っていきましょう!
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる