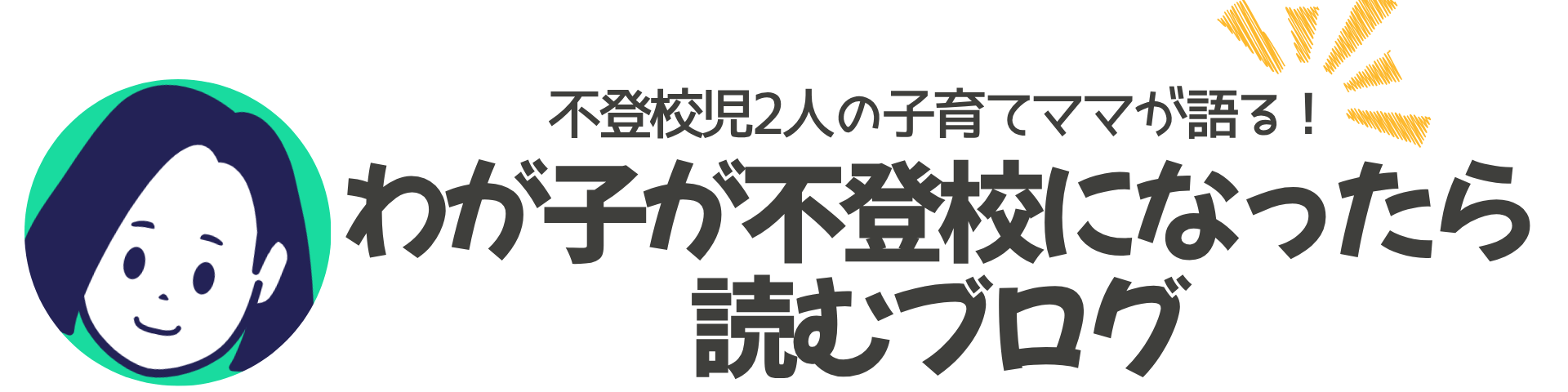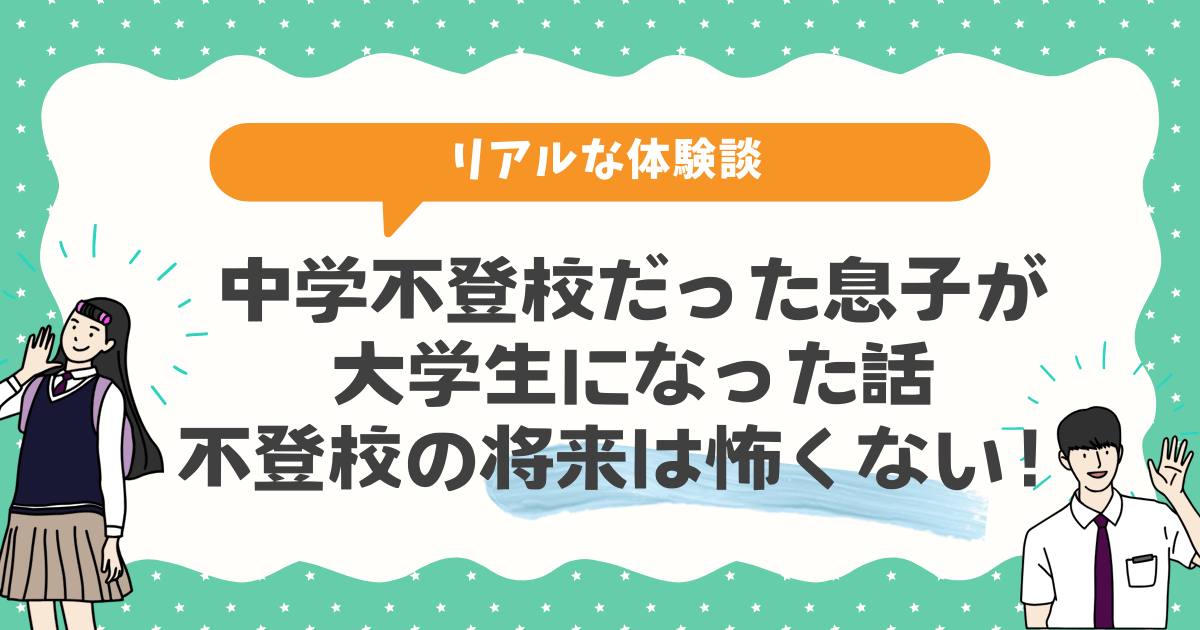「不登校のままで、この子の将来はどうなるんだろう…」
この記事を読んでいるあなたは、今、そんな不安と戦っているのではないでしょうか。
「高校に進学できなかったら、将来は?」「このままだと、将来はニート?怖い…」
私も、息子の初めての不登校を経験したときに、この先の将来を考えて、先の見えない恐怖に怖くなり、毎日不安を抱えていました。
 ゆき
ゆき私は今、フルタイムで働きながら2人の不登校を経験した子どもを育てています。2人とも中学不登校でしたが、今では大学生と通信制高校に進学できました。
この記事では、我が家の子どもたちの現在の姿、そして友達のリアルな現状をご紹介したいと思います。
我が家の体験を通して、不登校の将来について不安に思っている方に、少しでも明るい未来への光になれば嬉しいです。
子どもの不登校で、高校進学に不安を感じているなら、まずは気になる通信制高校の資料をまとめて請求してみるのがおすすめです。学校のサポートや子どもの様子や変化、進路もチェックすることができますよ。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校でも将来怖くない①我が家のリアルな体験談


不登校になると、「将来どうなるんだろう?」という不安が、どうしても付きまといますよね。
まずは、我が家の子どもたちの現状、リアルな体験談をお話ししたいと思います!
不登校だった息子は通信制高校から大学生へ
- 不登校になる前、休日の部活への行き渋りがあった
- 中学2年生から、学校へ通えなくなった
- それまで通っていた塾も通えなくなり、勉強はまったくやっていなかった
- 児童精神科では、「学習障害のグレーゾーン」と仮診断を受けたが、その後息子が通いたがらず
- 息子は極端に字を書くことが苦手だった(グレーゾーンの可能性と想像しています)
- 反抗期と重なり、親子のコミュニケーションは取れないことが多かった
息子が学校に行かなくなって、一番の課題は「高校どうする?」ということでした。
「高校行かないと、本当にまずいよな…」と、息子自身も焦りを感じていたようです。
ただ、3年生になっても学校へ通えていなかったため、全日制高校への進学は難しいと判断し、通信制高校という選択肢を選びました。
通信制高校に進学して1ヶ月はこまめに通学していたのですが、自分のペースで学べるという学校の特性から、学校へ通わずに自宅で過ごすように。



「あれれ?また不登校に逆戻りか…」と、当時は心配でしたが、本人に聞いて問い詰めるようになっては行けないと、学校へ問合せしてみることに。
「課題はできているようです、大丈夫ですよ」と返事をいただき、息子なりに自分のペースで進めているようで、安心しました。
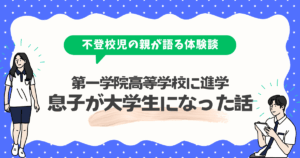
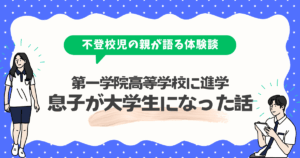
息子の変化点
息子が通信制高校に進学して、しばらくは学校へ行ったり行かなかったり、「これって不登校から回復していない?」と心配でした。
そんな息子でしたが、1学期の終わりころに「ダンス」を習いたいと私に相談してきたんです。



自分から「ダンスをやりたい」と言い出したころから、息子が変わってきたと思います。
本人がやりたいことをやらせよう、家と学校以外の人と関わることで、何か変わるかもしれないと、ダンスを習わせることに。
そして数ヶ月後、「バイトをやりたい、レッスンを増やしたいから、その分はバイト代から自分で払う」と言ってきたたんです。
そこで関わった大人、同世代の子や先輩と関わることで、息子の考え方が変わり、何より自分に責任を持ち始めたように感じました。
私が知っている範囲ですが、ダンスの先生やバイト先の店長に言われていたことがあります。
- 親を頼りすぎない、教室まで距離があるけど自転車で来れない距離ではないから自分で来なさい(ダンスを始めた当初は私が送迎していました)
- 自分の好きなことをやっているんだから、自分で動くこと(レッスンを増やしたいときに、先生がバイトを進めてくれたようです)
- 少し体調悪くてバイトを休みたいと連絡したとき、「熱はない?寝込むほどではない?だったら責任をもってバイトへ来なさい」と言われていた(私に相談してきたとき、さぼりたそうな雰囲気があり、体調はそこまで悪くなかったと思います。店長もそれを分かってくれていたのかもしれません。本当に体調が悪かったら休ませました。)
先生や店長の言葉を聞いて、私はハッとしました。



不登校だからと、どこか慎重になりすぎて、息子を甘やかしている自分がいたのかも、と感じました。
この頃から、息子は自分でどんどん行動するようになり、親を頼ることが減っていきました。
学校へ通う頻度は相変わらず少なくて心配にはなりましたが、2年生の三者面談では先生から「しっかりレポートも提出されているし、友達も多くて楽しそうにしている姿を見ます」と言われ、ホッとしました。
そして2年生の秋頃から、自分で進路を考え始め、「ここのオープンキャンパスに行きたい」「ここが気になっている」と私に相談してくるようになりました。
この頃には反抗期も終わり、息子とも良い関係が築けていたので、将来について話す機会も増え、結果的には大学へ行くという進路を選択できました。
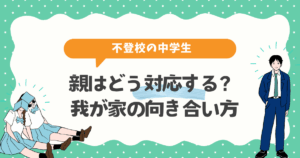
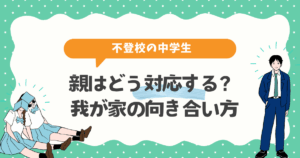
娘は中学不登校から通信制高校へ進学
- 中学校に入った頃から、頭痛や腹痛が多くなった
- 中2になってから、頭痛や腹痛で保健室へ行ったり欠席が増えてきた
- 週の半分が休みになった辺りから、児童精神科に通院、「抑うつ」と診断される
- 疲れていても夜に眠れない、朝方まで寝つくことができない
- 本人は学校へ行きたい気持ちはあったが、体がついていかない様子だった
- 全日制高校の進学を希望していたので、塾やタブレット学習にもチャレンジした
- 通信制高校に進路を切り替えたことで、無理して学校へ通うことを辞め、心の回復に努めた
娘もまた、中学2年生の秋から不登校になりました。
息子とはまた違ったタイプの不登校で、朝起きられない、学校に行くのが怖い、といった軽度の抑うつ症状もありました。
娘は「全日制高校に行きたい」という強い気持ちがあったので、3年生になってからは保健室登校で出席日数をカバーしていました。
ただ授業には出られないので、学習の遅れは娘自身も不安に思っていたため、様々な学習方法を試しました。
- タブレット学習:自分の好きな時間に学習できるので、生活リズムが乱れていても、少しずつ勉強を進めることができました。
- 個別学習塾:マンツーマンで教えてもらえるので、周りの目を気にすることなく、分からないところを質問できました。
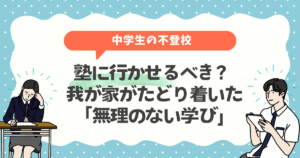
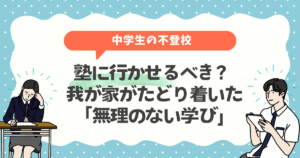
娘の変化点
全日制高校へ通いたい気持ちで、勉強も頑張り、オープンキャンパスにも参加していました。
反面、心が回復していないため、丸1日眠り続けることも少なくありませんでした。
そんな娘の様子を見て、「全日制高校と並行して、通信制高校も調べてみない?」と提案してみたんです。
- 通える範囲にある通信制高校のパンフレットを取り寄せて、娘と一緒に見てみる
- 娘と私が気になった学校をピックアップして、説明会や体験会へ参加
- 専門コースがある通信制高校に娘が興味を持ったので、オープンキャンパスに参加
娘は絵を描くことが好きで、中学では美術部に入っていて、学校へ通えない時も絵を描き続け、いくつか賞も取るほどでした。
絵を描くことを続けたいと考えていた娘は、イラストの専門コースがある通信制高校を知り、無理して全日制高校に通わなくてもいいかもしれないと、考えが変わっていったんです。



全日制高校へ行きたい気持ちはあるけど、毎日通学することへのプレッシャーや通えなくなるかもしれない不安を思うと、通信制高校のほうが自分に合っているかも、って考えが変わっていったよ。
最終的に、通信制高校への進学を決め、安心した娘と私は、高校入学に向けて心の回復を優先し、保健室登校をやめて本格的に学校を休みました。
今は自分のペースで学校へ通い、好きなイラストの勉強をしながら、友達とプリクラを撮りに行ったりできるようになりました。
まだ毎日通うことは難しかったり、精神科で薬を処方してもらっていますが、無理はせず見守っていこうと思っています。


不登校でも将来怖くない②友達の体験談


息子の友達①小学校から不登校で今は通信制大学へ進学
息子の友達に、小学生高学年から不登校だった子がいます。
不登校だったのですが息子と仲が良かったので、ゲームで繋がっていたり、たまに遊びに行ったりしていました。
不登校になった原因は分かりませんが、中学生になっても息子とは繋がっていて、高校進学についてはお互い相談し合っていたそうです。
我が家と同じように通信制高校を調べていたようで、結果的には息子と同じ通信制高校に進学することに。
息子に少しだけ聞けた話だと、友達は周りの人間関係で不登校になったようで、小学校と同じ友達がいる中学校も通うことが難しかったそうです。
その点、通信制高校は周りの人が干渉してくることもないし、自宅でも勉強ができるので、学校へ通うこともできたみたいです。



ただ、勉強の遅れはあったので、「レポートを解いていくのが大変だった!親子で徹夜だった…」と、お母さんに聞きました。
息子と同じく無事に通信制高校を卒業して、通信制大学へ進学しました。
また中型バイクの免許を取得して、バイトして貯めたお金でバイクを購入し、満喫しているそうです。
息子の友達②全日制高校進学も退学、通信制高校へ再入学
起立性調節障害で中学1年から不登校になった友達がいました。
小学校の頃も少し体調に不安があったようですが、中学に入学後は顕著に現れてしまい、中学2年の終わりころまで不登校になりました。
その後は回復して登校できるようになり、全日制高校へ進学しました。
ところが高校1年生のときに環境の変化に体がついていけなかったのか、再度不登校になってしまい、自主退学をしたそうです。
そして、1年遅れて通信制高校へ再入学。体の負担を考慮して登校なしの通信コースを選択、2年目からは週3日通学コースに変更して、自分のペースで学べているとのこと。



息子とも仲が良く、ママさんも近所なので、近況を教えていただきました。
小学生のころから慎重派で、自分から積極的に行動することが少なかったようなのですが、息子が積極的に誘い出しているようで、今ではバイトをしたり、免許を取って車で出かけたりして、学生生活を満喫しているそうです。
不登校で将来不安に思っている親ができる3つのこと


不登校の子どもを持つ親として、不安を抱えながらも、どうすればいいのか分からない…という方もいると思います。
私自身の経験から、これだけはやってよかった!と思うことを3つご紹介します。
1. 相談できる人を見つける(最重要!)
一人で悩まないでください。これが一番大事です。
自治体の教育相談窓口や、フリースクール、民間団体など、相談できる場所はたくさんあります。
私の場合はスクールカウンセラーでしたが、第三者の専門家に話を聞いてもらうだけで、本当に心が軽くなります。
「私だけじゃないんだ」「こういう選択肢もあるんだ」と、視野が広がり、冷静に子どもと向き合えるようになります。
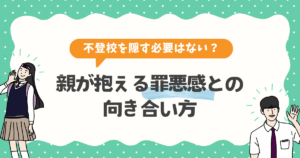
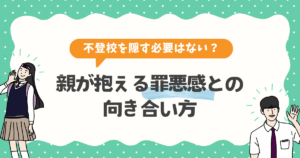
2. 「学校に行くこと」にこだわらない
「学校に行かないとダメだ」という固定観念を、一度手放してみるのもひとつの考え方です。
もちろん、学校は大切な場所です。でも、学校だけが全てではありません。
不登校の子どもたちの「学びの場」は、今や多岐にわたります。
通信制高校やフリースクール、高卒認定試験など、様々な選択肢があります。
息子や娘のように、不登校を経験したことで、かえって自分の将来について真剣に考える時間を持つことができた…というケースもあります。


3. 子どもの「好き」を応援する
不登校の子どもたちは、学校以外の場所で、自分の好きなことや得意なことを見つけることが多いです。
- ゲーム
- アニメ
- イラストなど
どんなことでも構いません。子どもの「好き」を全力で応援してあげてください。
「え、ゲームばっかりしてて大丈夫?」と思うかもしれませんが、ゲームを通してコミュニケーション能力や集中力が養われたり、オンラインで友達ができたりすることもあります。
「ねぇ、このゲーム、新しいステージができたんだって!」 「へえ、面白そうじゃん!やってみたら?」
こんな風に、子どもの「好き」に寄り添って、一緒に楽しむ時間を持つことで、親子の信頼関係も深まります。
通信制高校は、子どもの「好き」を伸ばせる専門的なコースがあります。学校によって学べるコースやサポートが違うので、気になる学校はまとめて資料請求して、比較してみましょう。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校の将来が怖い…大丈夫!子どもを信じて


子どもが不登校になると、出口の見えない不安に襲われると思います。
「このままだ将来どうなっちゃうんだろう」「高校進学できるのかな?」
こんな風に考えてしまい、将来に対して怖くなってしまうことも。
ただそれは、子どもたち自身も同じではないかな?と思います。少なくても私が知っている子どもたちは、不安を感じていました。
学校へ行ければ、それはそれで問題ありません。でもそれだけが正しい道ではない、と少し見方を変えてみると、親も子もラクに生きられるようになるかもしれません。
子どもたちは、学校というレールから少し外れたことで、もしかしたら、もっと自由に、もっと自分らしく生きる道を見つけるかもしれません。
もし、子どもが何かに挑戦したいと言ったら、チャレンジさせてみてください。
不登校だからと甘やかさず、親が心の余裕を持って見守ってあげる、そして困っている時は手を差し伸べられる距離感でいられることが大切だと、私は感じました。
不登校を経験した子どもたちは、とても強い心を持っています。あなたのお子さんも、きっと大丈夫です。
一緒に、子どもの将来を、そしてあなたの未来を、明るくしていきましょう。
お子さんのエネルギーが回復すれば、驚くほどのスピードで学びを取り戻せるケースも多いです。
大切なのは、「今の」お子さんの状態に合った学びの環境を選んであげること。
全日制高校だけが選択肢ではありません。最近では、不登校サポートが手厚い通信制高校や、個性に合わせたフリースクールなど、多様な学びの場が増えています。
まずは「どんな選択肢があるのか」を知ることから始めてみませんか?
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる