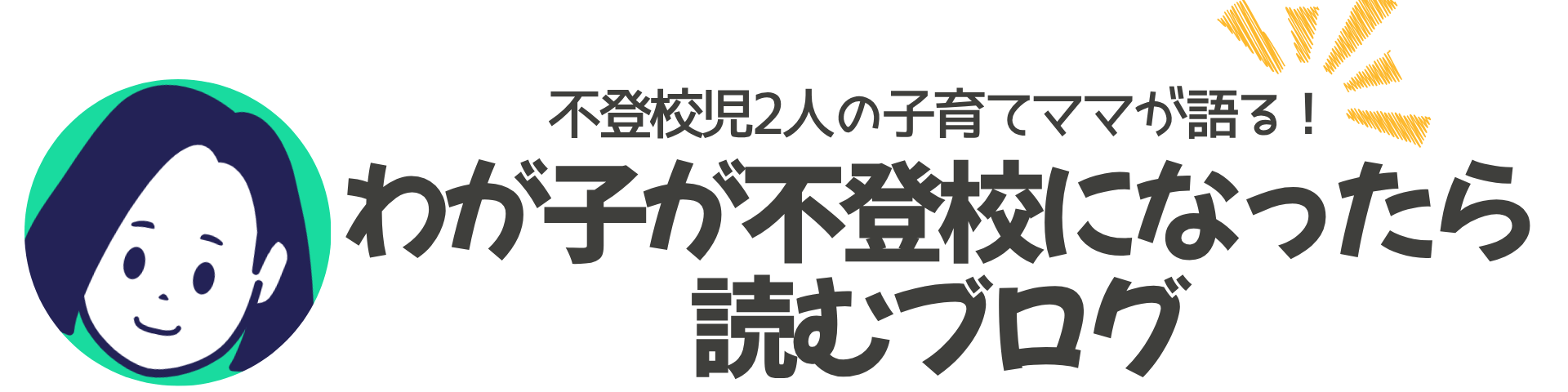「うちの子、学校に行ってないのに家でも全然勉強しないんだけど、このままで本当に大丈夫なのかな…?」
「みんなはどんどん進んでいくのに、この子だけ置いていかれてる気がして、すごく焦る…」
今、このブログを読んでいる方は、そんなふうに不安でいっぱいの毎日を送っていませんか?
真面目で、お子さんのことを誰よりも大切に思うからこそ、不登校という現実に加えて、子どもの学力や将来まで心配になり、心が押しつぶされそうになっているのかもしれません。
 ゆき
ゆき学校からは定期的に授業のプリントを渡されても放置され、積み重なっていく山。そして、どんどん進んでいく授業。このままだと復帰できても、勉強についていけなくなるんじゃないか、という不安と、勉強しない子どもにイライラしていました。
このブログでは、私の経験をお話ししながら、不登校で勉強しない子どもに不安や葛藤から、一歩踏み出せるヒントになれば嬉しいです。
私たち親子の結論は、まずは勉強よりも「心の回復」が先だった、ということです。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校で勉強しないわが子に焦りまくる日々


子どもが学校に行けなくなって、昼夜逆転の生活になったり、一日中部屋にこもりがちになったりすると、親としては不安や焦りを感じます。
特に、学校という「学びの場」から離れることで、「勉強」という新たな問題に直面します。
「勉強しなさい」焦れば焦るほど逆効果だった
息子は不登校になる前、個別指導塾に通っていました。でも不登校になり、塾も通えなくなり、まったく勉強しなくなりました。
それでも学校の授業は進んでいくので、定期的に授業で使ったプリントやテスト用紙が渡されます。
勉強しないでゲームばかりしている姿を横目に、プリントが山積みになっているのをみて、私は不安になります。
「たまには勉強してみない?プリント溜まってるよ」そう声かけても、息子は「んー」というよく分からない返事だけ。
「不登校でも塾だけは行っておこうよ」といっても、まったく行く気配もない。



「ねぇ、プリントやった?」 「…まだ」 「いつになったらやるの?」 「…あとで」こんな会話の繰り返しで、私は次第にイライラが募っていきました。
私が何度も言っていると、次第に息子も「またか…」という表情になり、すぐに自分の部屋へ逃げ込むようになりました。
あの頃の私は、とにかく「学校に復帰させなければ」「勉強させなければ」という焦りで頭がいっぱいだったんです。
「やる気が出ない」「頭に入ってこない」…子どもが勉強しない本当の理由
私の焦りは、子どもたちをさらに追い詰めてしまっていたのかもしれません。
娘の場合、不登校だったけれどギリギリのところで登校日数を稼ぎ、全日制高校への受験を希望していました。
そのため、塾へ通ったり、タブレット学習にチャレンジしたり、家でも学習できる環境を整えてきましたが、なかなか勉強に取り掛かることができません。



親としては、お金もかけてるし、勉強したいといって始めたのに、「なんでできないの?」と一方的に攻めてしまっていたんです。
そして娘と話す機会があったとき、「勉強しても、頭に入ってこない」「学校のこととあ、いろんなことが気になって、集中できない」と言ったんです。
娘の言葉に、私はハッとしました。子どもたちは、勉強したくないわけじゃない。でも、勉強する「心のエネルギー」が枯渇してしまっていたようです。
あの頃の私には、そんな子どもの心の奥底に隠された本当の気持ちが見えていませんでした。
ただただ「勉強しないこと」だけに目を向けて、「どうすれば勉強させられるか」ということばかり考えていました。
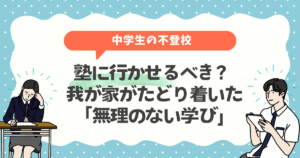
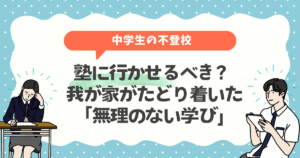
焦りは禁物!不登校中の勉強は「心と体の回復」が先だった


「じゃあ、焦らずに、どうやって子どもと向き合えばいいの?」 そう思いますよね。
私が経験から学んだのは、不登校中の子どもにとって、まず優先すべきは「勉強」ではなく「心と体の回復」だということです。
まずは「勉強しなさい」を言わないこと
私は、娘の言葉を聞いてから、自分の対応を大きく変えることにしました。
それまでは、「勉強は?」「勉強した?」と口うるさく言っていましたが、それをやめました。
まずは学校のことを一旦考えないこと。そして何か楽しいこと、やりたいことにチャレンジさせることにしました。
もちろん、その時は不安でたまらなかったし、昼過ぎまで寝ていたり、ゲームや動画ばっかりで「本当に大丈夫?」と心配になったり、そんなことの繰り返しでした。
でも、まずは家を「安心できる場所」「休める空間」にすることが最優先。子どもの心のエネルギーを回復させることに集中することにしたんです。
私に少し余裕ができると、子どもたちも何となく今までより安定して、少しずつリビングにいる時間ができたり、私とコミュニケーションを取ってくれるようになりました。
「興味の芽」を育てる!我が家の「楽しい」から始めてみた
「心のエネルギー」が少しずつ回復してきたと感じてから、私は「勉強」ではない、別の方法で子どもたちの「知的好奇心」を刺激しようと試みました。
それが、子どもたちが「楽しい」と思えること、つまり「興味の芽」を育てることでした。
- 息子の「社交ダンス」と「アルバイト」
-
息子はマンガでみた社交ダンスに興味を持ちました。「やってみたい」という彼の気持ちを尊重し、地域の教室に通い始めると、そこで新しい人脈ができ、生き生きと活動するようになりました。さらにアルバイトも始め、社会との接点を持つことで、彼は大きく成長していきました。
- 娘の「イラストコース」
-
娘は通信制高校に進学してから、イラストコースを選択し、好きなことに没頭するようになりました。中学時代には見られなかった集中力で、タブレットに向かっている姿を見た時は、本当に驚きました。
- 夜の散歩
-
外に出るのが難しかった二人でしたが、夜なら抵抗がないようでした。夜の散歩は、昼間とは違う静かな雰囲気の中で、子どもとコミュニケーションが取れる、貴重な時間になりました。 たまの散歩は、気晴らしと運動、そしてコミュニケーションの場になりました。
大切なのは、親が「勉強させなきゃ」と焦るのではなく、子どもが「楽しい!」と思えることを見つけてあげて、そっと背中を押してあげること。
それが、結果的に「学び」につながるのだと確信しました。
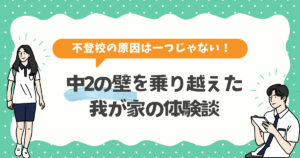
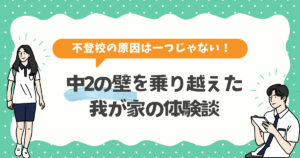
「勉強しなかった」のに進学できた理由


「でも、本当に勉強しなくても大丈夫なの?」 そう思いますよね。
我が家の子どもたちは、中学の不登校期間中、ほとんど勉強をしませんでしたが、最終的にはそれぞれの道を見つけることができました。
息子は通信制高校で自分のペースを見つけた
息子は中学を不登校のまま卒業しました。正直、このままでは高校に進学できないのではないか、という不安が常にありました。
でも、彼の心の中には「高校は行かないとマズい」という焦りの気持ちも確かにあったんです。
そこで検討したのが、通信制高校という選択肢でした。



正直言うと、息子は出席日数は足りない、学力も足りない状況で、私たちが住む地域では全日制高校への進学は難しい状況でした。
でも、そんな状態でも受け入れてもらえる通信制高校は、ありがたい存在でした。
通信制高校なら自分のペースで通うことができるし、全日制高校と比べて時間がある分、やりたいことにチャレンジする時間が作れました。
通信制高校に進学した息子は、自分の好きな時間に集中して勉強できることが合っていたようで、少しずつ自信を取り戻していきました。
そして、高校1年生の夏休みからはアルバイトも始め、今では大学で好きなことを学んでいます。
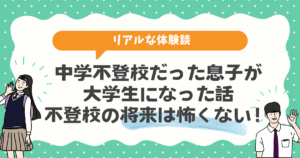
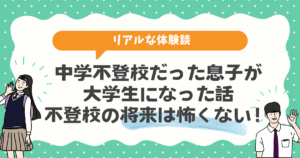
娘は「好き」を深める学び方で自信を取り戻した
娘も、全日制高校への進学を諦め、通信制高校に進学しました。
最初は葛藤もあったようですが、「中学の時より、今の学校の方が私には合ってるみたい。無理しなくていいって、こんなに楽なんだね!」と笑顔で話してくれました。
彼女は今、イラストという「好き」を深め、将来の夢を具体的に語るようになりました。
不登校という経験は、我が家の子どもたちにとって、学校という枠にとらわれず、自分に合った「学びのスタイル」や「居場所」を見つけるための大切な時間になりました。
そして、その過程で、勉強を無理強いするのではなく、「心の回復」を優先し、「楽しい」という気持ちを大切にしたことが、子どもたち自身の可能性を大きく広げてくれたのかな、と今は思っています。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校で勉強しない・・・まずは心の回復から始めてみて


不登校のわが子を前に、「どうすれば勉強してくれるのだろう?」と悩む毎日。
そして、子どもが勉強しないことに、親として悩ましいし、辛くて出口も見えないし、不安を感じることも多いと思います。私もその一人です。
勉強しない子どもに「勉強しろ」と言っても逆効果、子どもは反発して更に勉強から遠ざかってしまいます。
まずは子どもの感情、心をしっかり回復させる環境作りから始めてみてください。
勉強してほしい、という気持ちは一旦抑えて、子どもが自分から行動できるようになるよう、見守ることが大切だったと、今となっては感じています。
不登校という経験は、つらいこともたくさんあるけれど、それを乗り越えた先には、必ず新しい景色が広がっています。
あなたとあなたのお子さんの未来が、希望に満ちたものになることを心から願っています。
お子さんのエネルギーが回復すれば、驚くほどのスピードで学びを取り戻せるケースも多いです。
大切なのは、「今の」お子さんの状態に合った学びの環境を選んであげること。
全日制高校だけが選択肢ではありません。最近では、不登校サポートが手厚い通信制高校など、多様な学びの場が増えています。
まずは「どんな選択肢があるのか」を知ることから始めてみませんか?
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる