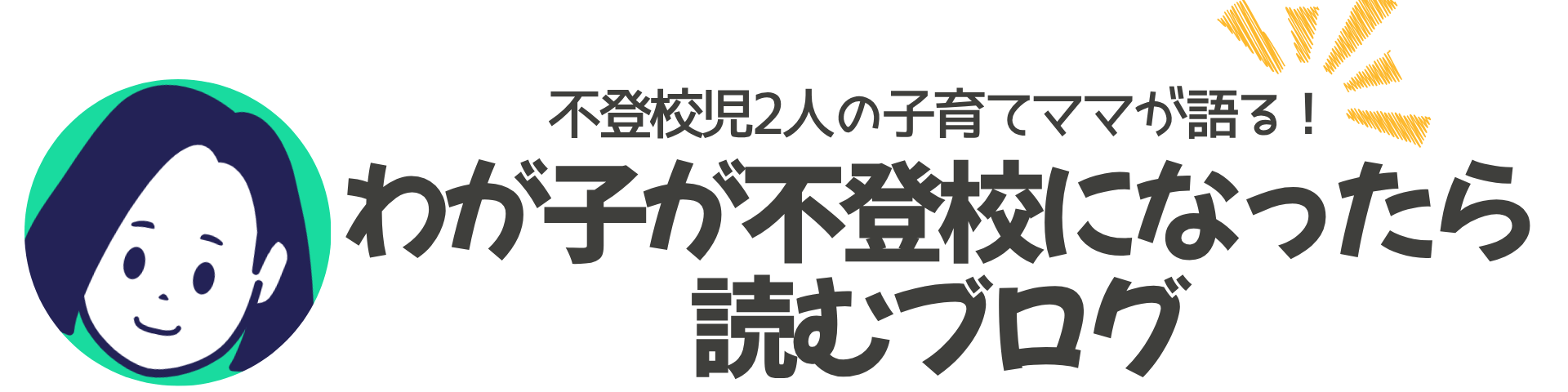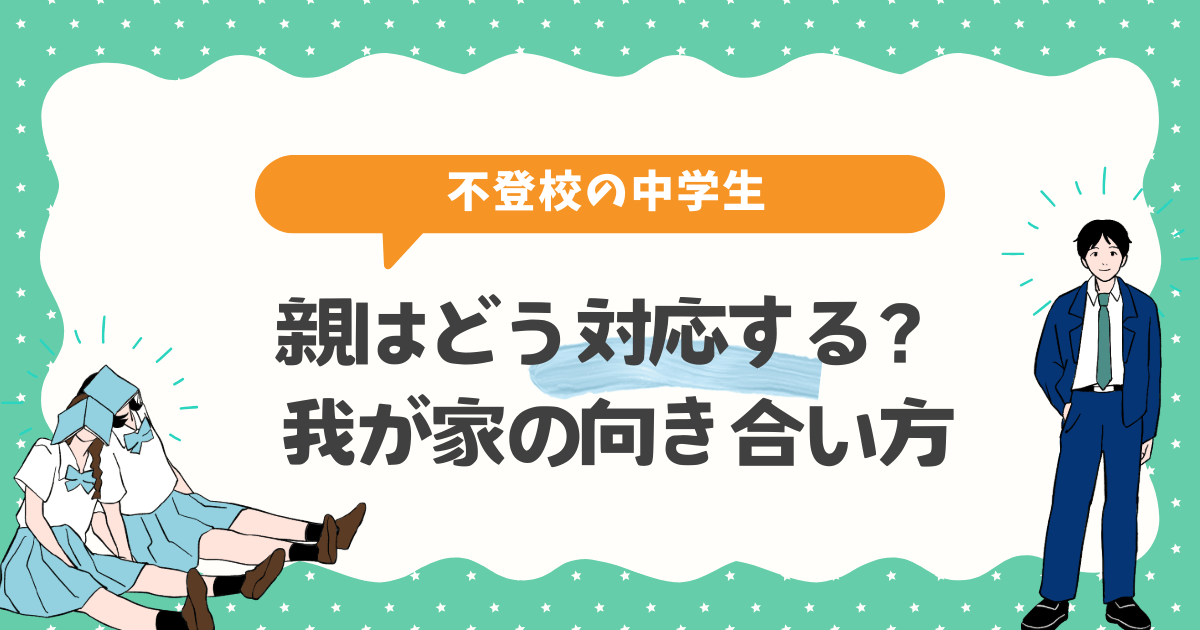「うちの子、学校に行かなくなったんだけど、どうしたらいいの…?」
「このままで大丈夫なのかな…?」
今、このブログを読んでいる方は、そんなふうに不安でいっぱいの毎日を送っているかもしれません。
子どもが不登校になるなんて思っていなかったから、実際に直面したときに親はどうやって対応すればよいか、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。私もそうでした。
 ゆき
ゆき私は今、フルタイムで働きながら2人の不登校を経験した子どもを育てています。2人とも中2から不登校になりましたが、今は不登校から脱出し、大学生、通信制高校に進学しました。
我が家は何とか不登校から抜け出すことができましたが、それが他の子どもにも通用するかと言われると、分かりません。
子どもによっても親の対応方法は変わってくるからです。
このブログでは、我が家の経験談をお話しすることで、「不登校から抜け出すことができるんだ」と少しでも心の重荷を軽くして、前向きな気持ちになってもらえたら嬉しいです。
親がどう対応し、どう子どもと向き合っていくか。そのヒントを一緒に探していきましょう。
不登校から抜け出すキッカケのひとつが「通信制高校」です。
焦らなくて大丈夫です。 お子さんのペースで学び直せる環境も、ちゃんと用意されています。
通信制高校やフリースクールなど、安心して過ごせる居場所を知るだけでも、 気持ちが少し楽になりますよ。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
「親はどう対応すればいい?」不登校のわが子を前に混乱する親の心


子どもが学校に行けなくなった時、まず親の心には、混乱、焦りが巡ってくるのではないでしょうか。
「なんで?何があった?」「この先どうなってしまうの?」そんな思いで混乱してしまいますよね。
私もそうでした。特に中学2年生という多感な時期に不登校になったので、高校受験を前に相当焦ったものです。
焦り、不安、そして自己嫌悪…親がまず「受け止めるべき」感情の波とは
息子が中学2年生になったばかりの頃でした。朝、起きられなくなり、学校に行くのを渋るようになりました。
私はフルタイムで働いていましたし、息子が中2のときに離婚して、私一人で子どもの面倒を見ていたので、とにかく余裕がありませんでした。
「どうして学校に行かないの!?何があったの?このままじゃ高校に行けないよ!」



当時の私は、息子を問い詰めてばかりいました。不安と焦りが先立ってしまい、冷静に息子の話を聞くことすらできていなかったんです。
そのせいで、反抗期の息子はどんどん口を閉ざしてしまい、ますます部屋にこもるように。
そして自分の対応方法に自己嫌悪で落ち込んで、という悪循環の繰り返しだったんです。
「まじめで、子どものことを第一に考えている親ほど、自分を責めてしまう傾向がある」とスクールカウンセラーに言われました。
不安や焦り、自己嫌悪は、それだけ子どものことを真剣に考えている証拠だし、そうやって思うこと自体は悪いことではない、ということです。
まずは、「私は今、すごく不安なんだ」と自分の感情を受け止めてみると、気持が少しだけ楽になりますよ。
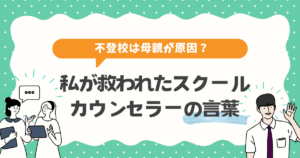
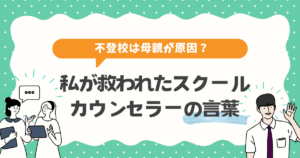
学校との連携?情報収集?「行動」する前に知ってほしいこと
子どもが不登校になると、「とにかく早く何とかしなくては!」と、親は必死で行動しようとしますよね。
私も、手当たり次第に情報を集め、学校の先生に相談し、スクールカウンセラーの予約を取り…と、フル回転でした。
もちろん、情報収集や学校との連携は大切です。
でも、ここで一つ、私の体験談から言えることは、「行動」する前に、まず「立ち止まって」ほしいということ。
当時の私は、「どうして学校に行かないのか、何が原因なのか」と、理由探しに必死でした。
息子に「何で行きたくないの?」と聞いても、「別に…」「行きたくないから」としか言いません。明確な理由が分からないことに、私はさらに焦りを募らせていました。
でも、スクールカウンセラーの先生と話をする中で、大切なことに気づかされました。
「お母さん、焦っても仕方がないですよ。お子さんの気持ちが回復しないことには、先に進むことはできません。」



この言葉は、私にとって大きな衝撃でした。私は、子どもの気持ちを無視して、自分の焦りだけで動こうとしていたのかもしれない、と気づかされたんです。
焦って無理に動こうとすると、子どもはさらに心を閉ざしてしまうことがあります。
まずは、子どもの今の状態をじっくりと観察して、子ども自身のペースを尊重すること。
これが、行動する前に最も大切な心構えだと、私は経験から学びました。
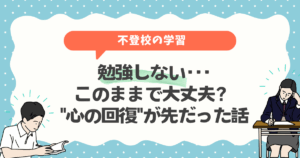
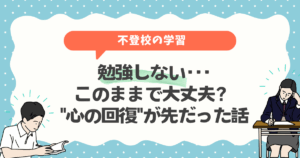
不登校の子どもと「向き合う」ための親の対応で大切なこと


「じゃあ、焦らずに、どうやって子どもと向き合えばいいの?」
そう思いますよね。私が試行錯誤の末に見つけた、不登校の子どもと向き合うための、たった一つの大切なこと。
それは、「子どもを信じる」こと。
言うのは簡単ですが、これが本当に難しい。でも、これができれば、親子の関係が大きく変わるきっかけになります。
無理強いは逆効果!「安心できる場所」が一番の特効薬だった
息子が不登校になってすぐの頃、私は「早く学校に戻さないと」という気持ちが強く、朝、なかなか起きられない息子に「遅刻するよ!」「早く行きなさい!」と毎日言ってしまっていました。
時には、無理やり布団を剥がしたり、感情的に怒鳴ってしまったりすることも。
そのたびに息子は口を閉ざし、さらに部屋にこもってしまい反発してしまうので、悪循環もいいとこです。
そんな時に、スクールカウンセラーに言われた言葉で、私がやっていることは子どもの感情を逆なでているだけ、余計に殻にこもってしまうんだ、ということに気付きました。



子どもも学校に行けないことに苦しんでいる、将来に対して不安を感じている、という子どもの気持ちに寄り添うことができていなかったと反省したんです。大人だって、苦しいときに詰め寄られたら、余計に辛くなってしまいますよね。
まずは心の回復を目指して、「家でゆっくり休ませよう」という気持ちに切り替えることができました。
(とはいっても、時には不安になって、イライラしてしまうことだってありました。完璧な人間なんていないですよね。)
ゲームに動画、時には昼夜逆転していることもありましたが、しばらくは何も言わずに見守ることに徹しました。
その後、中3になり、高校進学をどうするかという話を、息子としっかり向き合って話し合うことが出来ました。少しずつ気持ちが回復していたのかな?と思います。
子どもにとっても、親にとっても、家っていう場所は本来、一番安心できてくつろげる場所ですよね。
それなのに、無理に学校へ行かせようとすることで、「安心安全な居場所」が「プレッシャーを感じる場所」に変わってしまいます。
まずは「家だけは、安心して過ごせる場所」にしてあげることが、親にできる最初の、そして一番大切な対応だったのかなと、思っています。
理由がわからなくても大丈夫。親が「変わる」と子どもも変わる
「うちの子は、なんで学校に行かないのか理由がわからないから、どう対応したらいいのか…」
そう悩む親は本当に多いですよね。私もそうだったから分かります。
でも、私の2人の子どもの不登校経験から、不登校の原因は一つじゃないし、親にも、そして子ども自身にも、はっきりとした理由が分からないことだってあるんだ、ということに気が付きました。
息子の場合、今も明確な理由は分かりません。ただ「行きたくなかった」と彼は言います。
一方、娘は児童精神科で「抑うつ」と診断されました。生活リズムの乱れや学校への不安が複雑に絡み合っていたのです。
理由がはっきり分からないというのは、親にとって本当に不安なことです。でも、理由が分からなくても、親にできることはたくさんあります。 むしろ、「理由探し」に固執しすぎないことが、状況を好転させるカギになることもあります。
私が意識して変えたこと。それは、「子どもを信じる」ことです。
子どもを心から信じて、その上で子どものペースを尊重し、安心できる環境を作ることに注力しました。
完璧な母親であろうとすることをやめ、自分自身も少し肩の力を抜きました。



完璧なご飯を作らなくても、お惣菜だっていいじゃないか!と自分を許したり、疲れたら子どもたちに「ママ、ちょっと休憩するね~」と、ごろんと昼寝したり(笑)。無理しなくなりました。
私の態度が変わると、子どもたちも少しずつ心を開いてくれるようになった気がします。
不登校は、親だけが頑張ってどうにかできるものではありませんよね。
親が「変わる」ことで、子どもも安心して「変わる」ことができるようになる。そんな不思議な循環があるように感じます。
親の「対応」が変われば子どもの未来も変わる


「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」
そう思っているあなたのために、私が実際に試した「対応」と、それが子どもたちの未来にどう繋がったかをお話ししますね。
「無理に行かせない」決断と通信制高校という新しい選択肢
息子が不登校になって数ヶ月経った頃、私は「もう無理に学校に行かせなくてもいい」という決断をしました。
これは、当時の私にとっては本当に勇気のいる決断でした。



もちろん不安はすごくありました。でも無理やり行かせることが本当に正しいのか?と疑問に思うようになったんです。
その代わり、息子は「高校は行かないとマズい」という焦りはあったので、不登校の解消を考えるより、高校進学という未来を目指していこう、という思考に切り替えました。
幸い、いくつか通信制高校を見学することができ、息子と決めた学校に絞ることに。
進学を希望する中学生を対象に、夏休みに何度か通信制高校に通わせてもらう機会があったのですが、そこには自分から通うことができた息子を見て、ホッとしました。



毎日学校に通う必要がなく、自分のペースで学習を進められる通信制高校は、今の息子の「高校へ行く」という目標を達成しつつ、無理なく過ごせる場所だと感じました。
あくまでも我が家の場合ですが、地域によっては不登校でも受け入れてくれる全日制高校もあるので、お子さんにあった学校を探してみてくださいね。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
学校の外で見つけた自分らしさ
通信制高校に進学した息子は、少しずつですが自信を取り戻していきました。
自分のペースで通え、学習を進められることが彼には合っていたようです。
そして、高校1年生の1学期には、なんと「社交ダンスにチャレンジしたい」と言い出したんです!これには私も正直驚きました。まさか息子が社交ダンスとは!



正直、続くのか?月謝は高いし用品も高いし、大丈夫か?と不安はありました。でも「やってみたい」という気持ちは尊重したかったので、教室を探し、週1回のクラスに通い始め、今では大会で賞を取るまでになりました。
さらに、高校1年生の夏休みからは、アルバイトも始めました。
結果、家族や学校以外の人と関わることで、様々な経験を積み、不登校で家に引きこもっていたころとは別人のようになりました。



大学生になった今では、ほとんど家に帰ってこないくらい、活発に動いています。
不登校というと、マイナスなイメージが付きまといますし、息子本人もそう感じているのは正直なところです。
でも、決してマイナスだけではないんじゃないか、と私は感じています。
学校という枠にとらわれず、自分にあった「学びのスタイル」「自分の得意なこと、できること」を見つめるための時間になるんじゃないかなと。
親の対応が変われば、子どもの未来も変わっていけるんじゃないかと思っています。
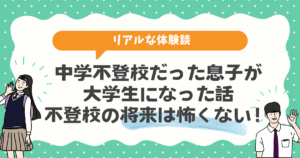
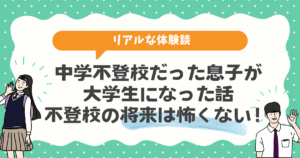
不登校の対応は子どもを信じること、自分を許すこと


不登校の中学生の親として、日々どう対応し、どう向き合うか。この状況は、親にとって本当に辛く、しんどい道のりです。
出口が見えず、孤独を感じ、心身ともに「疲れた」と感じるのは、当然の感情です。
不登校は、子どもの個性、学校環境、家庭環境、社会情勢など、様々な要因が複雑に絡み合って起こるものです。
そして、時には子ども自身も、なぜ学校に行けないのか、明確な理由が分からないことだってあるんです。
今、あなたが感じている「不安」や「戸惑い」は、あなたがどれだけお子さんのことを真剣に考えているかの証です。
その感情を無理に押し殺さず、時には誰かに頼り、時には自分を甘やかすことを許してあげてください。
完璧な母親であろうとする必要はありません。あなたが笑顔でいることが、何よりもお子さんにとっての安心につながります。
今は辛くても、必ず乗り越えられる日が来るはずです。一緒に頑張っていきましょう!
まずは親御さんが笑顔でいることが、お子さんにとって一番の安心材料になります。
心のエネルギーが少し回復してきたら、次のステップとして、お子さんの「これからの居場所」や「学びの選択肢」について、ゆっくり考えてみませんか?
今すぐ決める必要はまったくありません。「こんな道もあるんだ」と知っておくだけで、親御さんの不安も少し和らぐはずですよ。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる