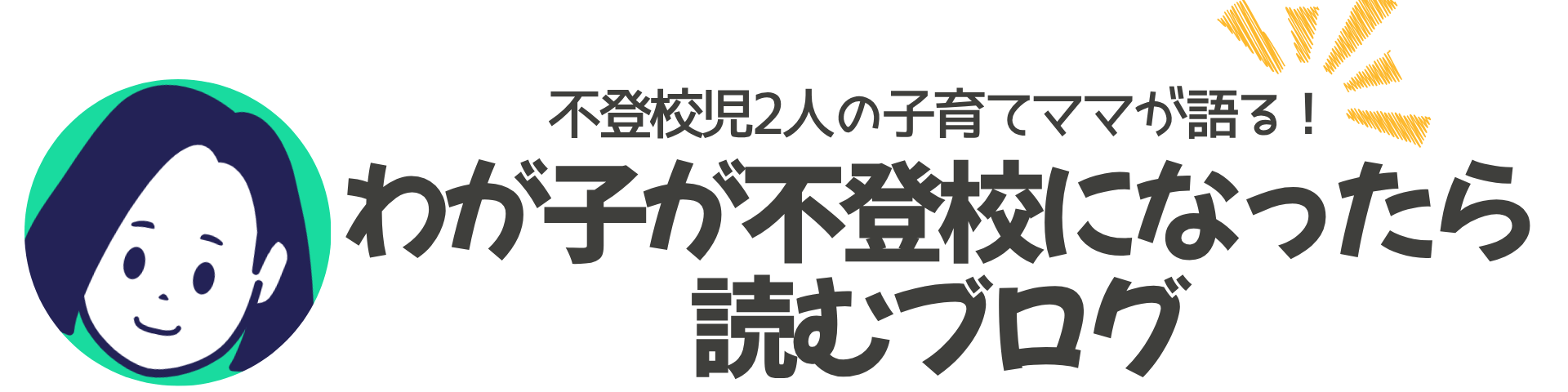子どもの不登校で、学校との関わり方に悩んでいる親御さんって多いのではないでしょうか。
 ゆき
ゆき中学生で不登校になった、2人の子どものママ、ゆきです。
一人目の不登校では、私自身も分からないことが多くて、先生とのやり取りに疲弊していました。
子どもが不登校になったら、学校との連携は不可欠です。
でも、その学校とのやり取りや関係性は思ったようにいかないことも多く、意見の食い違いがあったり、配慮が足りなくて置き去り感を感じたりすることも。
また学校とのやり取りには時間の調整も必要になるので、仕事をしながら学校へ行ったり先生と面談したりするのは結構大変ですよね。
担任の先生や部活の先生にどうやって話せばいいのか、何から伝えればいいのか。私も、手探りの中でたくさんの失敗を経験してきました。
でも、その中で私自身も「こうすればよかったんだな」と、学んだこともたくさんあるんです。
この記事では、子どもが不登校になった時の学校とのやり取りのコツやコミュニケーション方法、そして私の体験談や感じたことをご紹介しながら、お話ししたいと思います。



学校とのやり取りに悩んでいる方、ストレスに感じている方に、少しでも気持ちがラクになる手助けになると嬉しいです。
高校進学に不安を感じているなら、早めに通信制高校のことを知っておくことが重要です。



中学校は全日制高校の進学には対策してくれますが、通信制高校のことはほとんど知識がありません。
通信制高校の進学は学校に頼ることができないため、親が積極的に行動していくことが大切なんです。
まずは一括資料請求サイトから、気になる通信制高校の資料をまとめて取り寄せて、学校の比較から始めてみましょう。
\ 【無料】気になる学校をまとめて資料請求 /
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる
不登校になったらまずは学校へ!「連絡」するタイミングと伝え方


子どもが学校に行かなくなって、まず最初に直面するのが「学校への連絡」ですね。
「いつ、何を、どう伝えるか」は、その後の学校や先生との関係を築く上で、とても大切になってきます。
担任の先生にいつ、どう伝えるべき?
子どもが学校に行けなくなったら、あるいは数日休んだ後には、担任の先生への連絡は避けられないと感じますよね。
私もそうでした。「すぐに先生へ連絡するべき?」 「もう少し様子を見ても大丈夫?」こんな風に悩んだり…。
最近では欠席の連絡はアプリなどからできるし、家庭訪問もなかったので、担任と話したこともなかったんです。



ほとんど面識がない先生に、何から話したらいいのやら…と、かなり戸惑いました。
結論から言うと、できるだけ早い段階で、正直に状況を伝えるのがベストです。
ただ、いきなり「不登校です」なんて、言わなくても大丈夫です。
「体調が優れなくて」「少し疲れが出ているようで」といった伝え方からでも大丈夫です。
大切なのは、子どもが学校に行けない状況にあることを、学校側に把握してもらうことです。
その後、先生から連絡があったらもう少し詳しく「朝、起きられなくて」「学校に行くのが難しいようで…」といったように、子どもの状況を具体的に、かつ冷静に伝えられるといいですね。
感情的にならず、事実を伝えることに徹することで、先生も状況を理解しやすくなります。
この最初の連絡で、先生が子どもの状況を把握してくれるので、学校と連携した今後のサポート体制を考える第一歩に繋がります。
【実体験】私が学校とのやりとりで失敗したこと
息子が不登校気味になったのは、部活を欠席しだしたころから始まりました。
そのため、部活の顧問、そして担任と連絡を取ることに。
定期的に子どもの様子を確認するために担任から連絡があったのですが、部活の顧問からも担任とは別で連絡が来るようになったんです。
息子は相変わらずの不登校、特に変わらない様子を何度も話さなくてはいけないことに、親として何も出来ていないという自己嫌悪やプレッシャーを感じるようになりました。



だんだんと精神的なストレスが溜まり、耐えかねた私は「何か変化があったら、こちらから連絡をします」と、つい感情的になってしまったんです。
結果として、先生もどう対応していいか戸惑った様子で、その後の連携もスムーズではありませんでした。
もちろん、先生も忙しいですし、不登校の子どもを抱える親の気持ちを全て理解するのは難しいと、後になって気づきました。
親がストレスを感じてしまうことは仕方がないことですが、ため込みすぎないこと、友人やスクールカウンセラーなど、自分の気持ちを吐き出す場所を持っておきましょう。
感情的な訴えではなく、具体的な情報と相談内容を伝えることで、より建設的な協力関係を築けるのだと痛感しました。
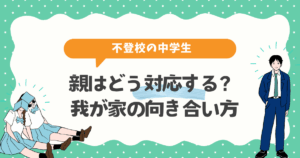
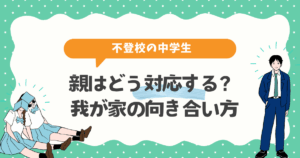
担任と信頼関係を築くためのコミュニケーション術


担任の先生は、子どもが不登校になったときに、学校側で最も身近な存在です。
先生と良好な信頼関係を築くことは、子どもの学校復帰や、新たな学びの場への移行において、大きな助けとなります。
先生への期待値と現実のギャップを埋める方法
不登校になった時、私たち親は先生や学校に期待を抱きがちです。



学校のことは先生が解決してくれるんじゃないか、と漠然として期待を持っていました。
でも、当たり前ですが現実はそう甘くはありません。
先生は多忙であり、一人の生徒にだけ時間を割くことは難しく、そこまで深く生徒のことを理解できていない、という現実を目の前にして、ガッカリしたのは言うまでもありません。
この「期待と現実のギャップ」が、親の不満、不信感に繋がりやすいので要注意です。
先生や学校は、親が期待するほど生徒のことを理解できていません。
中には不登校に関する知識が十分でない先生も中にはいます。
だからこそ、親側から積極的に情報を共有して、学校側ができることも理解した上で、共に解決策を探る「パートナー」という意識を持つことが重要です。
先生に過度な期待はしない、そして「先生は子どもの学校生活の専門家。私は子どもの家庭での専門家」という気持ちを持つことで、協力体制を築きやすくなります。
例えば、先生に何かをお願いしたいとき、「〇〇してほしい」と”一方的に伝える”のではなく、「〇〇について、先生のお力をお借りしたいのですが、いかがでしょうか?」と”相談する形”に変えてみましょう。
また、先生から何か提案があった時には、たとえそれが望まない内容であったとしても、一旦は「検討します」と返答するなど、先生の提案を受け止める姿勢を見せることで、先生との信頼関係が生まれやすくなります。
定期的な連絡で子どもの様子を共有するメリット
子どもが不登校になると、学校との接点が減ってしまうことで、情報共有が滞りがちになります。
ただ、子どもが学校に行かなくなってからも、定期的に担任の先生と連絡を取り合い、子どもの家庭での様子を共有することは、非常に大きなメリットがあります。
子どもは学校では見せない顔を家で見せ、家では見せない顔を学校で見せているものです。
不登校中の子どもの些細な変化、例えば…
- 「今日は部屋から出てきて、少し話すことができました」
- 「昨日はリビングで宿題を広げていました」
- 「体調の良い日が増えてきました」
といった前向きな変化はもちろんのこと、
- 「今日は気分が沈んでいるようです」
- 「ゲームをしている時間が長くなっています」
など、良いことも気になることも、正直に伝えることが大切です。
家庭内での様子も、子どもが学校に来た時にどう接すれば良いかを考える上で、先生にとって参考になる情報になるそうです。
例えば、先生が「〇〇さんが元気にしてると聞いて安心しました。何か困っていることがあれば、いつでも学校に連絡してくださいね」と声をかけてくれることで、子どもが「先生は自分のことを気にかけてくれている」と感じ、少しずつ学校への安心感を抱くきっかけになることもあります。
先生との連絡の頻度は?
先生との連絡は、決して毎日でなくても構いません。
週に1回、あるいは2週に1回など、無理のない範囲で問題ないと思いますが、先生とざっと決めておくと安心です。
学校によってはメール、アプリなどのツールを活用する場合もあるかもしれませんね。
とにかく大切なのは、「継続的に、学校と情報を共有する」こと。
密な連絡は大変ですが、適度な距離間で学校と繋がりを持つことで、学校や先生と信頼関係を築くことができますし、助けになってくれます。



子どもの状況が変わらないのに、先生とやり取りすることは、親も負担にですよね。でも、子どもが学校に通えるようになった時にことを考えて、連絡はしっかり取っておいたほうが、何かと安心です!
【不登校】学校のやりとりにスクールカウンセラーを味方につける


担任の先生との連携と同様に、不登校問題の解決において非常に重要な存在が「スクールカウンセラー」です。
専門的な視点から、子どもと親の両方をサポートしてくれる、心強い味方です。
スクールカウンセラーには何を相談すればいいの?
スクールカウンセラーとは、学校に常駐、あるいは定期的に来校し、生徒や保護者の心の健康に関する相談に応じてくれる専門家です。
初めて利用するときは、「何を話せばいいのかな…」と迷うかもしれません。



私も初めてのときは何から話したらいいか分からず、最初は緊張して部屋に入ったことを覚えています。
スクールカウンセラーには、以下のようなことを相談できます。
- 子どもの心理状態
「子どもがどんな気持ちでいるのか分からない」「昼夜逆転している」「感情の起伏が激しい」など、子どもの行動や言動の背景にある心理を理解したい時。 - 家庭での接し方
「子どもへの声かけがうまくいかない」「どう接すればいいか分からない」など、具体的な関わり方について悩んでいる時。 - 親自身の心のケア
「不登校で自分が精神的に辛い」「罪悪感で押しつぶされそう」など、親自身のメンタルヘルスについて相談したい時。 - 学校との連携の橋渡し
担任の先生に言いにくいこと、あるいは先生との連携がうまくいかないと感じる時に、スクールカウンセラーが間に入ってくれることもあります。 - 外部機関の紹介
子どもの状況に応じて、より専門的な医療機関(心療内科、精神科)や、教育支援センター、フリースクールなど、適切な外部機関を紹介してくれます。
スクールカウンセラーは、学校にいる専門家の中で、最も「子どもの心」に特化した存在です。
だからこそ、子どもの心の状態や、それに対する親の接し方など、デリケートな内容こそ積極的に相談すべきです。
「こんなこと話してもいいのかな?」とためらわず、正直な気持ちを伝えてみましょう。
カウンセリングの進め方と効果的な利用方法
スクールカウンセリングは、通常、事前に予約をしてから行われます。
初回のカウンセリングでは、カウンセラーがあなたの話にじっくり耳を傾け、現在の状況や抱えている悩み、お子さんの様子などを詳しく聞いてくれます。



私も初めてカウンセリングを受けた時、溜まりに溜まった思いをワーッと話を聞いてもらい、心が軽くなるのを感じました。
カウンセリングを効果的に利用するためには、いくつかのポイントがあります。
- 正直に話す
どんな悩みでも、どんな小さなことでも、隠さずに正直に話しましょう。カウンセラーはあなたの味方です。 - 具体的な状況を伝える
「子どもが朝起きられない」「ゲームばかりしている」といった具体的な行動や、それに対してあなたがどう感じているかなどを具体的に伝えることで、カウンセラーもより的確なアドバイスをしやすくなります。 - 質問を準備しておく
「こういう時、どう声かけたらいいですか?」「この先の進路で不安があります」など、事前に質問したいことをメモしておくと、限られた時間の中で効率的に相談できます。 - 継続して利用する
一度話しただけで全てが解決するわけではありません。子どもの心の変化や、親自身の感情の変化に合わせて、定期的にカウンセリングを利用することで、長期的なサポートを受けられます。私も、子どもの状況に応じて、定期的にカウンセリングを利用していました。
カウンセリングは、一方的にアドバイスをもらう場ではなく、カウンセラーと共に解決策を探していく共同作業です。
「話すことで、自分の頭の中が整理される」「専門家からの客観的な視点を得られる」という大きなメリットがあります。
積極的に活用して、あなたの心の負担を減らしていきましょう!
【不登校】学校以外の専門機関とのやりとり


一番に考えるのは学校との連携ですが、子どもの状況によっては学校以外の専門機関も考える必要があります。
多角的なサポート体制を築くことで、子どもに合った最適な支援を見つけることができるので、知っておくと安心です。
①教育支援センターや精神科の利用
学校に行けない子どもたちをサポートする機関は、学校だけではありません。
「教育支援センター(適応指導教室)」は、不登校の子どもたちが学校以外の場所で学習したり、社会性を身につけたりするための公的な施設です。
多くの場合、学校と連携しており、教育支援センターに通うことが、学校への復帰の足がかりとなることもあります。
教育支援センターの担当者と学校の先生が情報を共有することで、より一貫したサポートが可能になります。
また、不登校の背景に、発達障害(ADHD、ASDなど)や、うつ病、不安障害といった精神的な不調が隠れているケースも少なくありません。
その場合、精神科や児童精神科といった専門医の診察を受けることが不可欠です。



我が家の場合も、2人とも児童精神科で診察を受けました。診断が出ると対応方法が明確になるので、手探りの状態よりは安心できました。
専門医が診断を下し、適切な治療や投薬が必要だと判断された場合、その情報(診断名や治療方針など)を、あなたの同意を得た上で、学校や教育支援センターと共有することが重要です。
これにより、学校側は子どもの状態をより深く理解し、特性に合わせた配慮やサポート(例えば、学習方法の変更、休憩時間の配慮など)を検討してくれるようになります。
専門機関との連携は、子どもの不登校の原因を多角的に分析し、より根本的な解決策を見つけるために不可欠です。
決して敷居が高いものではなく、子どもが自分らしく生きるための大切なステップだと捉えて、積極的に利用をおすすめします。
②フリースクールや通信制高校とのスムーズな引き継ぎ方
不登校の子どもの学びの場は、学校だけではありません。
最近は、フリースクールや通信制高校といった、多様な選択肢が注目されています。
もしお子さんが学校への復帰が難しいと感じていたり、より個性に合った学びの場を求めている場合は、これらの機関を利用することも検討してみましょう。
ただし、これらを利用する場合も。学校との連携は不可欠です。
フリースクールに通う場合、学校側は出席扱いにするかどうかの判断をします。
そのためには、フリースクールでの学習内容や活動状況を、学校に定期的に報告する必要があります。
文部科学省の「不登校児童生徒への支援に関する通知」により、フリースクールなどでの学習活動が学校の「出席」として認められる場合があります。
フリースクールによっては、学校との連携サポートを行ってくれる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。


通信制高校への進学を考える場合も、中学校からの「調査書」や「内申書」が必要になります。
不登校で出席日数が足りなくても、通信制高校への進学は可能です。
中学校の先生には、通信制高校への進学を検討している旨を伝え、必要な書類の準備や、中学校の先生から通信制高校の先生への情報共有を依頼しましょう。
通信制高校は、全日制高校と比べて入試が早くから始まります。
年々早まっていて、夏休み明けには本格的に入試に向けた活動が始まるので、通信制高校への進学を決めたら、早めに先生と情報を共有して、書類の準備をお願いしましょう。
学校以外の学びの場へ移行する際も、学校との連携を怠らないことが、子どもが新たな環境で安心して学び始めるための大切な鍵となります。
通信制高校やフリースクールは、 「今の学校では難しいけど、学びは続けたい」というお子さんにとって大切な居場所です。
もし「どんな学校があるのか知りたい」「費用や通学スタイルを比べたい」 という方は、資料をまとめて取り寄せてみましょう。
ズバット通信制高校比較なら、全国の学校を一度に比較でき、 登校日数・サポート内容・学費などをまとめて確認できます。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
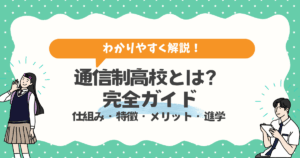
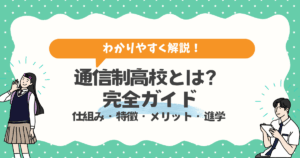
【不登校】学校とのやりとりで親が疲弊しないための心構え


学校との連携は、子どものために必要なことですが、同時に親にとって大きな負担となることもあります。
特に、不登校の長期化や、学校との関係がうまくいかないと感じる時に、親が疲弊しないための心構えは大切です。
学校任せにしない、すべて抱え込まないバランス
「学校に行けないんだから、学校が何とかしてくれるべき」という気持ちと、「親が全てを解決しなければ」という責任感の間で、親は揺れ動きがちです。
しかし、このどちらかの極端な考え方は、親を疲弊させてしまいます。
「学校任せ」にしてしまうと、学校側の対応が不十分だと感じた時に、不満や怒りが募り、学校への不信感が募ってしまいます。
また、学校側も「親が何も言ってこないから、大丈夫だろう」と受け取ってしまう可能性もあります。
一方で、「すべてを抱え込む」ことも危険です。
親が一人で問題を解決しようとすると、心身ともに限界を迎えてしまいます。不登校は、親一人で解決できる問題ではありません。
大切なのは、「学校にできること」と「家庭でできること」、そして「外部の専門機関に頼ること」のバランスを理解し、それぞれが協力し合う体制を築くことです。
「学校に求めるべきこと」と「家庭で担うべきこと」を明確にし、必要に応じて外部の力を借りるという意識を持つことで、親自身の負担を軽減し、効果的な連携を保つことができます。
親自身のメンタルヘルスを守るには
不登校の子どもを持つ親は、常に子どものことを心配し、自分のことよりも子どもを優先しがちです。
でも、親が精神的に疲弊してしまっては、子どもを支える力も失ってしまいます。
学校との連携においても、親自身のメンタルヘルスを守るための「線引き」が必要です。
例えば、学校からの連絡は、すべてを真剣に受け止め、即座に対応しようとせず、「連絡は〇時以降」「緊急時以外はメールで」といったルールを設けることも有効です。
また、学校からの提案が、あなたや子どもの気持ちに合わないと感じる場合は、無理に受け入れず、「一度持ち帰って検討します」「今は難しいです」と断る勇気も必要です。
学校の先生やスクールカウンセラーは、あなたの味方ですが、多忙な中で働いていて、親の負担を理解してくれる先生ばかりとは限りません。
だからこそ、あなた自身が「これ以上は無理だ」というサインを見逃さず、限界を感じたら、迷わず助けを求めましょう。
【不登校】学校とのやりとりは決して無理はしないで


どれだけ努力しても、学校との連携がうまくいかない、あるいは学校の対応に納得できないという状況に陥ることもあります。



私も、何度か「先生とうまく連携が取れない・・・」と感じた経験があります。
そんな時、親は「どうすればいいんだ…」と絶望的な気持ちになるかもしれません。
学校との連携がうまくいかない場合は、悩んでいるよりも「次の選択肢」を考えていきましょう。
例えば…
- 学校の主任、校長や教頭といった上層部に相談をお願いしてみる
- 教育委員会に相談する
- 第三者機関を頼る
- 転校や転学を検討する
大切なのは、「この学校でなければならない」という固定観念にとらわれすぎないことです。
子どもの幸せと成長を第一に考えて、柔軟な考え方を持つこと、そして時には、場所を変えることが子どもにとっても親にとって、新たな希望を見つける大きなきっかけとなることもあります。
不登校になったとき、まず初めに必要なやりとりは、学校との連携です。
精神的にも大変なことですが、親がすべての責任をとる必要はありません。
この記事が心の負担を少しでも減らして、お子さんと共に前向きな一歩になったら嬉しいです。
まずは親御さんが笑顔でいることが、お子さんにとって一番の安心材料になります。
心のエネルギーが少し回復してきたら、次のステップとして、お子さんの「これからの居場所」や「学びの選択肢」について、ゆっくり考えてみませんか?
今すぐ決める必要はまったくありません。「こんな道もあるんだ」と知っておくだけで、親御さんの不安も少し和らぐはずですよ。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる