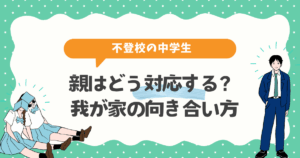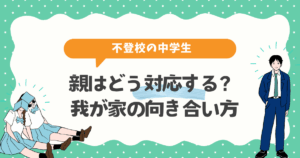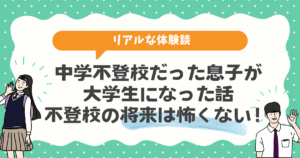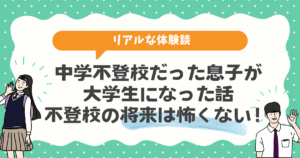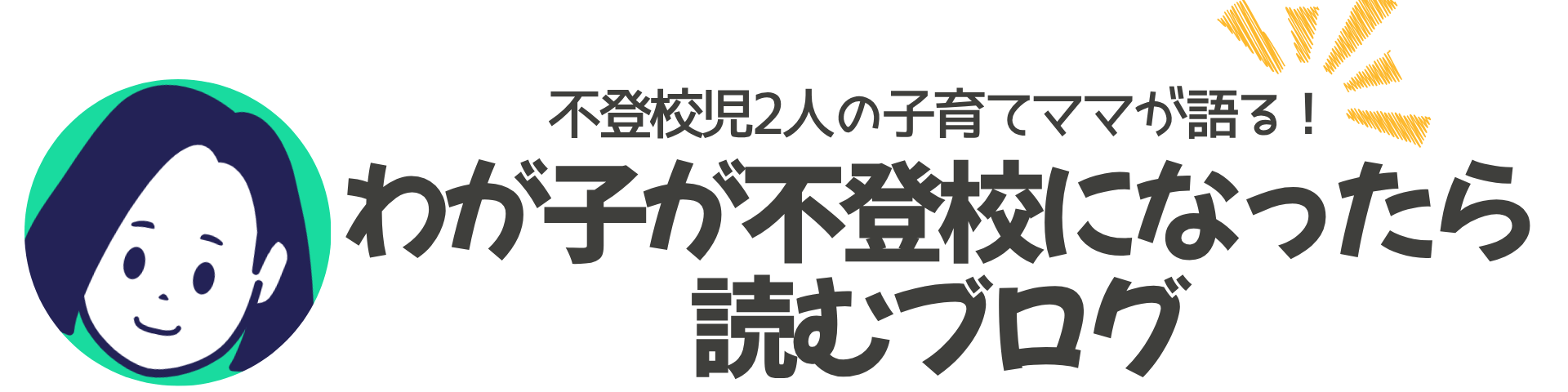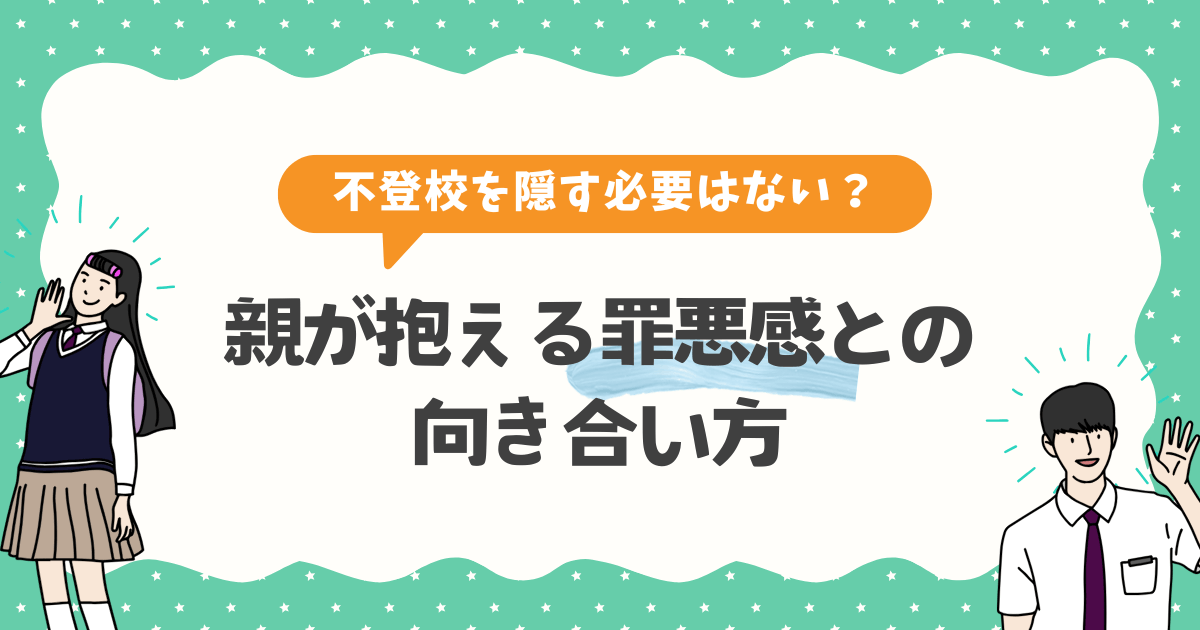「もしかして、うちの子、不登校なのかな?」
そう思い始めたとき、不安、焦り、悲しみ、怒り、そして罪悪感を感じていないでしょうか。
「私の育て方が悪かったのかな…」
「他の子たちは学校に行っているのに、どうしてうちの子だけ…」
毎日、重い荷物を背負って生きているような、そんな気持ちになっていないでしょうか。
 ゆき
ゆき私は今、フルタイムで働きながら2人の不登校を経験した子どもを育てています。かつては、私も同じように、そんな「罪悪感」に押しつぶされそうになっていました。
でも、安心してください!不登校は、決して親のせいではありません。そして、不登校を隠す必要だってありません!
この記事では、私自身の経験も踏まえながら、親が抱えがちな罪悪感の正体、そしてその気持ちとどう向き合っていけば良いのかについて、皆さまと一緒に考えていきたいと思います。
このブログを読んでくれている方の心が、少しでも軽くなるヒントが見つかれば嬉しいです。
不登校で、その先の進路に不安を感じている親御さんも多いと思います。通信制高校は不登校でも受け入れてくれる高校です。まずは資料だけでも取り寄せて、通信制高校について知っておくと安心です。
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
「不登校を隠したい」親が抱える罪悪感の正体


子どもが学校に行かなくなって、まず真っ先に頭をよぎるのは「どうしよう…」という戸惑いですよね。
そして、その戸惑いの裏には、得体の知れない「罪悪感」が潜んでいることが多いものです。
「うちの子だけ?」という孤独感が罪悪感を生む
朝、当たり前のように子どもたちが学校へ向かう通学路を眺めていると、「どうして、うちの子は行けないのかな…」という気持ちが湧いてきます。
幼稚園や小学校からずっと、みんなと同じように集団生活を送ってきたのに、突然うちの子だけが、そのレールから外れてしまったように感じてしまう。
そんな時、私たち親は「うちの子だけがこんな状況になっている」という、孤独感に襲われます。
まるで、自分たちだけが異世界にいるような感覚になり、その孤独感が「何か、私がいけなかったのだろうか」という、根拠のない罪悪感へと繋がってしまいます。



私も、ママ友との会話の中で学校の話が出るたびに、胸が締め付けられる思いがしました。当たり前のように「学校どう?」と聞かれても、どう答えていいか分からず、言葉に詰まるたびに、辛くなっていました。
これは不登校に悩む親御さんなら、誰もが一度は通る感情ではないでしょうか。
「不登校は親のせい」という世間の目に苦しめられていた私
不登校という言葉には、残念ながら、まだまだ偏見や誤解を持たれています。
私自身も、かつてはそう思っていたところがありました。
「親が甘やかしたから」「親が子どもに関心がないから」といった、まるで親に全責任があるかのような無言のプレッシャーを、社会全体から感じてしまうことはありませんか?
私もそうでした。特に、シングルマザーという立場上、「私の子育てに問題があったのか…」と、引け目を感じて必要以上に自分を追い詰めてしまうことが、多々ありました。



周りの人の視線が、「この子は学校に行かない、問題のある子」「問題を抱えた親」として見られているような気がしてなりませんでした。
SNSで楽しそうに投稿される友達家族の投稿、子どもの様子を見るとたびに、自分と比べ、辛くなっていました。
でもこれって、大きな誤解なんです。
不登校の原因は、家庭環境や親の育て方だけではありません。
学校での人間関係、学習への不安、発達の特性、そして社会全体の変化など、非常に複雑な要因が絡み合って起こるものなのです。
この事実をしっかりと心に留めておくことが、不登校は親のせいという世間の見方から自分を守る第一歩になります。
他の子と比べてしまう…親同士の会話が辛かった日々
子どもが不登校になってから、私は意識的にママ友との会話を避けるようになりました。
特に、子どもの学校や習い事、友達関係の話題になった時、どう答えていいか分からず、冷や汗をかく自分がいました。
「〇〇ちゃんは部活で頑張ってるって聞いたよー」「□□くんは成績がすごく伸びたって言ってたよ」といった、他のお子さんの活躍の話を聞くたびに、心の中で「うちの子は…」と比べてしまい、落ち込む私。
そして、そんな風に比べてしまう自分自身にも、また罪悪感を抱いてしまう。
この悪循環から抜け出すのは、本当に大変でした。
子どもを比べるのは親として良くないことだと頭では分かっていても、感情が追いつかない。
この感情は、多くの不登校の親御さんが経験しているかもしれません。
でも大切なのは、この感情を否定せず、「今は辛いよね」と自分に寄り添ってあげること。
そして、この他人と比較してしまう感情は、決して愛情不足からくるものではないんです。
【実体験】我が子が不登校と知られたくなかった正直な気持ち
私が不登校の親として一番つらかったことの一つは、「不登校であることを、周りの人に知られたくない」という気持ちでした。
担任の先生からの電話にさえ、初めのうちは妙な緊張感を感じていたことを覚えています。
ママ友や、習い事の先生、近所の人たちには、なんとか「体調が悪い」「しばらく休んでいる」と、ごまかし続けていました。
どうして隠したかったのか?



今思うと、周りから悲観的に見られることが嫌だったこと、そして「親の育て方が悪い」「シングルマザーだから」という、偏見の目で見られるのが怖かったから。そして「不登校」というレッテルを張られることへの恐怖感もあったかも。
また、子どもが「学校に行けないこと」を、私自身がネガティブなことだと捉えていたからかもしれません。
子どもがかわいそう、この先の人生がどうなるのか不安、という気持ちが強く、「不登校」という事実自体を隠したいという心理が働いていました。
でも、この「隠したい」という気持ちは、実は私たち親をさらに孤独にさせ、子どもを逆に追い詰めてしまう可能性もあるので要注意です。
私はこの経験を通して、不登校を隠すことよりも逆にオープンにして、周りの助けを求めることの重要性を痛感しました。
不登校は隠す必要がない理由~親も子も楽になるために~


「不登校は隠す必要がない」と聞いて、抵抗を感じた方もいるかもしれません。
私みたいに、周りの目が気になる方もたくさんいると思います。
でも、不登校をオープンにすることは、あなた自身、そしてお子さんの未来にとって、とても大きなメリットがあるんです。
不登校は特別なことではない、誰にでも起こりうること
文部科学省のデータを見てもわかるように、不登校の子どもの数は年々増加しています。
もはや不登校は、一部の家庭で起こる特別な問題ではなく、どの家庭でも起こりうる、ごく一般的な現象になりつつあるのです。


あなたのお子さんだけが、特別なわけではないんです。あなただけが、特別な親なわけでもないんです!
私たちの周りには、実は同じように不登校で悩んでいる親御さんが、声を上げられないだけで実はたくさんいらっしゃいます。



私が子どもの不登校で悩んでいることを話したことで、実は子どもの不登校で悩んでいる、過去に悩んでいた、という方がたくさんいることが分かりました。
どうしても、周りが当たり前にやっていることが出来なくなると、ネガティブに考えがちでが、「不登校は特別なことではない」という認識を持つことが、罪悪感から解放される第一歩なんです。
決して不登校は恥ずかしいことではありません。
むしろ、不登校という困難に立ち向かっていることは、子どもに真剣に向き合っていると自信を持ってください!
隠すことで失う「サポート」と「成長の機会」
不登校を隠し続けることは、あなたと子どもの未来にとって、大切なチャンスを奪ってしまうことになりかねません。
まず、必要なサポートを受けられないという点です。
学校の先生、スクールカウンセラー、教育支援センターの担当者、医療機関の専門家など、不登校の子どもたちを支えるための公的な、そして民間の様々なサポート体制があります。


でも、不登校であることを隠している限り、これらの支援にアクセスすることができません。
私自身、最初の頃は学校に詳しい状況を話すことをためらっていました。



私の場合、正直に話すことで担任の先生が子どもの状況をより深く理解してくれたり、スクールカウンセラーとの面談を提案してくれたり、具体的な支援に繋がっていきました。
あの時、勇気を出して話していなければ、今の我が子たちの未来はなかったかもしれません。
次に、子どもの「成長の機会」を奪ってしまう可能性があります。
不登校の子どもにとって、家庭は唯一の安心できる場所かもしれません。
しかし、家庭だけで全ての問題を解決することは困難です。フリースクールや通信制高校といった、多様な学びの場は、子どもが社会との接点を取り戻し、自分らしいペースで成長していくための大切な機会となります。
隠していると、こうした選択肢を検討する機会さえ失ってしまうことになります。
さらに、親自身が孤立し、疲弊してしまうという点も挙げられます。
不登校は長期化することも少なくありません。
一人で抱え込み、誰にも話せない状況が続くと、親の心身が限界を迎えてしまいます。外部のサポートは、親の心を守るためにも不可欠なのです。
子どもが安心して過ごせる「開かれた家庭」の重要性
不登校の子どもにとって、家は「唯一の安全地帯」です。
子どもは、親の不安や緊張を敏感に察知します。
親が「不登校を隠さなくては」とピリピリしていると、子どもは家にいても心が休まらず、かえって精神的に不安定になってしまうこともあります。
私も、息子のときは初めてぶち当たった不登校に余裕が持てなくて、気持ちばかり焦り、子どもと上手く関わることもできませんでした。
でも、学校にも行けず、家にも居づらくなったら、子どもは八方塞がりで辛いんじゃないかと気づき、家庭は「安心して休める、オープンな場所」であることを心掛けました。
そうすることで、子どもは心のエネルギーを充電して、次の一歩を踏み出す力が蓄えられるんだなと感じました。
周囲の目を気にしない!親が自信を持つためのマインドセット


不登校を隠す必要がないと頭では理解しても、実際には周囲の目が気になるものです。
でも、そんな心を縛る「周囲の目」から自由になるための考え方があるんです。
それは、心の持ち方、マインドセットを変えることから始まります。
他人の評価より「我が子の幸せ」を最優先にする視点
私たちは、知らず知らずのうちに「世間の常識」や「他人の評価」に縛られて生きています。
「学校に行くのが当たり前」「友達がたくさんいるのが良いこと」「良い大学に入って良い会社に就職するのが幸せ」…。
もちろん、これらも一つの幸せの形ですが、唯一の幸せの形ではありません。
不登校という状況になった時、私たちは立ち止まって、本当に大切なものは何なのかを問い直す機会を与えられます。
我が子の笑顔、心身の健康、そして何よりも「我が子が幸せであること」。これが、親として何よりも優先すべきことなのではないでしょうか。
世間の評価や、他人からの「こうあるべき」という声は、時にはあなたを苦しめる鎖になってしまいます。
その鎖を断ち切る勇気を持つこと。
「子どもが今、何を必要としているのか」「どうすれば心穏やかに過ごせるのか」という視点を常に持ち、他人の評価軸ではなく、「我が子の幸せ」を最優先に考えるようにしましょう。
そうすれば、周囲の目は自然と気にならなくなってきます。
親自身が「不登校」を正しく理解し説明できるようになる
周囲の目が気になるのは、不登校に対する知識や理解が不足しているからかもしれません。
不登校が特別な病気や怠けではないこと、そして多様な原因があるんです。


そして、さまざまな支援や進路の選択肢があることを、親であるあなたがまず正しく理解してみましょう。
そして、もし誰かに聞かれた時には、慌ててごまかすのではなく、できる範囲で「今は学校をお休みしています。子どもの心と体の状態を優先しています」と、冷静に説明できる準備をしておくことです。
無理に詳細を話す必要はありません。でも、「うちの子は今、こういう状況です」と、あなた自身が明確に説明できることで、あなたの心の中に確固たる自信が生まれます。



私自身も、初めは言い訳ばかりしていましたが、不登校について自分なりに調べたり、専門家の方々の話を聞くうちに、自信を持つことができました。
そうすると、不思議と周囲からの見方も変わってくるんです。自信を持って話すことで、相手も真剣に耳を傾けてくれるようになります。
批判的な言葉は「聞き流す」
残念ながら、中には不登校に対する理解が乏しく、心ない言葉を投げかけてくる人もいるかもしれません。
「〇〇すればいいのに」「甘やかしてるんじゃないの?」といった、無責任な言葉に、深く傷つくこともあるかもしれません。私も経験があるので、その痛みはよく分かります。
しかし、そのような言葉を投げかける人は、不登校の苦しみを本当に理解していない人たちです。
彼らは、あなたの状況を本当に心配しているわけではなく、無知ゆえに、あるいは単なる好奇心から発言しているに過ぎません。
大切なのは、そのような言葉を「真に受けない」ということ。



心の中で「この人は、不登校のことを全く知らないんだな」と割り切り、スーッと聞き流すように意識するとラクになりますよ。
すべてを真剣に受け止めていたら、私たちの心が持ちません!自分の心を守るために、時には適当に受け流すことも必要です。
自分にとってプラスにならない情報は、積極的にシャットアウトしてしまうのがおすすめです。
SNSで心がざわつくような投稿を見かけたら、一時的にミュートする、ブロックする、といった対策も有効です。
「罪悪感」を手放すための具体的な行動と心のケア


罪悪感は、親の心に重くのしかかり、時には心身を壊してしまいます。
でも、安心してください。その重荷を少しずつ手放していくために、具体的な行動と心のケアをする方法を試してみましょう。
信頼できる人に話すことが孤独から抜け出す一歩
不登校の親が最も苦しいのは「孤独」です。一人で抱え込んでいると、罪悪感はどんどん膨らんでしまいます。
だからこそ、信頼できる人に話すことが、その孤独から抜け出すための最初の一歩になります。
もし身近にそういう人がいなければ、不登校の親の会、自治体の相談窓口、スクールカウンセラーなど、専門の第三者を頼ることは非常に有効な手段です。



私も最初は話すことに抵抗がありましたが、スクールカウンセラーの先生に聞いてもらった時、「私の話を理解してくれる人がいる」というだけで、心がどれだけ軽くなったか分かりませんでした。
「こんなこと話したら、どう思われるだろう?」という心配は無用です。
あなたの話を否定せず、ただ耳を傾けてくれる人を見つけてください。
話すことで、自分の感情を整理でき、客観的に状況を見つめ直すことができるようになります。
そして、あなたが一人ではないことを実感できるはずです!
親自身の心を満たす時間を意識的に作る
不登校の子どもに寄り添う親は、常に子どものことで頭がいっぱいで、自分のことを後回しにしがちです。
でも親が疲弊してしまっては、子どもを支えることも難しくなってしまいます。
だからこそ、親自身の心を満たす時間を意識的に作ることがとても大切なんです。
- ストレッチなど軽い運動
- ゆっくり湯船につかる
- 好きな食べ物やスイーツを食べる
- 好きな音楽を聴く
- 読書をする
- ゆっくりお茶やコーヒーを味わう
- 美容に時間をかける
- たっぷり寝る



たとえ短時間でも、「ホッとできる」「楽しい」と感じることを、日常の中で意識的に取り入れてみてください!
「こんな時に自分だけ楽しんでいいのだろうか」という罪悪感が湧くかもしれませんが、それは違います。
あなたが心身ともに満たされていることが、子どもにとって最大の安心材料になるんです。
あなたが笑顔でいれば、子どももきっと安心してくれます。
自分をケアすることは、決して「怠け」ではなく、子育てのための「投資」だと考えると気持ちがラクになりますよ。
完璧な親ではなく「十分な親」を目指す
私たちは、つい「完璧な親」であろうとしすぎてしまいます。
特に、子どもが不登校という状況になると、「もっと完璧でなければ」と自分にプレッシャーをかけてしまいがちです。
でも、完璧な親なんて存在しません。完璧を目指せば目指すほど、逆に苦しくなってしまうだけです。
「Good Enough Mother(良い加減な母親、十分な母親)」という言葉があります。
子どもに対してイライラしてしまうことも、上手くいかない日もあります。
それでも、私たちは十分頑張っています!愛情を持って子どもに接し、子どものために悩み、心を痛めています。
それだけで、すでに「十分な親」なんです。
「今日は〇〇ができなかった」と自分を責めるのではなくて、「今日は〇〇ができた!」と小さなことを肯定してあげることが大切です。
不登校を経て、親も子も「自分らしく」!


不登校は、親にとっては本当に辛く、先が見えないトンネルの中にいるように感じるかもしれません。
私自身もそうでした。でも、そのトンネルの先に、必ず光はあります。
そして、不登校という経験が、親も子も「自分らしく」生きるための大きな学びとなることもあるのです。
不登校が教えてくれた「親子の絆」の深め方
不登校になる前は、当たり前のように過ぎていく日々の中で、子どもと深く向き合う時間が少なかったのかもしれません。



不登校になったことで、私は子どもと改めて向き合う時間が増えました。
学校に行けない子どもが何を考え、何に苦しんでいるのか。どうすればこの子の心を支えられるのか。
そう考えるうちに、私たちは以前よりも深く話し合うようになり、特に反抗期が終わった息子とは「あの頃は…」と不登校だった時の話を笑って出来るようになりました。
とはいっても、当時はぶつかり合うこともたくさんあったし、まともに話ができない時期もありました。
きれいごとばかりではない時間も、今では一緒に乗り越えたことが絆となって、良い親子関係を築くことに繋がりました。
隠さずに前向きに進むことで得られた経験と学び
私は、初めは隠していた不登校について、オープンにすることを選びました。(とはいっても、言ってもいい人、言わない方がいい人の判断はしました)
最初は勇気がいりましたが、正直に打ち明けることで多くの学びや経験を得ることができました。
- 学校では正直に状況を相談し、連携することで、知らなかった支援制度、情報などを知ることができた
- 信頼できるママさんに状況を話すことで、気にかけてもらったり、他の不登校のママさんを教えてもらって情報を共有することができた
- 職場の人に相談することで、不登校を経験した方を教えてもらい、相談することができた
そうすることで、だんだんと私の中の不安や罪悪感も薄れてきて、気持がラクになってきたことで家庭内の雰囲気も良くなり、子どもとの関係も良い方向へ変わっていったんです。
不登校は、私たち親子にとって大きな試練でしたが、それを乗り越えようと努力した経験は、何ものにも代えがたい「強み」となりました。
不登校という経験が子どもの「強み」になる時
「中学校で不登校になって、この子の将来はどうなるんだろう…」
こんな風に心配になっていませんか?私はまさにそうでした。
でも大丈夫、安心してください!不登校の経験は、決してマイナスなことばかりではないんです。
学校という画一的な枠組みから外れたことで、子どもは「自分って何なのか」「どう生きたいか」ということを深く考える機会を得ます。
自分の心と向き合い、本当に好きなことや得意なことを見つける時間を持つことができます。



中学時代の不登校から通信制高校へ進学して、今は大学に進学しました。学校やバイト、習い事などから人との出会いに繋がって、自分の興味を深めることができています。



私は不登校から専門コースがある通信制高校に進学。自分のペースで学びながら、興味のある分野を積極的に挑戦しています。
子どもたちは不登校という経験を通して、「自分軸で生きる力」「困難を乗り越える粘り強さ」「多様な価値観を受け入れる寛容さ」を身につけてきたんじゃないかな?と感じます。
そして子どもたちは、通信制高校に進学したことで、自分らしい新たな道を見つけ、自分の可能性を広げることができたと感じています。
子どものエネルギーが回復すれば、驚くほどのスピードで学びを取り戻せるケースも多いです。
大切なのは、「今の」子どもの状態に合った学びの環境を選んであげること。
全日制高校だけが選択肢ではありません。最近では、不登校サポートが手厚い通信制高校や、個性に合わせたフリースクールなど、多様な学びの場が増えています。
まずは「どんな選択肢があるのか」を知ることから始めてみませんか?
関連記事: 通信制高校の選び方【決定版】はこちら
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
不登校でも大丈夫!罪悪感は不要!


今、あなたが不登校という状況で、心の奥底で罪悪感を抱え、先の見えない不安を感じているとしたら、正直、「不登校でよかった」なんて、到底思えないですよね。私だってそうでした。
でも、時間が経ち、子どもたちがそれぞれの道で、自分らしく輝いている姿を見るたびに、私は「不登校という経験は、決してマイナスではなかったのかも」と、前向きに思えるようになりました。
今は、すべてが私たち家族にとっては必要なプロセスだったのかな?と、思えるようになったんです。
不登校は、親子が共に成長し、本当の幸せとは何かを問い直すための貴重な機会ですが、決して一人で抱え込まないこと、そして自分を責めないことは忘れないでほしいです。
不登校は、終わりではないんです。親が笑顔で前向きで過ごすことで、子どもの気持ちも前を向いて未来が開けていくはずです!私もあなたのことを応援しています!
\【無料】気になる学校をまとめて資料請求/
\ズバット通信制高校比較のオススメポイント3つ/
(1)診断で子どもにあった学校を絞り込みできる
(2)一括資料請求で効率よく情報が得られる
(3)口コミが見られる